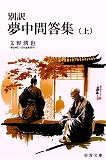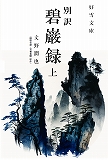足利直義:「修行者の理解度にバラツキがあるから説明の仕方も変わる」、というのはよくわかります。
では、なぜ人々の理解度、というか学習能力にはバラツキがあるのでしょうか?
夢窓国師:究極の真実の境地から見れば、「人」もいなければ「法」もない。
ただ、いきなりそんなことを言ってもついてこられるヤツはほとんどおらんので、説明の都合上、仕方なく「人」と「法」が違うものであるかのように説いたのじゃ。
人々の学習能力をタイプ別に分類すると、およそ次の五種類になる。
- 声聞(しょうもん)性
- 縁覚(えんがく)性
- 菩薩(ぼさつ)性
- 不定(ふじょう)性
- 闡提(せんだい)性
声聞性は「教えてもらって悟る」タイプ、縁覚性は「自力で悟る」というタイプで、どちらも自分を救うことにしか興味がないという点で共通しておる。
だから「小乗(自分一人だけしか乗れない小さな舟で彼岸に渡ろうとする)」と呼ばれるのじゃ。
そして、自らを含む全ての生き物を救済しようとするのが「大乗(大きな船)」で、これを悲願とするタイプが菩薩性じゃ。
これに対して、時によって大乗だったり小乗だったりして安定しないタイプを不定性と呼ぶ。
最後の「闡提」というのは、一切の仏法を否定していて救いようがないという意味じゃ。
人間は本来みな平等であるべきなのにこのように様々なタイプに分かれてしまうのは、全人類の心の底に「無明(むみょう:とてつもない愚かさ)」があるからじゃ。
そして、仏教ではそれらのタイプに対応した教え方があるというわけじゃ。
円覚経に「人を含めたあらゆる生き物の心の奥底には、『生存本能』と呼ばれる貪欲さが潜んでいる。そしてその挙動は個体によって異なるため、五種類のタイプに分かれてくるのだ。円覚の智慧はただひとつだが、相手のタイプによって説明の仕方を変えざるを得ないというだけのこと。本当のことを言えば、救済する側(菩薩)と救済される側(衆生)の区別もない。そういう意味では、菩薩も衆生もマボロシであるといえる」と書かれておるのは、つまりそういうことじゃ。

☆ ☆ ☆ ☆
★別訳【夢中問答集】(中)新発売!(全3巻を予定)
エピソードごとにフルカラーの挿絵(AIイラスト)が入っています。
上巻:第1問~第23問までを収録。
中巻:第24問~第60問までを収録。
別訳【碧巌録】シリーズ完結!
「宗門第一の書」と称される禅宗の語録・公案集である「碧巌録」の世界を直接体験できるよう平易な現代語を使い大胆に構成を組み替えた初心者必読の超訳版がついに完結!
全100話。公案集はナゾナゾ集ですので、どこから読んでもOKです!
★ペーパーバック版『別訳【碧巌録】(全3巻)』