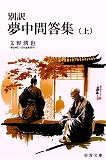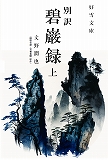足利直義:なるほどですね……
和尚の話を聞いていて思ったのですが、禅宗ではよく教導手法において「理致」「機関」という区別を用いますが、これはそれぞれどういったものなのでしょうか?
夢窓国師:禅の教導手法にそのような区別はない。
ただ、そう言ってしまうと身も蓋もないので、一般人にわかりやすくするために、理屈を説く手法を仮に「理致」と呼び、それ以外の、例えば棒で殴ったり急に大声を出したりする手法を仮に「機関」と呼んだまでのこと。
そう、全ては「召使いへの指示」なのじゃ。
ワシらはよく仲間内で「馬祖和尚や百丈和尚の時代は理致がほとんどで、たまに機関を用いていたが、それ以降は逆にほとんど機関で理致は少しになってしまったなぁ。これも時代の流れか……」と言っておるよ。
今どきの連中ときたら、理致が好きなヤツは機関をバカにし、期間が好きなヤツは理致を嫌がっておるのじゃが、みな物事の本質がわかっておらんと言うほかない。
もし機関がそんなに優れているのなら、それを多用しなかった馬祖・百丈の両和尚はボンクラだとでも言うつもりか?
また、理致が優れているのなら、機関を多用した臨済和尚や徳山和尚はただのバカなのか?
お釈迦様は悟りを得てから亡くなられるまでの約五十年間で、およそ三百種類の教導手法を用いたという。
しかし楞伽経には「釈迦は究極の悟りを得てから亡くなるまでの間に、ただ一言の教えも説かなかった」と書かれておる。
これがいったい何を意味しているか知っているなら、なんの理致を嫌がることがあるものか!
かつて法眼和尚が覚鉄觜和尚に「貴方の師匠の趙州和尚は、『達磨大師がインドから中国まで来たのは何のためか?』と問われて、『庭前柏樹子(ていぜんはくじゅし:そこにビャクシンの樹がある)』と答えたそうですね」と言ったところ、覚鉄觜和尚は「師匠はそんなつまらんことは仰らない。バカにしないでくれ!」と答えたそうじゃ。
覚鉄觜和尚は趙州和尚の高弟じゃ。公案にまでなっているこの故事を知らないハズがない。
なのに「そんなことは言わない」と答える覚鉄觜和尚の心意気を知るがよい。
この公案についてアレコレと論じておる連中は彼の足元にも及ばんよ。
庭前柏樹子の公案だけではない。
師匠たちが示してくださった公案の数々は、全てこれと同じこと。
手段が変わったからといって効能の良し悪しをあれこれ取り沙汰するようなヤツらは皆、師匠たちの真意を曲解しておるのじゃ。
究極の真実に目覚めて真の自由を得た人物は、手にした純金を土に変え、手にした土を金に変えることができる。
それを外から見ているヤツらが「アイツが手にしているのは金だ!」とか「土だ!」とか取り沙汰したところで何の意味があるというのか!
……まぁ、言ってしまえば、教導手法などというものは、みんなそういった感じじゃよ。
物事のわかった人物の言動を「理致」「機関」に分類したところでなにも始まらん。

☆ ☆ ☆ ☆
★別訳【夢中問答集】(中)新発売!(全3巻を予定)
エピソードごとにフルカラーの挿絵(AIイラスト)が入っています。
上巻:第1問~第23問までを収録。
中巻:第24問~第60問までを収録。
別訳【碧巌録】シリーズ完結!
「宗門第一の書」と称される禅宗の語録・公案集である「碧巌録」の世界を直接体験できるよう平易な現代語を使い大胆に構成を組み替えた初心者必読の超訳版がついに完結!
全100話。公案集はナゾナゾ集ですので、どこから読んでもOKです!
★ペーパーバック版『別訳【碧巌録】(全3巻)』