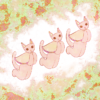恒例の間違い探しです。
前回のタイトル絵と違う箇所はどこでしょう?答はこの記事の最後に。
この記事は連続ものの4回目です。これまでの記事はこちら→ 1回目 2回目 3回目
描かれた絵と、書かれなかった言葉
こんにちは。地球フィクション研究家、猫型宇宙人の猫丸です。
さて、脱線しながらついにたどり着いた。今日こそ、すごく面白かったマンガ、つばな『バベルの図書館』について書きたい。
さっそく内容を少し紹介すると、本作の主人公は中学校の同級生である相馬(あいば)かなえと渡瀬量。
二人はそれぞれに、人と違う世界の感じ方を持つキャラクターだ。相馬かなえは、幼い頃の不思議な体験をきっかけに、この世界は嘘に満ちていて、目に見えない本当の世界があると密かに信じるようになる。渡瀬量は、言葉に関する独特の感受性、特殊能力の持ち主で、彼がその能力を使って相馬かなえの「目に見えない世界」のほんの一旦を覗き見たこと、観測・干渉したことが、二人の間のある事件に繋がるという物語だ。
渡瀬量は「言葉はパターンで文字は記号の組み合わせでしかない」と思っている。しかし、相馬かなえが選び、組み立て、物語のように書き綴る文章に他の人の言葉にはない美しさを感じて惹かれる。面白いのは、渡瀬量が独特の感受性で「感じる」ことができるのは「言葉」だけだということだ。彼が目で見て読み取る言葉は日本語などの文字で書かれているが、頭の中で感じている言葉は、ギリシャ文字ともアラビア文字ともつかない奇妙な記号の形をしている。そして彼は、「絵」に関しては何ら特殊能力を持っていない。だからこそ、自分の能力を使って密かに見ることのできない、相馬かなえの描いた未完成の絵を見てみたいと願っている(そしてそれは叶うことがない)
その後、相馬かなえが渡瀬量のためだけに贈った絵を、だが彼は見ようとしない。そこにあるものを見ず、読みたかった言葉を自分だけの世界の中で読み取ってしまう。このことが終局へ向かうターニングポイントにもなっている。
文字の時間は止まっている
すでに書かれている言葉も
これから書かれる言葉も
全部「そこ」に書いてある
お前が読んだのは書かれなかった言葉だよ!!つばな『バベルの図書館』より
自分が過ちを犯したのでは、と悟った渡瀬量の心に現れる言葉だ。
前回紹介した福永武彦『死の島』の中で、小説(言葉)を書いている主人公・相馬鼎が、画家である萌木素子の作品(絵)に惹かれるという構造をつい連想する。相馬鼎は萌木素子の絵を、そこに込められた彼女の「魂」を理解していると思っている。だがそれを言葉にして聞かされた萌木素子は何も理解されていないと反駁する。本作で描かれる破綻は、この二人の間の断絶とどこか似ている。
ボルヘスの「バベルの図書館」にもない物語
『バベルの図書館』は、「描かれなかった物語」「あったかもしれない可能性」が描かれて終わる。(たぶん)そう見る読者が多いだろう。だが、作者は決してどちらが現実に起こったことで、どちらが選ばれず幻に終わった選択肢なのかを作中で明らかにはしていない。悲しく切ない物語にもハッピーエンドにも見え、いくつもの受け取り方のできる物語だ。私自身は、どれが現実に起こったことだと思うから、というのではなく、むしろそこが本質ではないからという理由で、希望や明るさのある物語だと感じた。ぜひ実際に読んでみて、どういう物語だと感じるか、確かめてほしい。そこにあなたの「異世界感覚」が表れるだろう、ということは後で書く。
さて本作と同じタイトルを持つボルヘスの短編小説『バベルの図書館』に登場するバベルの図書館とはどんな図書館かというと「そこにはアルファベットのあらゆる順列からなる本、つまりは過去に書かれた、あるいは未来に書かれるどのような本もあるのだそうで、他ならぬ「バベルの図書館」という小説もまたその図書館にすでに存在するという奇妙な無限円環をなしています」(ホテル暴風雨図書館司書・バベルさん:談)
だということだ。作者も当然、この先行する作品を意識していたはずだ。
ボルヘスの書いた「バベルの図書館」には、この世に存在する、あるいはしない、あらゆる物語がある。だが、そこに「マンガ」や「絵」は収められていない。つまり本作は、決して描かれることのなかった、バベルの図書館にも存在しない物語を描いているともいえる。
そういう意味で、同タイトルであるボルヘス『バベルの図書館』よりも、書かれなかった何かを炙り出すような福永武彦『死の島』の方をより強く連想させた。
さらに、渡瀬量が言葉に関するその能力を駆使しても描くことのできなかった物語があるということ、つまり「バベルの図書館」にも存在しない物語があることを、彼の能力が感知できない「絵」を象徴的に登場させるという、マンガでしかできない視覚的な方法で表現しているところが面白い。
未だかつて描かれなかった物語などもうないかもしれないし、書かれた言葉も書かれなかった言葉も可能性の組み合わせでしかないが、具体的にどこかに描かれ、誰かに語られた物語は、独自の生命を得て生きているというイメージ。そこがこの先品に、先述した「明るさ」や「希望」を感じる点だ。
異世界への扉
福永武彦「死の島』(とボルヘス『バベルの図書館』)との連想で感じたことを主に書いたが、それとは別に、この作品、そして同じ作者の他作品にも通じる魅力は、独特の異世界感覚だと思う。
誰とも共有することのできない、人と違う感じ方というのは、それ自体が異世界への入口のようなものではないだろうか。
例えば私は宇宙人であるので、地球人類と違って、地球上の世界こそが「異世界」である。地球上にいると、この小さな星全体が自分にとっての「外」、それ以外すべての広大な宇宙が「内」だという感覚にとらわれることがある。私の故郷なり来し方なりも無限に広がる宇宙そのものではないというのに、虫眼鏡で覗いたミニチュアの世界のような地球こそが今自分の見ている「対象」であり「外」で、それ以外は人には見えず自分の目からも隠された「内」、光の当たっていない体内や脳内の暗がりのような気がしてくる。地球上の人々とは裏返しの世界を見ているような、自分自身が地球とそれ以外を裏返す対称中心であり両者をつなぐ扉であるような奇妙な感覚である。
地球人類の方々にもきっと、自分にしかわからない、他の人と違う感じ方というものがあるだろう。そういう感じ方というのは自分の中の閉じた秘密であるばかりではない。「もしほんの少し巡り合わせが違ったら、こうなっていたかもしれない」と思わせる重要な分岐点や選択は、「自分だけが感じられる世界」に、少なからず関わってはいないだろうか?自分自身に干渉し、決定する最大の異世界が、自分の感覚の中にあるような気になったことはないだろうか?
『バベルの図書館』『第七女子会彷徨』『惑星クローゼット』などのSF色のあるつばな作品はどれもそうした、脳や身体の中にある奇妙な感覚と近縁の異世界を視覚化したような魅力がある。
↑画像は7巻より7巻らしさのある『第七女子会彷徨』8巻表紙!(というのは私の意見ではなく作者があとがきで言っているのだ)
ちなみに『第七女子会彷徨』の主人公の一人、「金やん」こと金村町子の名前は、尾崎翠『第七官界彷徨』の主人公、小野町子から取ったと思われる。そしてもう一人の主人公、金やんいわく「愛くるしいほどのアホ」であるところの友達の「高木さん」のフルネームは何?と読む途中で気にならない人はいないだろう。意味なく隠されているわけではなく、最後まで読むとなるほどと思うので読んでのお楽しみだ。この作品は全体にコメディータッチでとても楽しく読め、『バベルの図書館』のテーマをもっと感覚上リアルに、ポジティブにした、永劫回帰の現代版解釈のような物語で本当に素晴らしい。またいつか詳しく研究して書きたいものだ。
↑2018年7月24日発売の『惑星クローゼット』2巻
そして『惑星クローゼット』の主人公は女子中学生・アイミこと杉沢愛海(すぎさわ・あいみ)だ。単独では思いつかなかっただろうが、『バベルの図書館』相馬かなえの登場の後では、『死の島』のヒロインの一人「相見綾子(あいみ・あやこ)」をつい連想してしまう。『惑星クローゼット』でアイミが夢の中の世界で出会う少女は自分の名前を忘れていて、アイミによって「フレア」と呼ばれることになるのだが、このフレアの本当の名前が「モエ」や「モトコ」だったりしたらどうしようと今から大変ドキドキしているところだ。
という妄想はさておき、続刊がとても楽しみです。
猫丸の地球虚構研究、いかがでしたでしょうか。
次回もどうぞお楽しみに。
ご意見・ご感想・猫丸さんへのメッセージはこちらからお待ちしております!
※間違い探しの答:猫魚になった猫丸さんの耳の先のアンテナが、片方真珠色になっています。