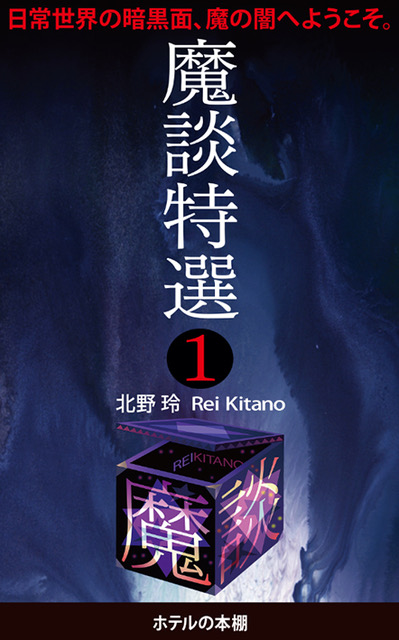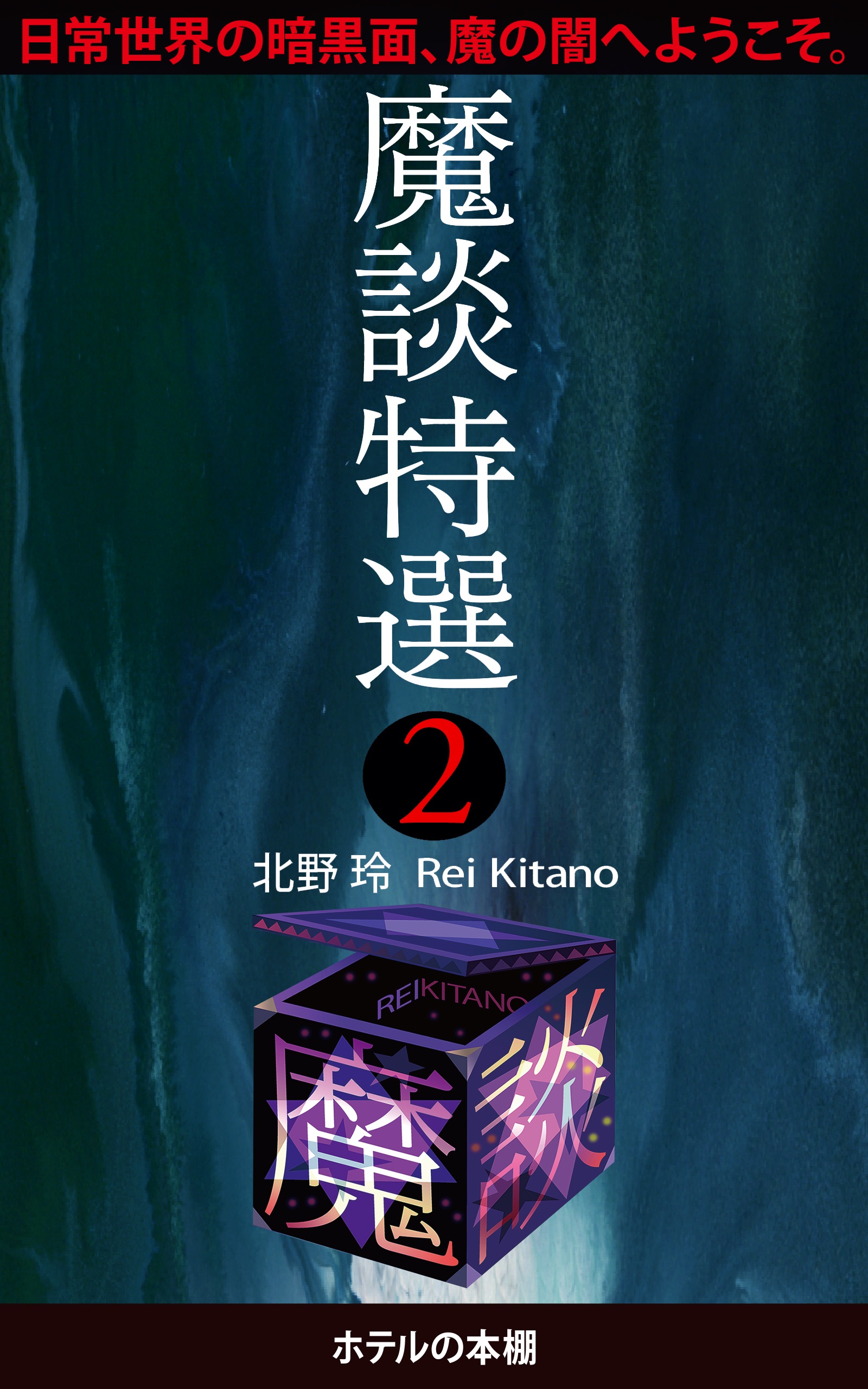【 飢餓遺伝子 】
「初めて叡山に入って修行僧となった時やけどな」とくまさんが語ってくれたことがあった。
「食事のひどさには、それはもうびっくりしたもんや」
実際、「びっくりした」どころの騒ぎではなく、栄養失調による眩暈(めまい)やら体調不良やら意気消沈やらで山を降りる修行僧は毎年のように出たらしい。
私はその話を聞きながらかずくんをチラッと見た。彼はまだ少年であり修行僧ではない。しかし修行僧の年齢となり修行僧としてこの山に入った時に、彼が一番恐れているのはまさにそのことだろうとすぐに想像はついた。彼はうつむいて黙って聞いていた。
「こりゃあかん。修行どころか、こんな食事じゃ体が持たん。何回もそう思ったもんや」
くまさんは叡山から琵琶湖に向かって山を降りたところにある坂本(大津市)の出身だった。
坂本といえば、歴史愛好家は「ああ、明智光秀」と連想するに違いない。魔談でも2020年1月3日「魔の湖底」で坂本と光秀を語っている。
坂本に暮らす人々にとって、叡山はまさに「故郷の山」だ。四方を山に囲まれた京都とは違い、叡山は目の前にドーンと屹立する「信仰の山」でもある。僧を目指す者にとってそこで修行するのは半ば当然の理想であるに違いない。しかし20代や30代の修行僧にとって「極貧の食事」というハードルは相当にキツイ。仮に「もうあかん。死んでまう」という追いつめられたギブアップ気分となって山を降りてしまったら、故郷である坂本で暮らすこともできなくなってしまうだろう。

「……ところがな」
くまさんは自分の体に起こった変化に驚いたことがあった。いつも腹を空かした生活で体力が次第に低下していくのは気がかりだったが、「他の修行僧を見ろ。人間はこんなことじゃ死なん」といった背水の陣的一大覚悟で修行生活を淡々と続けているうちに、あるとき体力がグッと持ち直してきた実感をありありと感じたというのだ。
彼は人差し指をスーッと滑らせて下降する線を示した。体力低下を意味する線だった。指先はどんどん下降していったが、あるところでグッと持ち直した。その後はほぼ「横ばい」ながら微妙に上昇した。
「自分でも信じられへんような変化やったな」
なにしろ食事の献立を自分で決めることはできない。毎日用意されたものだけを感謝して淡々と食べるしかない。そのような最低限の食事で栄養不足・体力低下に驚いた体が(意識とは関係なく)自ら体力回復の応急処置をとったというのだ。
この話を聞いた8歳の時点では「体は不思議な働きをすることがあるのやな」程度の感想でしかなく、正直なところピンと来なかった。くまさんやかずくんは毎日の食事に大いに不満があったに違いないが、私はそうでもなかった。それなりに「これでええ」と思っていたぐらいだった。ただくまさんのこの話は、その後長らく記憶に残った。「満腹はあかん。人間は空腹の方がええ」といった漠然とした確信が私の中で生き続けたことは間違いない。
その後、私は49歳の時に「菜食主義の人々を取材して本にする」というルポルタージュの仕事であちこち動いていた時期があった。その時に「サーチュイン遺伝子」の話を(菜食主義者から)聞いた。別の菜食主義者は「飢餓遺伝子」と言っていた。
簡単に説明するとこういうことである。人間はその長い進化の過程で、寒さや飢えなどじつに様々な過酷な環境を通過してなんとか生き延びてきた。その過酷さゆえに獲得したのが「生命力遺伝子」というものであり、その活性化によって免疫力を高めることができたというのだ。
このありがたい生命力遺伝子はもちろん我々人類全てが潜在能力として体の中に有している。しかし(ここが最も大事な点なのだが)飽食時代を謳歌し、「これは別腹」などと都合の良い言葉をでっちあげ、食事のたびに満腹となって幸福を感じているような人間では、生命力遺伝子は機能しない。まさに「自分の出る幕じゃない」てな感じで引っこんでしまうというのだ。誠にもったいない話ではないか。
ではどうするのか。菜食主義者たちは口を揃えて「お肉なんか食べない方がいい。野菜と果物だけにして、なおかつ常に空腹を維持すること。これこそが長生きの秘訣」だというのだ。また別の「フィッシュベジ」と呼ばれる人々は、魚は普通に食べる。野菜も果物も食べる。しかし少食でおさえる。「腹七分」こそが最も大事な点だと言った。
またチベットのことわざでこんなのがあるという。
「長生きの秘訣は、半分だけ食べて、2倍歩いて、3倍笑って、無制限に愛すること」
さてあなたはどう思います?
【 つづく 】