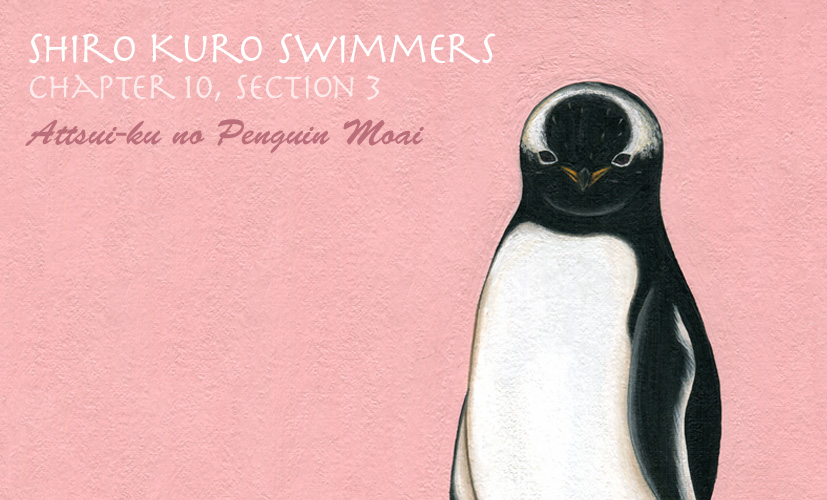
ペンギンモアイ行きのペンギンバスに乗り込んだ慈円津(じぇんつ)は、ガイドブック片手にウキウキペンペン観光気分である。
「あ、慈円津さん、こんぺんは」
「あら、真軽仁(まかろに)さんじゃない。もしかしてペンギンモアイに行くの?」
バスに後から乗り込んできたのはマカロニペンギンの真軽仁サラ世であった。あのおっちょこちょいでドジっ娘な真軽仁である。相変わらずイカを持っている。
「はい、そうです。ペンギン書道家の間で、ペンギンモアイに行ってイカを供えると書道の腕が上がるという噂、『イカ祈願』というのがあって行ってみようかなと」
真軽仁は慈円津の横の席に座った。
「あらそうなの。そういえば、真軽仁さんって、書道店やっているものね」
「はい。イカは食べるのも大好きですが、イカスミ書道は私の生き甲斐です」
真軽仁は、書道店を営む書道家なのである。イカスミで書いた書道作品はイカの芳しい香り付きだ。その上、真軽仁の書は純真で勢いがあり蒐集家の間でも評価は高い。
真軽仁は、持っていたイカのひとつを慈円津に差し出した。
「おひとつどうぞ」
「あら、ありがと」
慈円津は、もらったイカを華麗に丸呑んだ。
「慈円津さん、今日は店やアイドル活動はお休みしていいんですか?」
「最近、魚醤を王さんの酒屋に卸して配達してもらっているの。だから、以前ほどカチューシャ屋は忙しくないのよ。順子に店番をお願いしたりしてるわ。アイドル活動は、ぼちぼちペンペンね」
真軽仁もイカを一匹丸呑んでから言った。
「そうなんですね。だから、ペンギンモアイに観光しに行くんですね」
「あら、違うわよ。観光じゃないの」
先程まで観光気分だった慈円津だが、きっぱりと否定した。
「是非、と頼まれてペンギンモアイの怪現象の調査に行くの」
慈円津は経緯を話しだした。真軽仁は興味深そうに耳を傾けている。
「……で、アッツイ区テイストにブレンドした魚醤を土産店で販売してもらうつもりなワケ」
「そうなんですね。私も、イカスミ書道作品を委託販売して欲しいな」
「あら、じゃあ、私の調査を手伝ってくれればいんじゃない?」
「いいんですか?」
「構わないわよ」
慈円津は丸い腹をペンと叩いた。そして、「真軽仁さんは私の助手、ワトソンくんね」などとすっかりホームズ気分だ。こうして、慈円津と真軽仁という全く頼りにならない二人がペンギンモアイの調査に赴くこととなった。
慈円津と真軽仁は、終点のバス停「ペンギンモアイ前」に降り立った。アッツイ区の暑い日差しの洗礼を受け、慈円津の体は早くも汗ばんでいる。
「暑いわ」
「慈円津さんは、スズシ区の人だから暑いのが苦手なんですね。私は、ヌルイ区に住んでいるので、さほど辛くはありません」
二人はペンギンモアイへと歩き出した。バスの中からもペンギンモアイの奇妙な様子は分っていたが、近づくとその異変は明確になった。ガイドブックに掲載されている整然と並んでいる写真とは違い、モアイたちはバラバラの方向を向き、好き勝手な場所にいるのだ。しかも、「熱々モアイ土産店(あつあつもあいみやげてん)」の周りには、ペンギンモアイが全くいない。こんなペンギンモアイから離れた土産店にわざわざ立ち寄る観光客は少ないのではないだろうか。
二人は、土産店に入った。案の定、客は一人もいない。
「いらっしゃいっス!」
「いらっしゃいっス!」
「いらっしゃいっス!」
暇を持て余していた学生アルバイト店員の声が出迎えた。柄箱(がらぱご)・柄箱川(がらぱごがわ)・柄箱山(がらぱごやま)のス太郎たち三人組である。ス太郎たちは、店に入ってきた慈円津の顔を見ると、大仰に驚いた。
「ずぇずぇ!トップアイドルの慈円津サエリさんっスか!」
「もしや、電話の『じぇんつさん』って慈円津サエリさんだったんスか!?」
「わほぉ、握手してくださいっス!」
大興奮のス太郎たちは、慈円津を握手やサイン攻めにした。ついでに、真軽仁までも握手やサイン攻めにあっている。
「あらあら、今日はアイドル業じゃないんだけどなぁ」
当の本人たちも、まんざらでもない様子だ。
そこに店に入ってきた人物がいる。年配で恰幅の良いそのガラパゴスペンギンは、慈円津たちに近づいてきた。
「初めまして、慈円津さんでスね。私、アッツイ区長の柄箱巣ス平(がらぱごす・すっぺい)でス」
アッツイ区長であった。区長の紳士らしい挨拶に、慈円津も可愛らしいアイドル的な挨拶を返し、真軽仁を紹介する。
「区長さん、よろしくお願いしますね。こちら、助手の真軽仁さんよ」
真軽仁は、持っていたイカを一匹、「お近づきにどうぞ」と区長に差し出すと、
「やや、これはこれは、かたじけないでス」
と、区長はイカを威厳ある丸呑みに。そして、クチバシをペンギンモアイ柄のハンカチで拭きながら、感心したように二人の顔を見た。
「しかし、このような可愛らしいお嬢さん方が、あの噂の黃頭さんの代理とは頼もしいでス」
「うふふ……そうかしら」
慈円津はミステリアスに目を細めると、真軽仁も真似をして目を細める。ミステリアスを装う二人の妙な一体感がさらにミステリアスな雰囲気を増長させ、ス太郎たちは、「スゴイっス!」「ミステリアスっス!」「スっス!」とまたも大騒ぎだ。その騒ぎを制するように、区長が片フリッパーを眼前に出し言った。
「早速でスが、現場に向かいましょうでス」
区長に促され、調査が開始された。店を閉めて同行するス太郎たちも加えた一行は、土産店から一番近いペンギンモアイに向かった。外に出ると、日差しは先程よりもさらに暑くなっている。スズシ区の慈円津には慣れない暑さだ。しばらくして、巨像ペンギンモアイの足元に到着した。
「あらやだ本当だ、動いているわ」
間近で見るとペンギンモアイは、ほんの少しずつだが動いているのが分かる。
「モアイが動く理由はなんでスか?」
「なにかしら?」
「なんでしょう?」
慈円津と真軽仁は、ス太郎たちと区長の期待の眼差しを受けているが、一向に気にせず、「大きいわね」とか「記念写真を撮りましょう」とか楽しげである。真軽仁は、持っていたバッグからカメラを取り出そうとした時、重大なことに気がついた。
「あ!写真どころじゃないです、慈円津さん!」
区長とス太郎たちがウンウンとうなづく。そう、写真よりも調査が優先だ。
「イカを供えて、祈願しないと」
うなづいていた区長たちの動きが止まった。真軽仁の優先事項は、写真や調査ではなく「イカ祈願」らしい。
真軽仁は、緩慢に動いているペンギンモアイのすぐ足元にイカを供えて、両フリッパーを胸で合わせた。
「書道の腕が上がりますように。書道店が繁盛しますように。美味しいイカが毎日獲れますように。イケペンの彼氏ができますように。老後まで2000万ペン貯まりますように……ナムナム」
真軽仁の欲望だらけの念仏に合わせ、ペンギンモアイは、ぬるぬるのイカの上に乗り上げた。すると、イカに乗ったペンギンモアイは滑りが良くなり、動きが速くなった。しかし、向かう方向が土産店とは逆だ。土産店からどんどん遠のいてしまっている。
「あわわわわ、ペンギンモアイが離れていくっス!」
「あらあら」
一同はイカに乗って進み続けるペンギンモアイを追いかけていたが、しばらくして、ペンギンモアイは元の緩慢な動きに戻った。どうやら滑る原因のイカがモアイの下からなくなったらしい。
「土産店から遠のいてしまったでス」
遥か向こうの土産店を見つめ、呆然とクチバシを開いたままの区長とス太郎たちの様子を見て、慈円津はやっと調査のことを思い出した。
「では、私の出番ね」
そう、慈円津に何も策がなかったわけではない。例の方法があるのだ。ペンギンが手っ取り早くアイディアを得る方法、それは、もちろん「腹撫で」である。慈円津は、ペンギンモアイの前に座ると目をつむり丸い腹を撫でだした。隣で真軽仁も真似をして腹撫でをする。
「そうでスた!腹撫でという手があったのでス!」
「慈円津さんの腹撫でが見られるなんて最高っス!」
区長やス太郎たちが見守る中、慈円津は腹撫でを続けた。太陽の下、慈円津に強い日差しが降り注ぐ。時間が経つにつれ慈円津の全身から吹き出す汗の量が増し、眉間のシワが深くなっていく。そして、とうとう腹を撫でるフリッパーが止まってしまった。
「うーん、さっぱりペンペンよ。何も浮かばないわ……」
この暑さの中では、腹撫でに集中できるわけはない。横では、とっくに腹撫でに飽きた真軽仁がイカを美味しそうに舐めている。そのイカの匂いが慈円津の鼻孔を刺激した。
「そうだ!」
慈円津は、土産店で置くため、サンプルで持ってきた魚醤があることを思い出したのだ。これは元々は魚醤として作ったのではなく、本来は香水なのである。気分転換に最適なグッズなのだ。慈円津は、魚醤を腹に塗ってみた。思った通り、とても良い香りだ。さらに、アロマ効果で、塗った腹から涼しさが全身に染み渡っていく。
「うん、いい感じ」
すっかり汗が引いた慈円津は、魚醤を塗った腹を改めて撫で始めた。区長とス太郎たちも黙りこみ、息をこらしその様子を見守っている。慈円津の意識が集中し始めて10分ほど経った頃だろうか、慈円津は閉じていた目をぱちりと開けた。その瞳がペンペンと輝いている。
「私って天才!」
良いアイディアが浮かんだのだ。
「さすがの慈円津でス!」
「さすがっス」
「がっス!」
「ス!」
喜びの声をあげる区長とス太郎たちに、慈円津は、またもや目を細めミステリアスな顔つきになり微笑んだ。それを見ていた真軽仁も、イカを舐めつつ、目を細めてニヤリと笑う。
「任せておいて。とにかく善は急げね。土産店に戻りましょう」
一同は、土産店へと急いで戻ることに。そして、
「電話借りるわね」
と、慈円津は電話をかけてこそこそと話している。
「……でね、羽白(はねじろ)さん……が……で、古潟(こがた)さん……なの……」
どうやら電話の相手は羽白らしく、何かを相談をしているようだ。しばらくして、慈円津は受話器を置くと、区長やス太郎たちの方を向き、フリッパーの親指あたりを立ててグッと前に突き出した。
「万事OK!ばっちりぐーよ!」
そして、ペンと丸くふくよかな美しい腹を叩き、目を細めた。もちろん、その横で真軽仁も目を細めている。
区長とス太郎たちは、「ばっちぐー」といえる解決策がよく分からないが、慈円津の溢れ出る自信に圧倒され、
「やったでス!」
「やったっス!」
「たっス!」
「ス!」
と陽気に喜んだのであった。
(つづく)

浅羽容子作「白黒スイマーズ」第10章 アッツイ区のペンギンモアイ(3)、いかがでしたでしょうか?
うっかりクイーン真軽仁サラ世が「書道家」だったとは。うーん作品を見てみたい。それより、思わぬワトスン役を得て張り切る慈円津・ホームズの名推理とは何なのでしょう。不穏な予感がするような、しないような……いえ、おさかな香水のアロマで瞑想腹撫でしたのだからきっとばっちぐーな解決策っス!楽しみっス!!
ご感想・作者への激励のメッセージをこちらからお待ちしております。次回もどうぞお楽しみに。
※ホテル暴風雨にはたくさんの連載があります。小説・エッセイ・詩・映画評など。ぜひ一度ご覧ください。<連載のご案内>

