【 わるものが危機の打開に頭をしぼるとき…… 】
この第11章タイトルを見て、まずあれこれと考えたこと。
絵本や児童文学の文章を編み出す際に「どの程度までむずかしい漢字を使うか」「どの程度までむずかしい表現を使うか」という点。これは絵本や児童文学の作家が等しく悩む課題だ。
大抵の本にはターゲットがある。どのような年齢層に読んでもらいたいか。どのような性別、職業、趣味の人々に読んでもらいたいか。細かく設定してつくった本もあれば、あまりそういうことは考えずアバウトにつくった本もある。ターゲットをしっかりと設定するのは「ぬかりなく本を売る」という点では大事な留意点だが、あまりその点ばかりにこだわりすぎると、失敗した時に、つまりあまり売れなかった時に大いに失望することになる。本の内容よりも「この戦略のどこがいけなかったか」という分析ばかりに目が行くことになってしまう。やはりこの話も「過ぎたるはなお……」ということかもしれない。
章タイトルの話に戻ろう。
「わるもの」と「危機の打開」が章タイトルで同居している。「危機の打開」にはルビが振られている。これはたぶん翻訳者のこだわりだろう。ルビのことはともかく「危機の打開」というなかなかにむずかしい表現を漢字で使うぐらいなのだから「わるもの → 悪者」ではいけないのだろうか。
細かいことを言い出すようだが、「モモ」(岩波書店)は翻訳本であり、漢字とひらがなの扱いにはそうした「翻訳者のこだわり」と思われる表記が随所にあって面白い。その点も時々は取り上げていきたい。
✻ ✻ ✻
さて本題。この第11章は要するに「灰色の男たちの会議」である。会議のシーンしかない。巨大な会議室に幹部全員が召集されている。壁にはずらりとならんで帽子が引っかけられている。かれらはみな僧侶のように髪がないのだ。
はしが見とおせないほどの長い会議用テーブルに、びっしりとならんですわっています。
(原作)
議題はもちろんモモのことだ。
・多数を動員して追跡していながら、なぜ逃してしまったのか。
・モモはどこに逃げたのか。モモの逃亡を助けた何者かがいるのか。
・今後はモモに対してどう対処するべきか。
議長の説明の後、次々に立ち上がって意見を述べる幹部。その発言のたびに動揺したり、安堵したり、わめいたりする灰色の男たち。
エンデはこの章の冒頭でこんなふうに語っている。
彼らの気分はーーこの男たちにおよそ気分なんてものがあるとしたらの話ですがーーぜんたいにさえないようでした。(原作)
このあたり、これはエンデ一流のユーモアだろうか。
立場としては「わるもの」だが、この会議では前章のような追跡劇の「動」はないものの、灰色の男たちの内面の「動」がじつに巧みに描かれている。彼らもまた自分たちの生、自分たちの居場所を確保するために必死なのだ。そのためには手段を選ばないのだ。
一歩まちがえば「重罪裁判 → 死刑」という恐怖政治に支配された男たち。女の気配が全くない禁欲の男たち。彼らが活動している世界は、まるで途方もなく巨大な刑務所のようだ。
「わるもの」には「わるもの」が信じる道義があり、そのための行動に邁進せざるをえない理由がある。何十人(?)何百人(?)も集合した幹部たちがただ一人の少女をめぐって真剣に議論している。その光景は滑稽だが、同時に悲惨でもあり、どこか同情を誘うような一喜一憂を灰色の男たちは見せている。さすがはエンデ。
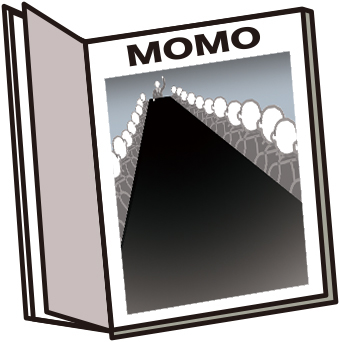
余談。
エンデは安野光雅との対談の中でこんなことを語っている。
「『モモ』の中で灰色の男たちが登場しますが、私は大真面目にあれを書いています。灰色の男という「力」は目に見えない世界に明らかに実在していますから。それが悪魔という存在の現代的な姿です」
【 つづく 】

