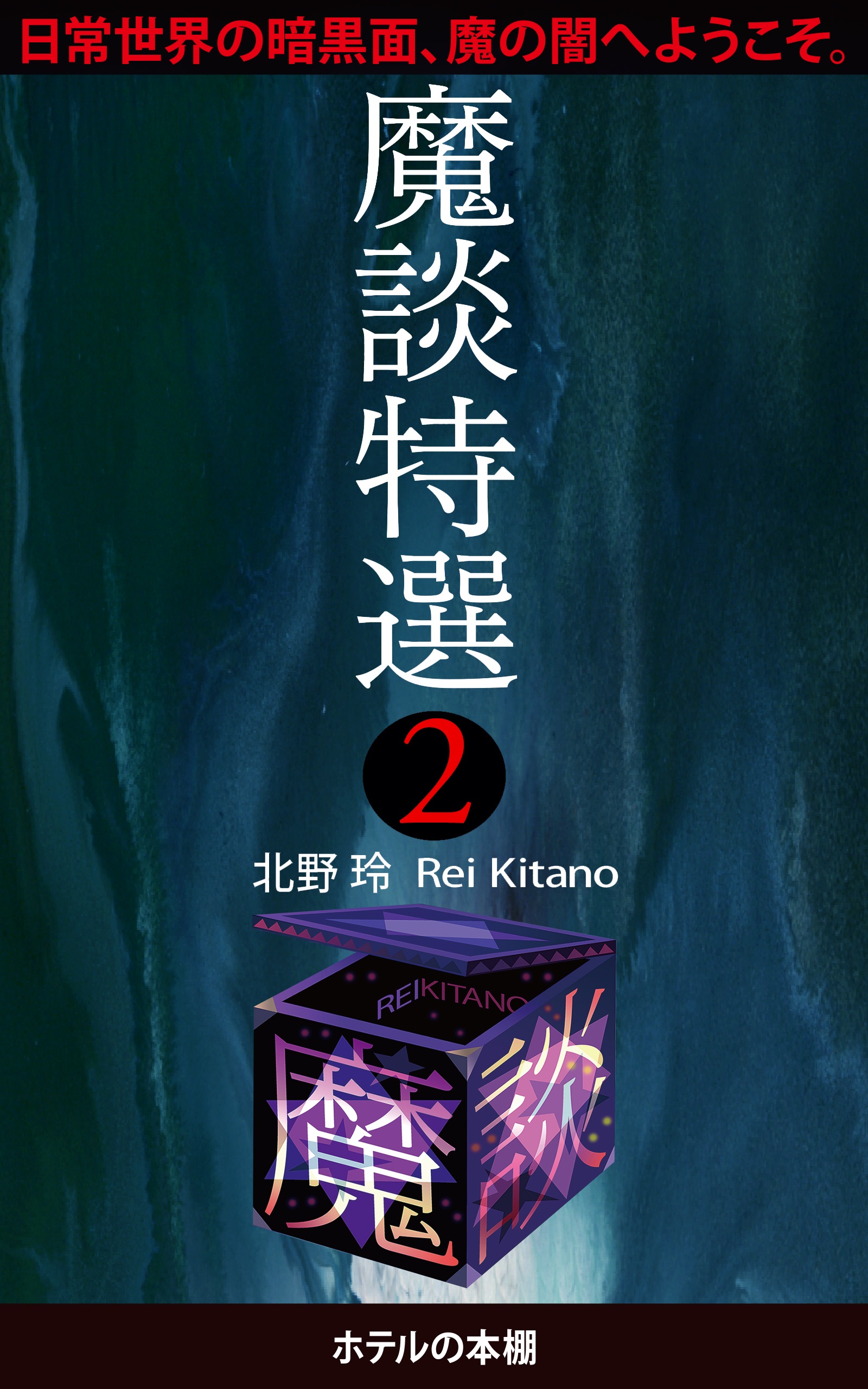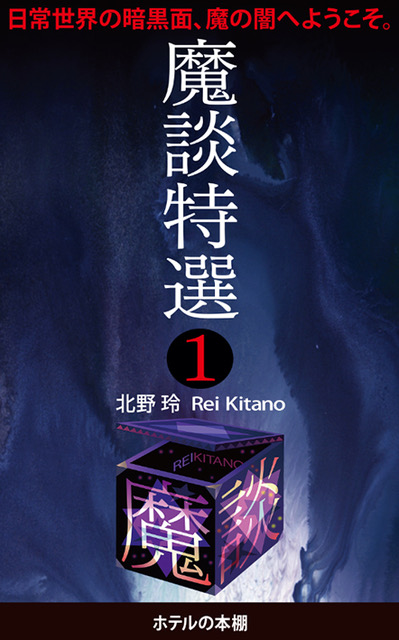【 忍者の追加 】
今回の魔談は映画「魔界転生」登場人物の、映画設定キャラと史実を語っている。
この物語は要するに天草四郎の復讐劇なのだが、映画の前半は「四郎の仲間集め」である。細川ガラシャ、宮本武蔵、宝蔵院インシュン。これで四郎を加えて合計4人となった。もうこのあたりでよかろうと思うのだが、四郎はいまひとりの若者を口説いて魔界転生に誘い、仲間に加えようとする。それが霧丸(きりまる)。実在の人物ではない。伊賀衆である。つまり忍者を加えようとしたのだ。
「あんた悪魔が味方についているんだろ? なんでわざわざ忍者まで追加するのさ?」と思ってしまうのだが、まあこの映画の前半は、このようにして「多士済々(たしせいせい)が集合していくワクワク感」みたいなものを狙っているのだろう。
さてその霧丸。今をときめく真田広之(1960 -)が演じている。この時、真田は21歳。彼は伊賀の隠れ里で平和に暮らしていたのだが、その村が甲賀衆の襲撃に会う。皆殺しと言っていい襲撃である。女子供まで容赦なく殺され、村は焼き尽くされてしまう。霧丸もこの戦いで命を落とすことになってしまうのだが……絶妙のタイミングで現れた天草四郎に口説かれてしまうというわけだ。確かに「ここで、こんな死に方で、人生を終わりにしたくはない」という気持ちはよくわかる。
それにしても、なぜ甲賀衆はここまで伊賀衆を憎んでいるのか。この映画ではその理由はわからない。同じ忍者どおしの反発感か。女王陛下の諜報員が某国の諜報員組織を襲って壊滅させるようなものなのか。
この「伊賀 vs 甲賀」に興味を持ったので、今回は(映画の設定はさておき)この2大忍者勢力を調べたい。
【 伊賀 vs 甲賀 】
我々日本人が想像している以上に、「忍者」は海外に人気が高いようである。特に欧米で人気が高いと聞いたことがある。「忍者ツアー」なんてのもあるらしい。私は3ヶ月ほどかけてフランスを縦断旅行したことがあるのだが、パリでも田舎でも私が日本人と知ると「知り合いに忍者はいるか?」と聞かれて笑ったことが何回かあった。
どこにそれほどの魅力を感じるのだろう。ひとつには彼らにとって東洋は全く文化圏が違うので、(欧米の武芸者にはない)ミステリアスなイメージが強いのだろう。黒装束に身を固め、目だけを出し、刀は背中に差し、手裏剣を懐に忍ばせ、夜に屋根瓦の上を音もなく走る。目くらましなどのマジックを駆使して相手を倒す(あるいは逃げる)黒装束の戦闘マジシャン。そんなイメージなのだろう。
さてその忍者に伊賀と甲賀という2大勢力があることは、大抵の日本人なら知っている。映画「魔界転生」に登場の霧丸は伊賀衆の「かくれ里」に住んでいたのだが、甲賀衆の襲来を受けて村ごと破壊され焼かれてしまう。このような襲撃は史実だろうか。伊賀と甲賀は(東本願寺と西本願寺のように)近親憎悪的に憎み合っていたのだろうか。
どうもこれは史実とは異なるようである。
奈良の伊賀と滋賀の甲賀。京都を挟んだこのふたつの山間の地は、独特の共通地形をしている。上空から眺めると、まるで毛細血管のように丘陵が張り出し、じつに複雑に絡み合った丘と谷の地形を形成しているのだ。地学的な説明としては「300万年前の古琵琶湖層という粘土層が侵食されて、このような地形となった」ということらしい。
300万年前と言われても全然ピンと来ないが、「古琵琶湖層」という名称は初めて聞いた。大いなるロマンを感じる名称ではないか。簡単に言えば、
(1)大昔の琵琶湖は、現在の琵琶湖よりはるかに広大な面積を占めていた。
(2)その湖底で形成された粘土層が、長い長い歳月の間に地表に出てきた。
(3)風雨により粘土層は侵食され、現在の伊賀・甲賀の複雑な地形を生み出した。
……ということらしい。(下の写真)

ともあれ、このような地形が理由で、古来からこの山岳地帯には、強大な力を持った勢力が生まれなかった。戦国時代においても大名の支配から無視されていた。「あんなどうしようもないところ、支配するほどの価値もない」といったイメージだったのかもしれない。
しかしもちろん人は住んでいた。丘陵地帯にへばりつくようにして暮らしていた地侍たちがいた。それが伊賀衆、甲賀衆と呼ばれていた集団だった。
この地侍たちはどのような生活をしていたのか。小さな集団どおしがお互いに連携し、一種の「自治組織どおしの同盟」を形成していた。何事もみんなで集まり、話し合いで決め、時には多数決で物事を決めていた。じつに理想的な、山間の生活ではないか。伊賀と甲賀も連携していた。互いに襲撃することなどなかったのだ。
しかし京都周辺における強大な権力の出現により、彼らの平安は次第に脅かされることになる。ここでもまた登場してくる「魔の男」が信長である。そんなわけで、次回は「信長 vs 伊賀甲賀」を調べていきたい。
【 つづく 】