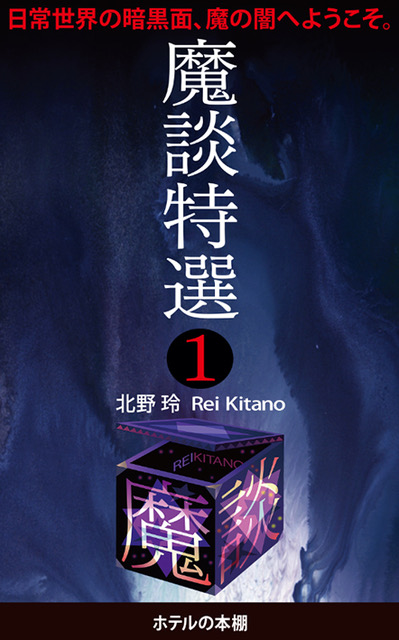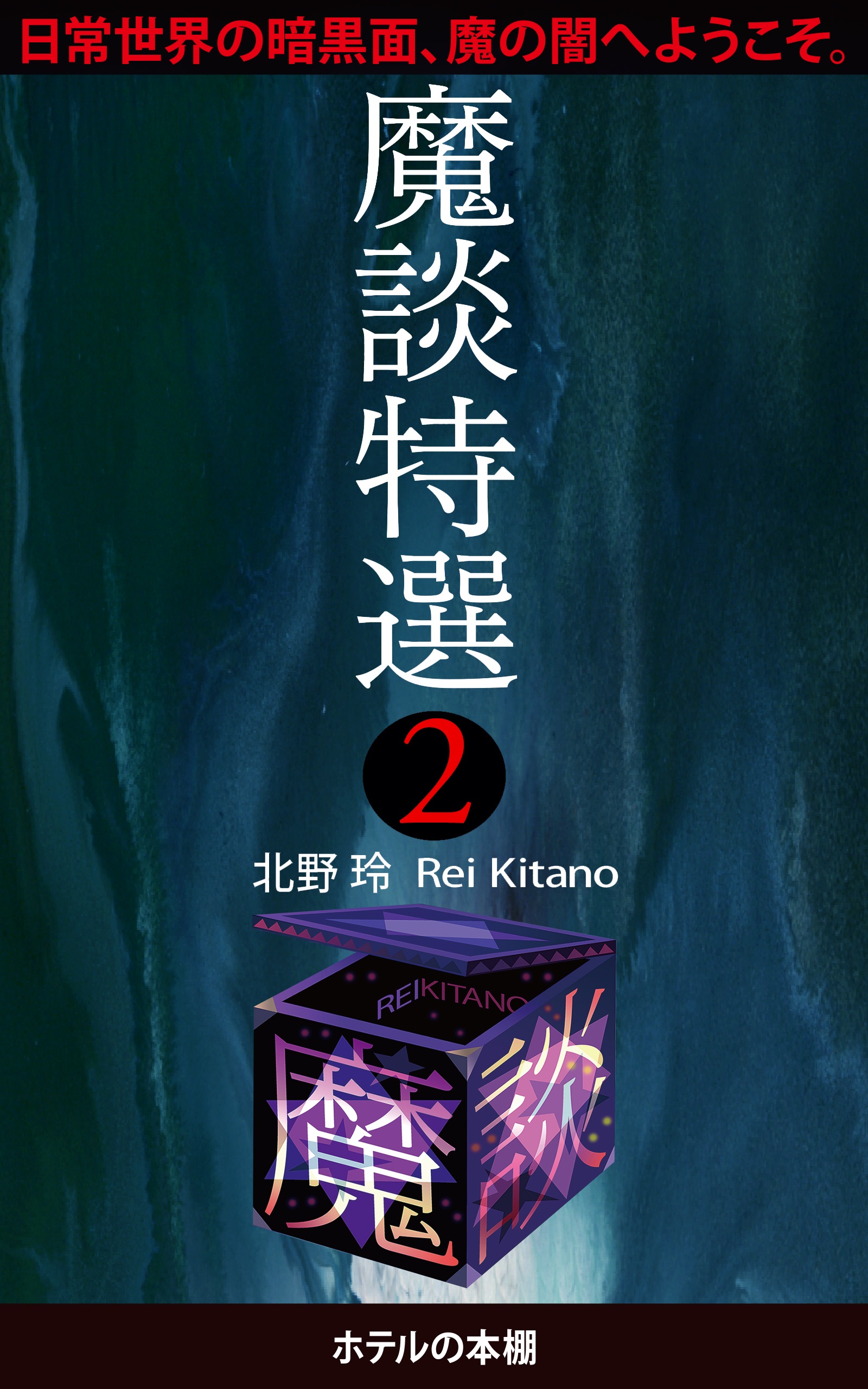【 マイルール 】
私の今回の人生で最初に「日本人以外の人」と直に接したのは、おそらくこの時であろう。朝鮮人と聞いたところで8歳の世界観では朝鮮がどこにあるのかも知らず、なぜ日本で暮らしているのかもわからなかった。もちろん今ではこの集落の人々がどのような経緯でここに住むようになったのか、大体の見当はついている。しかし「大体の見当」で話していいことではないので、ここではあくまでも当時の8歳目線で話を進めていきたい。
少年時代、捕虫網を振り回して虫を捕まえることに夢中になった人は多いと思う。私の周囲では、それらの少年はほぼ3種類に分類できた。
(1)虫ならなんでもかでも捕まえる派
(2)蝶・トンボだけを追いかける派
(3)蝶のみを追いかけ、しかも「手に入れたい種類」以外は目もくれない派
……というわけで、(3)に近づくほどマニアックなコレクターということになる。また年齢的にも(3)に近づくほど「小学校低学年 → 高学年」といったイメージがある。

私はどうだったか。(2)に近かったが、バッタやイナゴも捕まえていた。しかし(1)ではなかった。理由はなんとなく覚えている。蝶やトンボは捕まえて点検した時に羽の一部が破損していた、あるいは私のせいで破損してしまった、そういうケースが多かった。
「そんなこと気にしない」といった子どもたちもいた。しかし私は気にした。虫かごの中に4匹も5匹も入れてしまったら繊細華麗な羽が傷ついてしまうことは経験上わかっていた。そこで蝶を捕まえた時は、まず羽の具合を点検し、破損がない場合は(空っぽの)虫かごに入れた。少しでも傷ついていた場合は、すぐに逃した。
その次に蝶やトンボを捕まえた時はやはり羽の具合を点検し、破損がない場合は「すでに虫かごに入っている蝶やトンボ」と比較してどちらかを選び、どちらかを逃した。このような習慣というかルールを自分で決めていたので、私の虫かごには、常に1匹の蝶やトンボしか入っていなかった。私はそれで満足していた。「大量に捕まえる」ことにはなんの興味もなかった。
【 依頼捕虫 】
さて本題。
蝶やトンボに比べてイナゴというのは、さほど「捕まえるのがむずかしい虫」ではなかった。野原の草むらを歩いていると、イナゴは私の足元からパッと飛び立って2mほど先に着地する。じつに見事な保護色なので、着地したあたりをよく見ても大抵は発見できない。そこで「このあたり」と見当をつけて捕虫網をバサっとかぶせる。うまくいくと、あわてたイナゴは網の中で再び飛ぼうとするので、網にぶつかって簡単に発見&確保できる。
乾パンをいただいた翌日。私は10匹ほどのイナゴを捕まえた。イナゴの羽は蝶やトンボと違ってじつに強靭だ。なにしろ羽を機能的に折り畳むことができる。破損したり傷ついたりしたイナゴを見たことは一度もなかった。
「バッタはダメ」と聞いていた。私の足元からパッと飛び立った虫がバッタだった時はちょっとがっかりしたが、虫かごの中に入れたイナゴがどんどん増えていくという捕獲は、私にとって(それまでに経験したことがない)一種の快感となった。「あの人たちはこれを食べるんだ」という興味が私の「イナゴ狩り」を夢中にさせた。
いま思えば、私はこの時初めて「依頼された行為」を意識したのではないかと思う。もちろん当時はそんな分析的な考えをするはずはない。しかしただ自分の趣味だけで虫を捕らえていた時期とは全く違う意識で、イナゴを追いかけていたことはまちがいない。
私が10匹ほどのイナゴを虫かごに入れて(意気揚々と)ヤギジイの家に行った時、ソアが必ずどこからともなく現れて私を出迎えた。彼女はどこにいたのか、なぜ私がヤギジイの家に来たことをいち早く発見し、私の前に走ってきたのか、今となってはもう、それは謎でしかない。私はソアを見るとドキドキした。彼女が私を見る目に「特別なもの」が宿っていることを感じていた。
ヤギジイは私を見るとブリキのバケツを机上にドンと置いた。虫かごを開けて、そのバケツの中にイナゴをバラバラと落し、すぐに水を張った。イナゴは水の中でアップアップしていたが、しばらくして全部水死し、水面に浮いた。ヤギジイはその中の1匹を指でつまみ、鼻の前に持ってきてクンクンと匂いを嗅いだ。それをソアに回し、彼女も同じように匂いを嗅いだ。次に私に回した。匂いを嗅いでみるとバターのような独特の匂いがした。
【 つづく 】