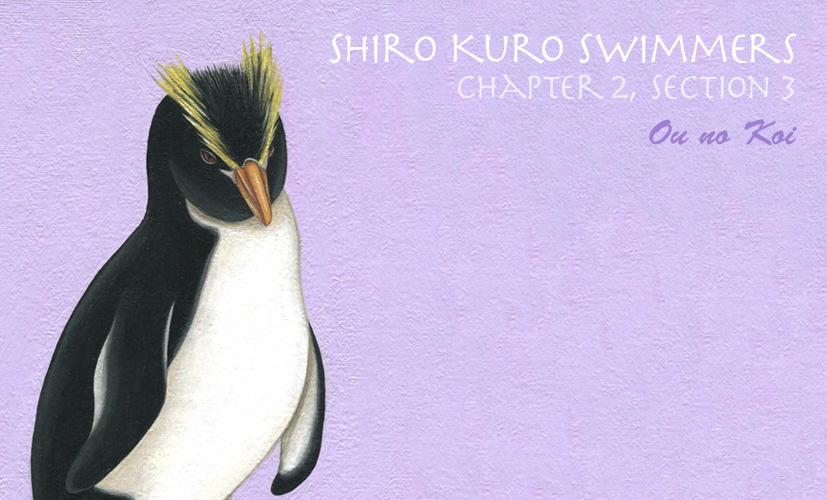
今日も慈円津はシュレーターズのプロマイドを見つめている。
「やっぱりシュレーターズのリーダー、主麗田キョン介(しゅれた・きょんすけ)がかっこいいわ。髪型がすごくキマってる……」
慈円津の視線は、頭髪の稲妻形が一番美しい主麗田に注がれている。慈円津は、プロマイドを見ながら何やら工作中のようだ。たまに作業を中断し、プロマイドに熱い視線を送っている。
「出来た!」
慈円津の工作がやっと出来上がった。ちょうど同時に、店の方から声が聞こえてきた。
「サエリー、ソフトカチューシャの在庫がもうないわー」
その声の主は、王と入れ違いに慈円津の店を手伝っているペンギンである。そのペンギンが慈円津のいる店の控え室に姿を現した。
「あら、ソフトカチューシャじゃなくて、ねじりハチマキよ。発注しておくわね。そうそう、順子、これ、今やっと出来上がったの。ちょっと着けてみて」
順子と呼ばれたそのペンギンは、地味な顔立ちのジェンツーペンギンだ。どれくらい地味かというと、湯飲み一杯の玄米茶を2リットルのぬるま湯で薄めたくらいの薄さである。だが、感じは悪くない。いかにも人(ペンギン)の良さそうな雰囲気である。慈円津よりも少し小ぶりであるが、てっぷりとした丸いお腹からはペンギン的品の良さも感じられる。慈円津とは仲が良さそうなのは分かるが、姉妹にしてはあまりにも似ていない。
慈円津は、そんな順子の頭に、出来上がったばかりの物を被せた。
「あら似合う」
「そうかしら」
順子は少し照れたように、頰にフリッパーを当てうつむいた。
「似合う、すっごくかわいい!」
慈円津は、そういうと満足げに順子のクチバシをチョイと触った。
そして、日曜となった。シュレーターズのライブの日だ。
ライブハウス「フィッシュ・ぼーん」は、興奮したペンギン達ですでに満員だ。
「まずい、もう時間だ……」
酒の配達で遅れた王が来たのは、開演間近。サマ春とサマ雪は、先に入場している。
穴蔵のような店に入ると、魚煙草で煙たい上に、ペンギン達の湿った熱気でアッツイ区のような暑さである。スズシ区に住む王にとって馴染みのない感覚だ。
「王ちゃん、来た来た!」
ドリンクカウンターで接客していた岩飛が、王を見つけ声をかけてくれた。
「遅くなっちゃって……」
王は幾分場違いな気分になりながら、サマ春達を探して会場を見渡した。
「サマ春さん達ならあっちだよ」
岩飛が指し示す先にサマ春達はいた。二人は、客が密集しているフロアの中央辺りにいて、王を見つけフリッパーを振っている。
「こんなに混んでいたら、あそこまでいけないな……」
王はそう思いながら、また視線を周囲に動かした。そう、この会場には慈円津がいるはずなのだ……。すると、後方から聞き慣れた声がする。
「いらっしゃーい!ツアーグッズはこちらでーす!シュレーターズ特製カチューシャ販売中~!魚醤とねじりハチマキも売ってまーす!」
振り向くと、ツアーグッズを売っている販売ブースがあり、人だかりができている。皆、争うように買った物をその場で頭に着けている。
そして、その販売ブースの売り子の中心になっているのが慈円津だった。慈円津は、シュレーターズの稲妻のような髪型を模したカチューシャを着けている。そう、客達がこぞって買って着けていた物と同じ物である。
「慈円津さん……」
「あら、王さん!」
ちょうどその時、「ギュイ~ン」と開演の合図であるギターの音が鳴り響いた。シュレーターズ特製カチューシャをつけたペンギン達が皆、我先へとなだれ込むようにステージへと向かい駆けてゆく。
あっという間に販売ブースから客がいなくなった。フィッシュぼ~んにロックなリズムが大音量で響き出す。
王は慈円津に話しかけるが、少し離れているので何も聞こえないようだ。会話が出来るように慈円津のすぐ隣に王は移動した。慈円津からはおさかな香水の良い香りが漂う。思わず瞳を閉じ、その美味しい香りについ恍惚となりそうになるが、すぐに目を開き横を向いた。至近距離に慈円津がいる。
「それ……?」
王は、自分の頭をちょいと指した。慈円津は自分の頭に着けているカチューシャをペンペンと叩き、笑った。
「いいでしょう!?新商品よ!シュレーターズ特製カチューシャを作ったの。ツアーグッズよ。毎日、資料のプロマイドを見て研究したわ……。おかげで大繁盛よ!見て、王さん!シュレーターズファンでトサカがない種族のペンギン達が、こぞって私のカチューシャを着けているわ!」
慈円津は、生き生きペンペンとしている。
「……え?慈円津さんって、シュレーターズのファンじゃないの……?」
「違うわよ。シュレーターズは嫌いじゃないけど、特別好きって訳じゃないなぁ~。大きな声で言えないけど、私、演歌の方が好きだし」
慈円津は続けて、
「あ!王さん、私が演歌好きっていうのは内緒ね」
と言うと、可愛らしく首を傾けフリッパーを口に持ってきて「シー」の素振りをした。
「……うん!慈円津さん、もちろんだよ!」
王の顔が赤くなっていく。見た目は黒なので、慈円津はその赤さには気がつかない。その時、ステージの爆音が止み、リーダーの主麗田が興奮する観客に向かいムードを変えて言った。
「次は、全世界の恋するペンギン達に贈る曲です。『おさかなに捧げるバラード』、聞いてくれ……」
静かなバラードの演奏が始まった。店の照明も暗くなっている。目の前のカチューシャをつけたペンギン達の後ろ姿が左右にゆっくりとキャンドルの光のように揺れ動いている。
王は、隣りを見た。慈円津がいる。シュレーターズの奏でる愛の歌が王と慈円津を包んでいる。王の鼓動が高まった。
「こ、こ、こりは、今しかないのでは……!」
王は、今が告白する絶好のチャンスであると悟った。今後こんなことはないかもしれない。そう、今しかない……。クチバシから胃の魚がポロっと飛び出しそうなほど緊張している。フリッパーで前掛けを固く握りしめ、王はついに覚悟を決めた。
「じ、じ、じぇんつさん!わ、わ、わたし……ん?……えっ!?」
その時、慈円津の後ろから、慈円津にかじりつくようにして顔を覗かせて王を見つめる子供のジェンツーペンギンが王の目に入った。そして、その子供の顔がやけに慈円津に似ていて、王はクチバシに出掛かっていた言葉をとっさに飲み込んでしまった。
(つづく)

浅羽容子作「白黒スイマーズ」第2章 王の恋(3)、いかがでしたでしょうか?
ついに神秘のヴェールを脱いだロックバンドシュレーターズとそのリーダー・主麗田キョン介。シュレーターペンギンは、ロック岩飛さんたちイワトビペンギンと同じマカロニペンギン属。地球では、ニュージーランド南部の島に住んでいます。見事に逆立った冠羽が特徴。
なんてことはさておき、今日もマイペースにしなやかに生き生きペンペンな慈円津さん、そ、その子は誰?そして超絶地味顔ながらミステリアスな魅力を振りまく順子とは?王さんの恋の行方はいかに!
ご感想・作者への激励のメッセージをこちらからお待ちしております。次回もどうぞお楽しみに。
※ホテル暴風雨にはたくさんの連載があります。小説・エッセイ・詩・映画評など。ぜひ一度ご覧ください。<連載のご案内>

