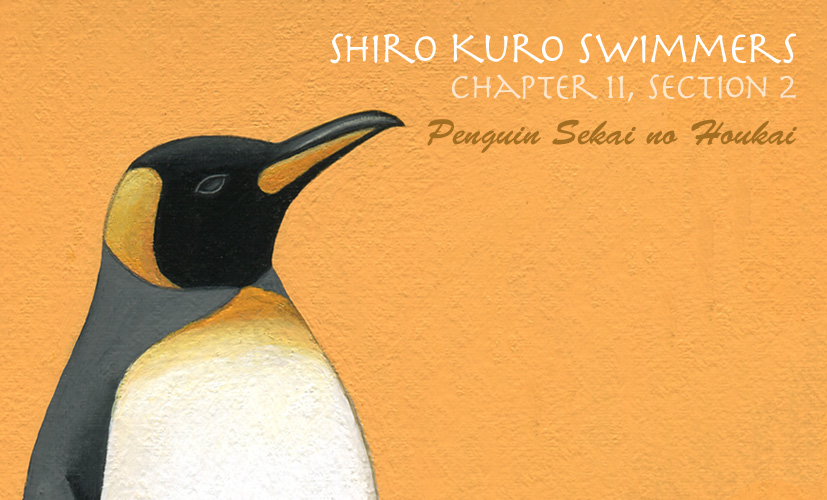
「皇帝さま!」
海から飛び出し、本気を出した貴族の走りは、まるでペンギンとは思えない俊足だ。貴族は大穴に落ちていく皇帝に素早くフリッパーを差し伸べた。寸前のところで、皇帝のフリッパーが貴族のフリッパーを掴む。皇帝の重みが貴族にズシンと伝わった。必死に堪える貴族。痩せているとはいえ皇帝の体重は、貴族の4倍以上はある。
「……くっ」
ついに、その重みに耐えられなくなった貴族は、徐々に大穴へと引きづられていく。そして、とうとう二人は大穴の中へと落ちていってしまった。
「うぁぁぁぁぁ!」
しかし、その瞬間、大穴から吹き出す風が起こった。今までなら、昼間には起こらないはずの吹き出す風だ。皇帝と貴族の体は持ち上げられ、大穴から大きく空に吐き出された。
「皇帝さま!」
「貴族さん!」
風に乗った二人は、自然とフリッパーを広げ、そのまま大穴の周りを大きく旋回した。風が弱まると同時に、皇帝と貴族はふんわりと浜辺に着地する。
「皇帝さま、大丈夫ですか!?」
「ありがとう、大丈夫だよ。貴族さんは!?」
「えぇ、大丈夫ですわ。でも……」
「うん、今のは……」
大穴からの風に乗った時、皇帝も貴族も妙な感覚を感じていたのだ。まるで、空を泳いでいるようなペンペンとした感覚である。しばし呆然としていた二人だが、皇帝のクチバシの端からダラリと飛び出した魚を貴族が見つけると、急に激しい剣幕でまくしたて始めた。
「皇帝さま! 歩きおさかなをするなんてマナー違反ですわ! スパルタコースで特訓して差し上げます! 本当にもうっ!」
この貴族の叱責には、おおらかな皇帝も大きな体を縮こまらせながら反省するしかすべがなかった。
* * *
「黄頭(きがしら)さん、サインくださいっス!」
「マリンさん、サインくださいっス!」
「クラゲさん、サインくださいっス!」
黄頭ナンデモ研究所の三人、黄頭とマリンとクラゲは、電話を受けた翌日からアッツイ区の調査を開始していた。柄箱(がらぱこ)・柄箱川(がらぱごがわ)・柄箱山(がらぱごやま)の学生アルバイト三人組のス太郎たちの陽気な歓待を受けた後、動くモアイの調査を進めていたのだ。
「で、こうやってモアイの好物のイカで釣って、モアイを方向転換させるっス」
ス太郎たちは、動くモアイの方向転換を誇らしげに実演してみせた。クラゲは、「スたろうさんたち、すごいね」と嬉しそうにス太郎たちとじゃれあっていたが、マリンは冷静だ。
「ス太郎くんたち、モアイはイカが好物な訳じゃなくて、イカのヌルヌル成分で滑るだけよ」
マリンの指摘にス太郎たちは驚いた様子である。
「どえっ、イカが好物じゃないんスか!?」
「さすがのマリンさんっス!」
「マリンさん、天才っス!」
感心しきりのス太郎たちは、次に穴が空いている箇所へと案内してくれた。アッツイ区長の言う通り大小の穴があちこちに空いている。好奇心旺盛なス太郎たちに囲まれながら、黄頭たちは採集マシーンで穴の中の成分を採取したり、様々な調査を行なった。一通り調査が終了し、ス太郎たちの屋台土産店に戻ることにした。
「マリン、クラゲくん、どう思う」
黄頭の問いに、マリンとクラゲは成分表を見ながら答えた。
「ボブ尾、多分、原因は昨夜話したアレだと思うわ」
「きかしらさん、僕もそう思うよ。ぶんせきしたサンプルの成分からするとマリンさんいうとおりだと思うな」
「私もだ……」
黄頭たちの神妙な顔つきにス太郎たちが心配そうに寄り集まってきた。
「大変なんスか?」
「だったら、皆さん、ちょっと休んだ方がいいっス」
「とりあえず、この新商品をお試しくださいっス」
ス太郎たちは、すかさず黄頭たちにコップを手渡した。中には、魚醤を冷たい炭酸水で割った魚醤ジュースが入っている。慈円津(じぇんつ)がアッツイ区用にブレンドした魚醤の試飲である。
「おいしいな、ぎょしょうジュース」
クラゲが破けた口から魚醤ジュースを飲むと、触手の間からこぼれていく。ス太郎たちは、触手の下で交互にそのジュースを飲みながら、「クラゲさんって、個性的っス」とはしゃいだ。
黄頭たちの目の前のス太郎たちの屋台には、みごとな筆使いで「藻亜胃(もあい)」や「毛愛(もあい)」や「裳阿医(もあい)」などのペンギン語が書かれたイカスミ書道の色紙が、「売れ筋No.1」というポップとともに貼り出されていた。
「ボブ尾、あの書、なかなかいいわね」
「1枚買っていこうか」
黄頭とマリンの会話にすぐさまス太郎たちは反応した。
「はい、毎度ありっス!」
「こちら、2枚買うと1枚おまけでつけるっス」
「さらに、5枚買うと2枚おまけをつけるっス!さらにお得っス!」
その会話を聞いたクラゲは、「スたろうさんたち、お得じゃないよ。ウフフ」と楽しそうに一回転した。
アッツイ区の調査の後も、黄頭たちの調査はペンペンと続いた。ヌルイ区やスズシ区、ゴッカン区にも赴き、様々な異変を調べたのである。そして、残す最後の区、ホドヨイ区の調査となった。
おさかな商店街会長の王とともに、ホドヨイ区の状況を確認してまわっていた黄頭たちは、岩飛(いわとび)のライブハウスの前に来ている。
「黄頭ちゃん、昨夜、突然ここに穴が空いたんだぜ」
岩飛は、魚煙草をくゆらせながら、沈痛な面持ちでライブハウスのすぐ前の道のイワシ1匹分くらいの小さな穴をフリッパーで指した。
「こんなところにも穴が……」
王は、増え続ける穴の出没に焦りを隠せない。頭につけたシュレターズカチューシャが揺れる。
「放っておくと、明日にはもっと大きな穴になってしまう」
黄頭は、そう言うと、
「応急処置なのだが……」
と前置きし、大きな注射器のような形の応急処置用凝固マシーンを取り出した。そして、穴の中に凝固成分を注入していく。
「これで、ひとまず穴の拡大は遅くなるはずだ。でも万全ではない」
「黄頭ちゃん、サンキュー。とりあえず、明日のスネアーズの単独ライブは開催できそうだな。でも、この調子だと、いつまでこのライブハウスもやっていけるかも分からないぜ……」
心なしか、岩飛のロックな飾り羽が弱々しく見える。みんな、いかにも鬱々ペンペンとした様子だ。そんな中、黄頭は王に向かい言った。
「王さん、実は、もうペンギン世界の異変の理由は分かったんだ」
「え!? そうなのかい?」
「うちの研究員たちは優秀だからな」
その言葉に、マリンは微かに微笑み、クラゲは嬉しそうに一回転している。黄頭は続けた。
「各所で穴が空く現象は、このペンギン世界の下層にある人間世界の大気汚染や有害物質などによりペンギン世界の地面が軟弱化したために思われる」
マリンが付け加えた。
「モアイ動くのは、それに関連して磁場が狂ったことに起因するわ」
「そうなのか……」
王はうなった。岩飛も苦い顔をしている。黄頭はレモン色の瞳で足元の穴を見つめた。
「残念なことに、私たちはまだ研究途中なのだ。この崩壊を食い止めるマシーンの完成には、ある物質が足りないのだ。それに、今回はホドヨイ区、いや、全区のみんなの手伝いが必要なんだよ」
「とにかく多くのペンギンたちの協力が必要なの」
マリンの瞳が力強く光った。クラゲさえも回転を止め、破けた星型の目で王を見つめている。王は、シュレーターズカチューシャをそっと外した。王が真剣な証拠である。
「分かったよ。確かに、このまま黄頭ナンデモ研究所頼みのままにしている状況ではないな。緊急にペンギン会議を開こう!」
王の一言で、全区合同ペンギン会議の開催が決まった。
(つづく)

浅羽容子作「白黒スイマーズ」第11章 ペンギン世界の崩壊(2)、いかがでしたでしょうか?
貴族貴子先生の機転と、「空を泳ぐようなペンペンとした感覚」(味わってみたい!)で皇帝さんが大穴に落ちずに済んだものの、ペンギン世界に大小さまざまの穴が空いて、しかも広がっている!? 今回は黄頭研究所のみんながいるから大丈夫……でありますように。次回はいよいよペンギン大集合、ペンギン会議開催です。
ご感想・作者への激励のメッセージをこちらからお待ちしております。次回もどうぞお楽しみに。
※ホテル暴風雨にはたくさんの連載があります。小説・エッセイ・詩・映画評など。ぜひ一度ご覧ください。<連載のご案内>

