【 推理小説愛読妻 】
推理小説を愛読する人は、そこに登場の名探偵に魅せられた人が多いに違いない。
「魅せられる」→「影響を受ける」ことになるだろうか。観察眼、想像力、推理力、そういうものが身につくものだろうか。
こんな話が思い出される。酒の席で友人デザイナー(T)から聞いた話だ。
Tは50歳を越えた時点で19歳年下の女性と結婚した。奥さんは「軽度の対人恐怖症」(友人の言)で、専業主婦を願った。友人は出版社勤めのデザイナーだったのでそこそこの給料をもらっていたし、ボーナスもあった。奥さんに対しても「外に出て働いてほしい」という希望は特になかったので、彼女の専業主婦希望をむしろ喜んだ。こうして新婚家庭がスタートした。
ほぼ1年が経過した頃、奥さんは「自分専用の本棚がほしい」と言い出した。Tにとってむろんそんなことに異論はなかったが、ちょっと不思議に思った彼は「そんなに本を持ってないのに?」と彼女に聞いた。すると奥さんは笑って、彼を自分のライティングデスクに招いた。
そのちょっと古風な、どっしりとした大きめのライティングデスクは彼女が自分の実家から運びこんだ家具だった。友人は「あれは彼女の大事なもの」といった扱いで手を触れることもなかった。扉を手前にパタンと倒すと、そこにはちょっと意外なほどの奥行きがあり、ずらりと本が並んでいた。また(彼はそれまで全然気がつかなかったのだが)デスクの下にある棚には観音開きの扉が付いており、それを開いてみると、そこにもぎっしりと本が並んでいた。感服した友人は即座に奥さん専用の本棚購入を許した。
「…‥でね、その時も彼女には特になにも言わなかったのだけど」
友人はちょっと声を落とした。同席して彼の話に聞き入っていた男たち3人は、ほとんど無意識に上体を少し傾けて彼の言葉の続きを聞き入る姿勢となった。そこにあった本は、そのほとんどがドイルのホームズシリーズと、アガサ・クリスティのポアロシリーズだったのだ。
「なんだ、そんなことか!」
聞き役の友人はもっと過激な本を期待していたらしい。怪奇小説とか、京極夏彦とか、その手の類だろう。しかし語り手のTにとって、それまで全く知らなかった彼女の趣味がじつは推理小説だったという事実は、少なからず衝撃だったようだ。
「たかが趣味だろ? なにを恐れる?」
聞き役の友人は笑ったが、Tは笑わなかった。
話は以上である。その後、この酒の席では別の話題に移ってしまった。しかしこの話にはなにか引っかかるものがあり、その後、長らく私の記憶にとどまった。
その瞬間、つまり奥さんが熱烈な推理小説愛好家だと知った瞬間のTの動揺……そこには一種の怯えに近いものも含まれていたのかもしれない。……その心境はなんとなくわかるような気がする。同席の友人は笑ったが、彼は笑い話としてそれを話したのではなかったのだ。
【 謎の調査行動 】
さて本題。モルグ街の殺人。
殺人現場の状況は新聞で克明に説明され、数々の証言もそろった。つまり「お膳立て」は出揃ったのだ。読者はここから「自分なりの推理」「自分なりの想像力」を働かせながらこの小説の進展を(まさに息を呑むように)見守ることになる。推理小説愛読者はまさにここにこそ、他の小説にはない一種のゲームを見出して存分に楽しむのだろう。
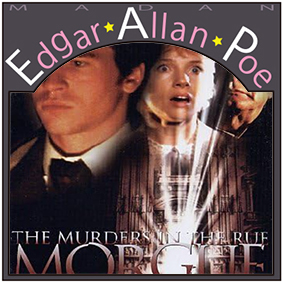
さてデュパン登場。この奇怪な事件を知ってどういう行動をとったか。
デュパンは特権的な行動をとっている。彼は警視総監とどの程度の知り合いだったのだろう。この小説でその説明はないのだが(やや御都合主義的な感じもするのだが)、ともかくデュパンは一般人でありながら、警視総監から現場調査の許可をもらうのだ。
彼は「僕は警視総監を知っている。必要な許可をとるのは簡単だろう」(原作)とサラリと言っている。時代も国も違うとはいえ、殺人事件なのだ。「必要な許可をとるのは簡単だろう」であるはずはない。これはもうデュパンが余程の「貸し」を警視総監との間で持っていたとしか思えない。
ともあれ、奇怪な事件を新聞で知って多いに興味を抱いたデュパン。
彼の行動を順に見ていこう。
(1)警視総監と面会。
(2)警視総監から許可証をもらう。
(3)事件現場に急行。
(4)室内および被害者女性の死体を調べる。
(5)新聞社に寄って帰宅。
こうしたデュパンの行動は、語り手である「私」から見た彼の行動だ。……なので、
・現場調査でなにがわかったか。
・被害者女性の死体を調べてなにがわかったか。
・帰りになぜ新聞社に寄ったのか。
これは「私」がその時点でわからなかった以上、読者もまたわからない。
ホームズにしてもポアロにしても、このようにして「事件の謎」に加えて「名探偵の行動の謎」が次々に追加される。しかし「事件の謎」は、ほっておくとそのまま謎が続くだけだが、「名探偵の行動の謎」はいずれ近いうちに名探偵が(ドヤ顔で)説明することが読者にはわかっている。こうしたお決まりの「推理小説の約束事」とでも言おうか、愛読者はそこに(期待は絶対に裏切られないと安心して)魅了されるのだろう。
さて次回からいよいよデュパンの「ドヤ顔」談に入りたい。
【 つづく 】

