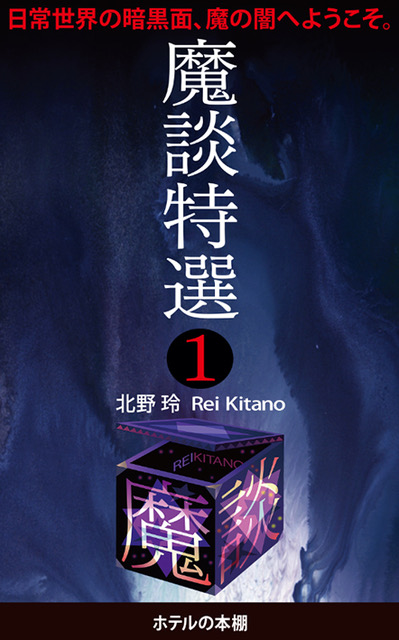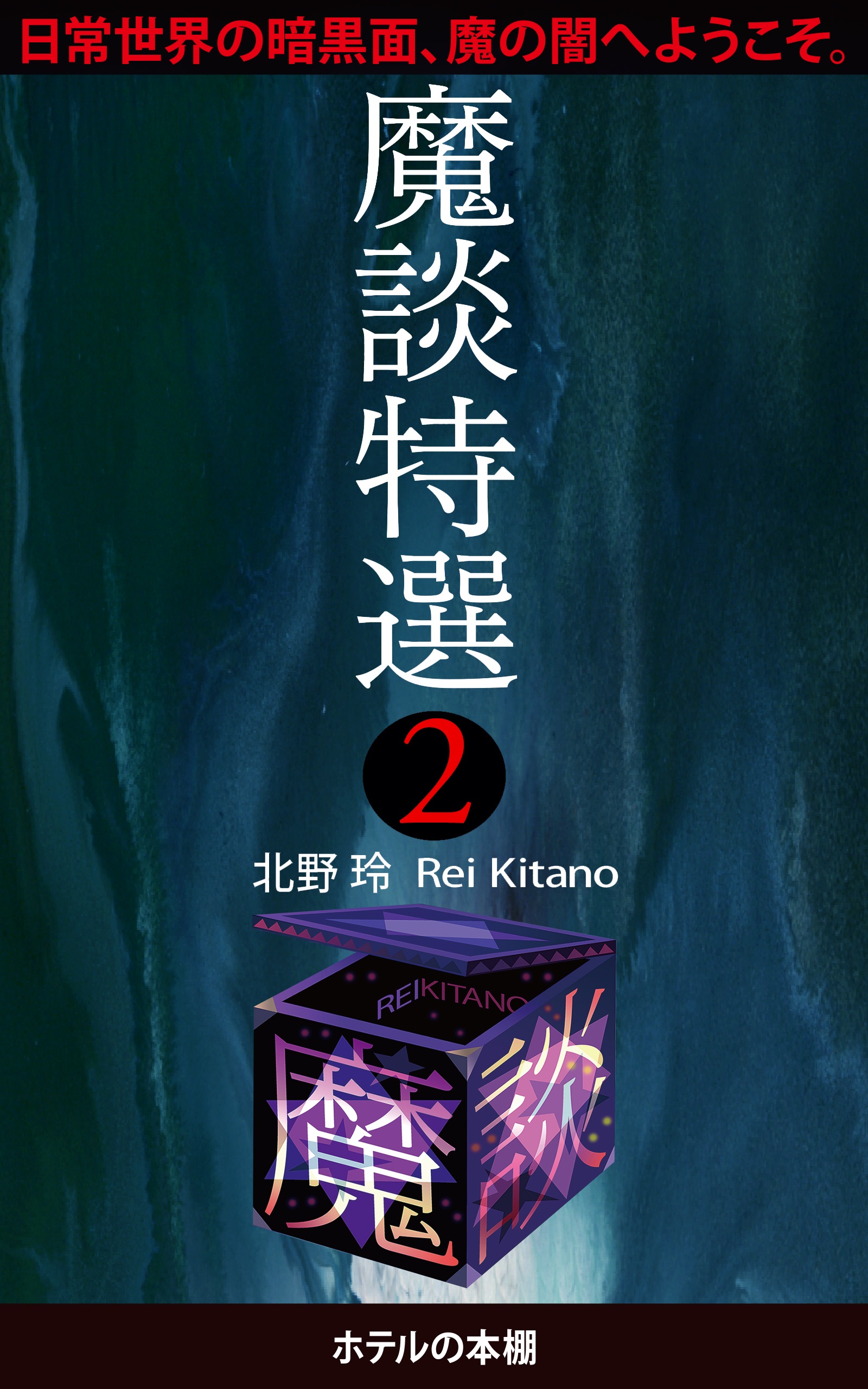【 呼吸を数える 】
「1……2……とな、自分の呼吸を数えるのや」
私は結跏趺坐(けっかふざ)、叉(しゃしゅ)、半眼、という定められた状態でかずくんの説明に耳を傾けた。
「呼吸を数える?……そんなことがなんの役に立つねん?」
そう思ったが、黙って従った。
彼の言ってることは、単なる思いつきとかその程度のことではない。延暦寺のお坊さんたちが、長年にわたり実践してきたことなのだ。
なんのためにこんなことをするのか。それは8歳の少年の理解をはるかに越えていたが、「大勢のお坊さんたちが、真剣にやってきた行為のおごそかさ」とでも言おうか、そのようなものは半ば直感で感じとっていた。彼のように100%心腹してそれに従うといった気持ちはなく、心の内では相変わらず不平不満が渦巻いていた。しかし圧倒的な宗教的空気が、私の前に仁王立ちになっていた。
ちょっと余談。
シュタイナー教育をある程度知っている人の間では有名な話だが、シュタイナー教育では、興味深いことに「7年に一度、人間の成長には節目がやってくる」という考えをしている。
・0歳〜7歳:身体をつくり、豊かな感情をつくる時期
・7歳〜14歳:芸術的な体験や刺激を多く与え、世界は美しいという思考を育てる時期
・14歳〜21歳:「私」という意識を持ち、多くの知識に興味を持たせる時期
これはもちろんルドルフ・シュタイナー(オーストリア人/1861-1925)の教育論であって、それがそのまま日本人の教育にも当てはまるのかどうかはわからない。しかし上記「7歳〜14歳」に最も重要とされる「芸術的な体験や刺激」を考えた時に「8歳の夏に延暦寺で10日間過ごした」という特異な体験は、学校の授業では到底得られなかったさまざまな影響を、その後の私に与え続けたことはまずまちがいないだろうと思う。

さて「呼吸を数える」話に戻ろう。
これは要するに意識をそのカウントに集中させることで、雑念をおいはらう目的というか方策というか、そういうことなのだろう。
しかし8歳の少年ではそんな簡単なことが、なかなかできない。
「途中で数を忘れた……どないするのん?」
彼は軽く笑った。
「気にせんでええ。また1から始めるのや。何回でもそうするのや」
私は「あほらし。やっとれん」と思いながら、また1から呼吸を数え始めた。
ところが(まさに修行が足らんということなのだろう)ついつい色んなことを考えている。その結果、「あれ?……いくつまで数えたっけ?」ということになる。毎回、30〜40あたりでそのカウントはあやしくなった。
もしよかったら、どうですか?
あなたもちょっと試してみてはいかがだろうか。
なにも「坐禅を組め」と言ってるわけではない。椅子に座ったそのままの姿勢で背筋をシャンと伸ばし、丹田のあたりで手を組み、半眼となって深く呼吸し、それをカウントするのだ。ただそれだけのことだ。
ところが、「ただそれだけのこと」が、意外なほどできない。私の経験では、すっと50まで問題なくカウントできた時は「まあまあ、さほど苦労せず、雑念を追い払うことができる人」と言えるのではないかと思う。50以前で「あれ?……いくつまで数えたっけ?」となってしまった人は、ちょっと時間をとって(ほんの20分ほどである)、何回かトライしてみてはいかがだろうか。
うまく行けば、カウントは50を突破し、心のさざなみがスッと静まり、目はうっすらと開いているのだがなにも見ておらず、しかし聴覚は徐々に冴えてくるような、そんな不思議な境地となるかもしれない。
最後に、何度やってもうまくカウントできなかった人に、私なりのちょっとしたアドバイス。
目は半眼で特になにも注視していないのだが、私は1呼吸するたびに、うっすらと開いた目で見ている前方の光景の真ん中に大きく白い文字で「1……2……」と数字を浮かべるようにしている。すると「あれ?……いくつまで数えたっけ?」ということにはならない。
コツと言えるかどうかわからないが、何度やってもうまくカウントできなかった人は、ぜひお試しありたい。
【 つづく 】