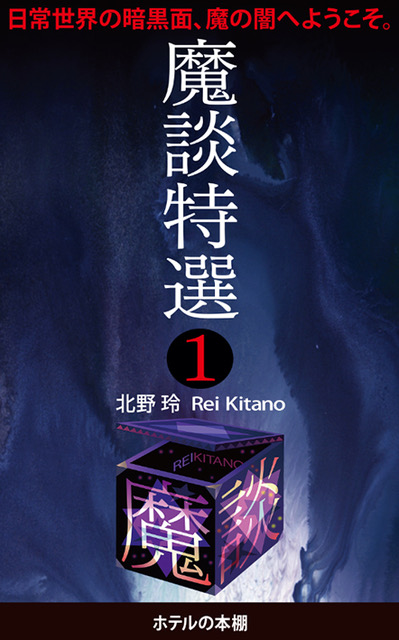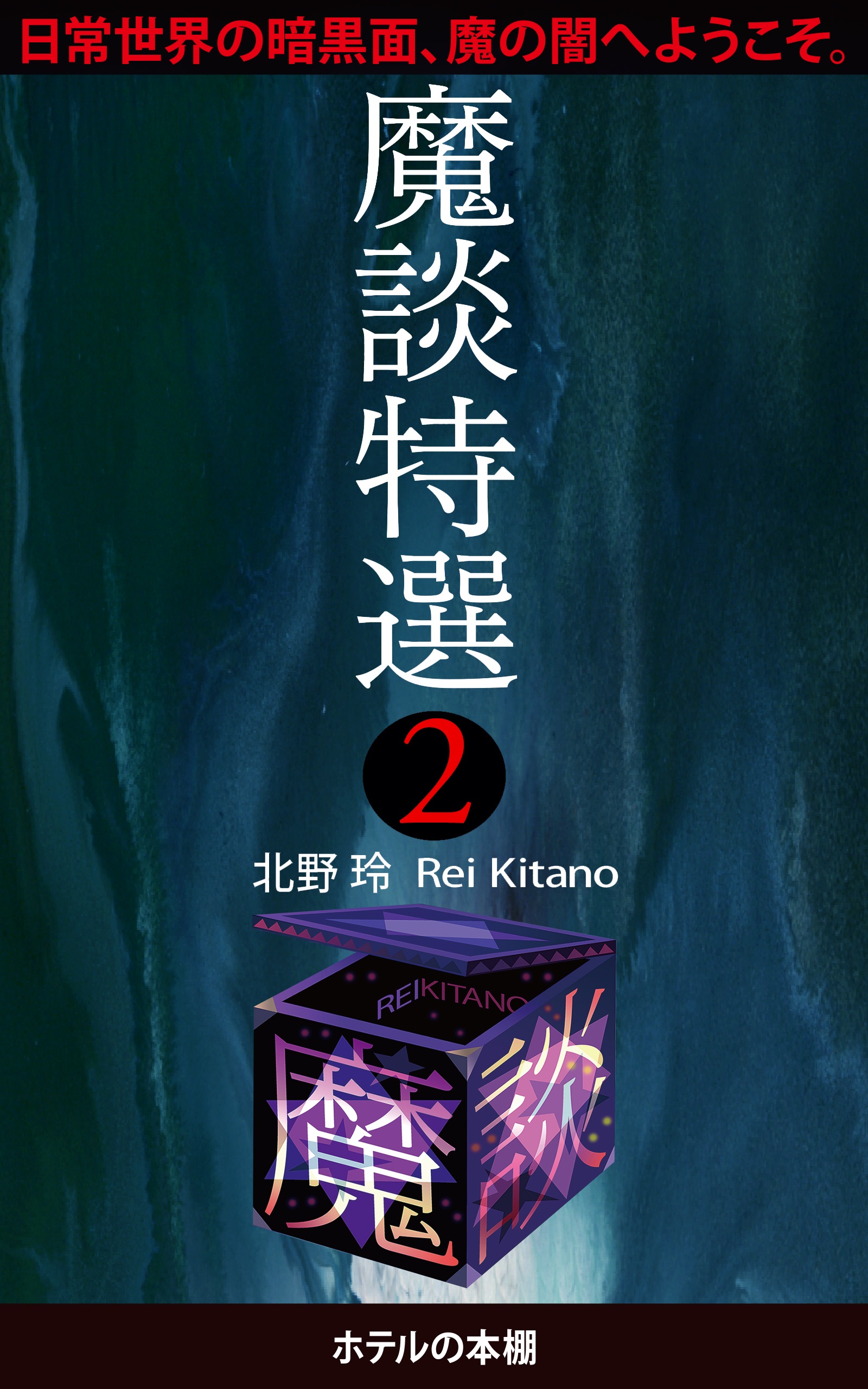【 知らんし 】
比叡山の僧はみな(老いも若きも)「お肉もお魚もあかん」ということになっている。
そもそもなぜ修行というのは「お肉もお魚もあかん」のか。その疑問は叡山に放りこまれて最初の食事を口にした時からあった。かずくんに聞いてみたいと思ったが、私の方から彼に質問することはなかった。当時の私は無口な少年で、母親が「あんたはこっちからなにか聞かへんと、ほんとに口を開かん子や。もっと活発にしゃべりよし」と注意されているような子だった。かずくんになにか質問したい件が出てきても、それを胸の奥に隠し、それを彼にぶつけるタイミングを粘り強く待つような子だった。
そのチャンスがやってきた。半分の5日間が経過したあたりからかずくんはみるみる明るくなった。空腹を我慢できるようになり、私に話しかけることも多くなった。修行とはなんの関係もない雑談、どうでもいい雑談も多くなった。彼のリラックスを見るにつけ、彼が気分よく語っているときに、私は胸の内にいくつかストックしていた質問を小出しにした。
あるときかずくんは「お寺さん」(彼の伯父)はお寿司が大好きという話をした。京都はなにしろ港がない。北の舞鶴に行くにしても、西の大阪に行くにしても、「海」ははるかに遠いというイメージを京都人は抱いている。お刺身にしてもお寿司にしても「高級」というイメージがある。
「お寺さん」の話が出てきたので私はチャンスと見て切り出した。ここ(比叡山)の僧はみな「お肉もお魚もあかん」のに「お寺さん」はなんで普通にお肉もお魚も食べるのか。
彼はグッとつまったような表情をした。元気のない声でただ一言、「知らんし」と言った。
じつにそっけない返事だったが、そのことで私が気を悪くするようなことはなかった。「やっぱし、ようわからんのやろか」と思ったり「あんまし考えたくないことなんかもしれん」と思ったりした。なにがなんでも追求したいようなことでもなかったので、それ以上の質問を重ねることはなかった。

ちょっと余談。京都人は日常的な会話の中で「知らんし」という言葉をわりあいに使う。この言葉の一種独特のニュアンスは関西人以外にはよくわからないかもしれない。これは単に「知らない」という意味ではない。「私には関係のないことなのでどうでもいい」とか「私はそのことにはあまり関わりたくない」といった否定感を含んでいる。
さて話を戻そう。
私の質問は「知らんし」の4文字で片付けられてしまった。私はそれでも全然構わなかったのだが、彼の方はこの質問になにかちょっとした衝撃を受けたようだった。私にはなにも言わなかったが、この質問についてしばらく考えこんでいたらしい。私がその質問をした次の日にいきなり話し始めた。
「ほんまはな、お寺さんも食べたらあかんねん」
私は面食らったが、すぐに「ああ、お肉とお魚のことやな」と了解した。
「修行中はあかんけど、山を降りてお寺さんになったらな、そんなかたいことは言うておれへんねん」
「なんで?」
「たとえばお経をあげに檀家の家に行くやんか。帰る時にな、ちょっと食事の用意をしたんでどうぞ食べていってください、なんてことがよくあるねん」
「ふーん」
「そんなときは断れへん。断ったら失礼や。そんな時によく出てくるのがお寿司や。お寿司を出したらお寺さんは大喜びや」
「ははあ」と私は思った。おかしくなった。
「……この食いしん坊はお寺さんになることで、そういうのも期待してんのやな」
【 つづく 】