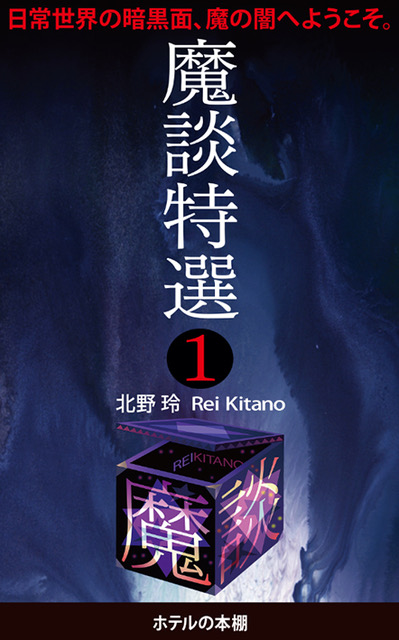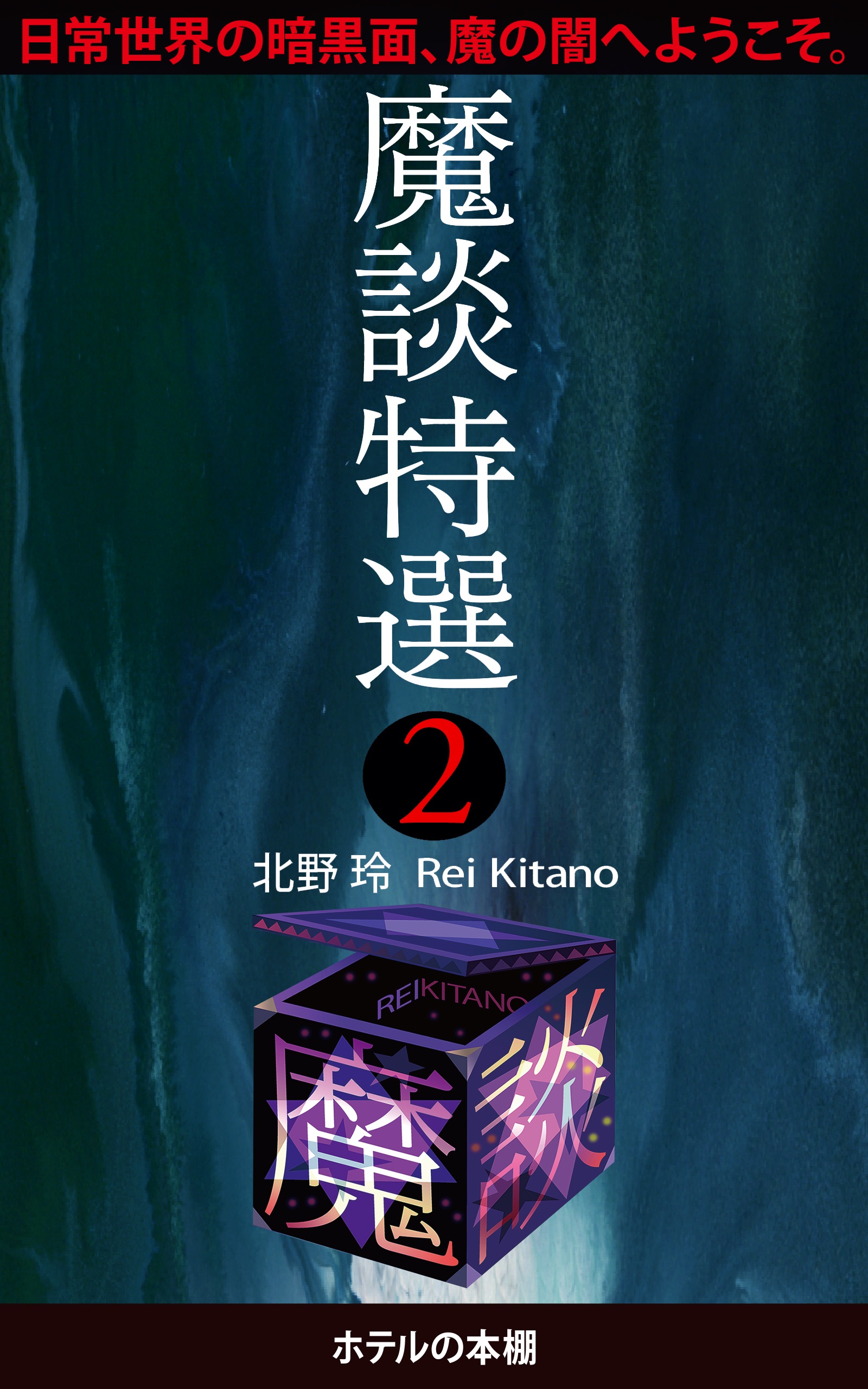【 くまさん 】
修行僧の中に子ども好きの僧がいた。かずくんは「くまさん」と呼んで親しんでいた。おそらく苗字に「熊」の文字が入っていたのだろう。くまさんはまだ若く、25歳あたりの青年だった。小柄で頬のあたりにまだ童顔の面影が残っていた。クリクリと動く目が印象的で「クマ」というイメージよりもむしろ「ネズミ」だった。
彼は庭掃除とか御堂掃除の時にちょくちょく我々のところに来た。ここでは掃除も修行の内であり、子どもと雑談をするなどもってのほかに違いない。そのためくまさんも長くいることはできず、5分やそこらだったが、我々を気にかけてくれているのが嬉しかった。かずくんを見ると「あと何日の辛抱や?」と声をかけた。
「3日?……そうかそうか。もうちょっとのがまんやな」と笑った。
こうしたたわいない会話や笑い声でさえ、ここ(叡山)ではものすごく貴重なことのように思えたものだ。思えば「笑う」という当たり前の気分でさえ、ここではかずくんと私のあいだで(しかも周囲を気にしながら)しか表現できなかった。ここの修行はなんと禁止だらけで、面白くない生活を延々と続けるのかという一種の(少年らしい)反感が、じわじわと私の内に芽生えていったように思う。そうした「えげつない生活」を黙々と実践している僧たちの中で唯一の例外が、くまさんだった。彼だけが「まともな大人」のように見えたものだ。

「ここのお坊さんたちは、みんな1日中、腹をすかしてるんか?」
私の質問にくまさんは思わず笑ったことがあった。ハッと気がついて周囲を見回してから言った。
「そうや。大きな声では言えへんけどな、みんな、一日中、お腹をグウグウ鳴らしてるねん」
「なんでそんなことが修行になるのん?」
「せやな。ほんまにそうやな」
私は驚いた。私の率直な疑問に対してすんなりと肯定してくれた僧は、彼が初めてだった。
「大きな声では言えへんけどな」
これはくまさんの口癖だった。口癖になってしまうほど、ここでは私語は禁止だった。
「ここでの教えはな、人間はいつも腹をすかしてる方が、修行に身が入るという考えやねん」
「腹一杯食べるのはあかんの?」
「あかんことはない。……せやけどな、腹一杯食うてしもうたら、動きたくなくなる。なにもかもどうでもよくなる。修行なんかアホらしいと思うようになる」
「ふーん」
「人間というのはそういうもんや。腹一杯食ったら、〈あー満腹〉とか言うて、幸せを感じてしまう。それはあかん。この山の坊主はな、修行以外に幸せを感じたらあかんねん」
「この山の坊主」という言い方もくまさん独特だった。
私は次第にくまさんと会うのが楽しみになった。彼が説明することを全部理解することはまだ難しかったが、彼が我々に対して「子ども扱い」せず、自分の考えていることを噛み砕いてきちんと説明しようとしていることはよくわかった。かずくんと私の間の会話でも、私は(知らず知らずの間に)くまさんのことを持ち出すことが多くなっていった。「ほんまにくまさんが気に入ったんやな」とかずくんからからかわれるほどだった。それでも「くまさんはこう言うとった」といった話を私は頻々とした。
くまさんとはこの時期に会っただけで、その後、会う機会は二度となかった。かりに彼が25歳だったとして、私(8歳)の17歳年上ということになる。今の私は69歳なので、彼は86歳。まだ生きているとすれば(まだ生きていてほしい)、どこかのお寺の住職になっているはずだ。
くまさんとその後会うことは二度となかったが、思えば私は彼の影響というか、(ほとんど無意識に)彼から学んだことがいくつかあったように思う。そのひとつは(些細なことだが)「相手が子どもであろうと年下であろうときちんと話を聞き、きちんと説明する」ということだ。これは当たり前のことのように思えて、「上から目線」を行使している大人が意外に多い。専門学校の講師でさえ実行できていない人を何人も見てきた。
「あのバカどもにこの(アプリ操作の)説明をするのは難しい」と酒の席で聞いてちょっと驚いたことがあった。酔いにまかせた発言でありその席では他の講師もいたので、私は黙っていた。しかし到底笑う気分にはなれなかった。
当時、私も担当していたMac(マッキントッシュ・コンピュータ)の講義では特に質問が多かった。講義時間が終了しても次の講義に差し支えがないかぎり、詳しく説明した。「この説明は先週にやったはずだ」と思っても、もう一度、1から説明した。私はただ「丁寧に教える」という仕事に徹したに過ぎない。しかし前述の講師(A講師としよう)が担当する講義から抜け出して、私の講義を出入口で聞こうとする生徒が出てきた。当然ながらそんな状況がA講師にとって面白かろうはずがない。
「北野先生はクラス以外の生徒が出入り口にいても注意しない」と学校にチクったらしく、私の講義時間はスタッフが出入り口に立つようになった。情けない気分だったが、私の立場ではどうしようもなかった。
その後、A講師はセクハラ問題を起こし、首になった。私は急遽、2クラスを受け持つことになり、A講師の生徒たちは大喜びだった。私はA講師のクラスを引き継ぐにあたり「出入り口にスタッフを立たせることはやめてほしい。そもそも今後はそのようなことをする必要はない」とスタッフに伝えた。スタッフもわかっていたらしく、即座にそれは了承された。
【 つづく 】