【 仮 説 】
12年前、「時計草庭園」の話に戻る。
「時計草庭園」と名づけた場所から逃げるように去ってしまったものの、そこで出会った御婦人、納屋にぎっしりとひしめいていたシーラ・ナ・ギグ、「サルタヒコ」と名乗る作者。……それらは時計草庭園を去ってしばらくのあいだ、強い印象となって私の心にとどまっていた。いやさらに正確に言うならば、それだけではなかった。私は御婦人の声を何度も思い出しては密かなため息をついた。
私は彼女の声に強く魅せられていた。それは美声ではなかった。低く、かすれ気味で、どことなくヒソヒソ話のような、一種独特の透明感を有した声だった。しかしこのように説明しながらも、その一方で私のダークサイドが冷笑している様子を私はありありと感じている。「この期に及んでお前はまだあのことを隠そうとしているのか?」と軽蔑の視線を向けているような気がする。
……そう、じつはその声は遠い昔、高校生時代に好きだった女子の声と酷似していたのだ。「声など正確に覚えているはずがない。どうかしてるよ、まったく」と首を振るように何度も否定してみたのだが、こうした記憶の片鱗というものは、一度その姿を現すとなかなか消えてくれない。いや消えるどころかますます鮮明な記憶となって頭の中をジワジワと占領してゆくようにさえ思われる。
「こんな、つまらない、どうでもいいことにこだわってる時間などない」と私は自分に言い聞かせた。背後を振り返りたい気分をわざと抑え、前だけを見るように努めた。
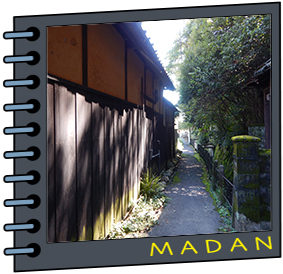
その頃、私は専門学校から出講を打診されている新設「ルポライター養成講座」1年コースの講義を引き受けるかどうかで悩んでいた。その時点で自分が企画したルポルタージュの本が出版社から3冊発行されていたので、実績はあった。「やってもいい。やってみたい」という意欲もあった。
しかしその講義を引き受けるとなると、週に4日は電車に乗って出講しなければならない。「出講は週に3日が限界。これを越えるとフリーで仕事を引き受けているデザインの仕事に支障がでる」という懸念があった。「無理だ」「いや、やってみたい」という気持ちの板挟みだった。
そのような状況だったが、「サルタヒコ」についての興味は持続していた。とりわけ私の関心を引いたのは「サルタヒコの妻はアメノウズメ」という事実だった。これを知った私は時計草庭園の納屋にひしめいていたシーラ・ナ・ギグにつき、ひとつの仮説を立てた。
制作者「サルタヒコ」としては、それは単にシーラ・ナ・ギグの模倣作品なのではなく、そのポーズを型取った「アメノウズメ」を作っていたのではないか。
その仮説を御婦人に伝えてみたいと思った。また「何体も制作する意図はなにか」という率直な疑問も彼女にぶつけてみたかった。
自宅に引きこもって人と会おうとしない制作者「サルタヒコ」がその仮説に応えてくれるとは到底思えない。しかし御婦人なら答えてくれるかもしれない。いやきっと答えてくれるだろう。そう確信していた。
しかしまたその仮説が正しいかどうかわかったところで……「だからなんだ」「どうでもいいことじゃないか」といった一種の虚無感というか、それに近い心情もあった。
結局私は「仮説と虚無」の間を行ったり来たりで日常生活の忙殺に流された。
ルポライター養成講座は引き受けることにした。「やってみたい」という好奇心が優ってしまったのだ。デッサン、イラスト、デザイン、Macのグラフィックツール操作……そうした美術畑では教壇に立ったことは何度もあった。しかし文学系で教壇に立ち生徒たちと接したことはそれまで一度もなかった。これを経験してみたいという好奇心がむくむくと出てしまった。
予想どおり、かつてない忙しさとなった。「ルポライター養成講座」が始まり私の出講に追加された。いつしか時計草庭園の一件は意識から遠のいていった。
【 再 会 】
時計草庭園に入ったのは一度だけだった。それは8月の半ばの、まさに盛夏を思わせる日だった。それから季節はめぐり、10月から「ルポライター養成講座」が始まった。
突然の再会は11月初旬に起こった。
その日、私は市役所近くの喫茶店でルポ作品の評価をしていた。生徒は全部で12名で、男性は3名だった。9名の女生徒のうち「この子はプロになれそうだな」と思われる抜群に文章が上手い子が2人いた。
課題は「誰でもいいので(……と言いつつ、担当講師である私以外だが)本校の講師をひとり捕まえて、その仕事内容を2000文字前後で紹介せよ」というものだった。
これは私が考えた課題だった。「ターゲットとなる講師はダブってはいけない。お互いに誰を取材したか、十分に注意すること」と文書で伝えていたにもかかわらず、ひとりの男生徒とひとりの女生徒の提出作品がダブっていた。
「クラスメイト同士でルポを見せ合ったりしないのだろうか。会話はないのか。そんなんでプロを目指していると言えるのか」……などと多少イライラした気分を意識しながらダブった2作品につき処分というか対応について頭を悩ましていた。
すぐ脇の窓ガラスがコツコツと音を立てた。
ハッと現実に戻ってその方向を見ると、そこに御婦人が立っていた。
* つづく *
魔談が電子書籍に!……著者自身のチョイスによる4エピソードに加筆修正した完全版。amazonで独占販売中。
専用端末の他、パソコンやスマホでもお読みいただけます。