【 京都市動物園 】
京都に動物園がある。ご存知だろうか。京都市動物園。京都観光が好きで有名な神社仏閣には何度も足を運ぶような人でも、動物園があることは知らない人が意外に多い。「京のみやび」で癒しを求める気分とは、微妙に合致しない場所なのだろうか。
京都市民からは「岡崎動物園」と呼ばれて親しまれている。左京区岡崎にあるからだ。開園明治36年。上野動物園に次いで「日本で2番目に古い動物園」である。
ここにいる動物たちの間で、なかなかの人気なのがゴリラだ。4頭いる。夫婦とオスの子ども2頭、つまり1家族なのだ。
このゴリラ家族を見るために京都市動物園に足を運ぶ人は多い。中にはスケッチブック持参でデッサンする婦人(画家)もいるという話だ。この画家はゴリラだけがお目当てで、埼玉県からわざわざ岡崎に来るそうだ。
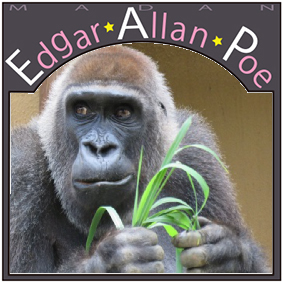
京都在住の友人(出版社勤務)も数ヶ月に一度は(ひとりで)ぶらっと岡崎に行き、その日はほぼ1日、園内でのんびりと過ごすそうである。彼もまたゴリラ一家は必ず見に行くそうだ。「よくじゃれあって笑ってる」らしい。私はちょっと驚く。
「笑ってる!……ゴリラは笑うのか?」
2頭の子どもたちはずいぶん歳が離れているのだが(2歳と10歳)、とても仲がよいらしい。よくじゃれあっているらしいのだが、そんな時は双方とも独特の声を発するという。「ホッホ、ホッーホ、ホッホ」といった感じの優しい声らしい。
「聞けばわかる。あれは笑い声だ」
友人は目を細めるようにしてゴリラ一家の話をした。私は「モルグ街の殺人」を持ち出そうとしていたのだが、やめた。
【 映画ではゴリラ 】
さて「モルグ街の殺人」。
オランウータンは、本当に、こんなふうに無抵抗の女性2人を惨殺するだろうか。いかに逃走中で、気が立っているとはいえ、カミソリを振り回して婦人を切りつけ、窓から放り投げ、娘の喉を締め上げて窒息死させ、超人的な力で煙突の中に逆さに押し込んだ……そんなことをするだろうか。
仮に現在のオランウータン研究者にこの話をしたらどうだろう?
「ありえない」
そんな答えが返ってきそうに思うのだが、あなたはどう思うだろうか。
映画でもその点で、つまり可能性の是非はともかく、ルックスとしてもイメージとしても「オランウータンでは映画にならん」と思ったのだろう。そこでオランウータン役をゴリラにした。ゴリラの方がオランウータンよりも獰猛そうだし、怪力もありそうだし、「キングコング」なんて映画もあることだし、てなところなのだろう。ゴリラにとっては迷惑千万な話だ。
ではポーはその点につき、どう考えていたのだろう。
ひとつの仮説としては、ポーには情報が少なかった。じつはオランウータンを見たことがなく、当時の博物学者が伝えていた情報だけでオランウータン像をつくってしまったのかもしれない。原作のデュパンもこのように述べて、語り手(つまりは読者)に納得させている。
「キュヴィエのこの章を読んでみたまえ」
それは東インド諸島に棲すむ黄褐色の大猩々(おおしょうじょう)を解剖学的に、叙述的に、詳しく書いた記事であった。この動物の巨大な身長や、非常な膂力(りょりょく)、活動力、凶猛な残忍性、模倣性などは、すべての人によく知られているところである。私はあの殺人が凄惨を極めているわけをすぐに悟った。
ジョルジュ・キュヴィエ(1769ー1832)。当時の高名なフランスの博物学者である。
じつはポーが「モルグ街の殺人」を発表した1841年当時、アメリカ人もヨーロッパ人も、その大半がオランウータンもゴリラもサルも見たことがなかった。ヨーロッパ界隈に野性の類人猿はいなかったのだ。当時のヨーロッパ人はみな新聞の記事や雑誌や博物学の本で「人間の姿に近い動物」を見て驚いたのだ。「オーマイガッ!……こんな動物がいるのか!」とすごく気味悪く思ったことだろう。
✻ ✻ ✻
博物学者キュヴィエはなにを根拠に「凶暴な残忍性」などと書いたのだろう。博物学者率いる探検隊が現地でオランウータンを捕獲するために追いかけ回した。追い詰められたオランウータンは歯をむき出して怒った。その形相を見て博物学者はおそれおののき、「凶暴な残忍性」と書いた。真実はそんなところじゃないだろうか。
あるいはまた、こんな想像もできる。ポーにとって実際のオランウータンなど、どうでもよかったのだ。彼はたまたま見つけた新聞記事で博物学者が書いたオランウータンの解説を目にとめ、「凶暴な残忍性」と知ってひらめいたのだ。
当時の彼は全米でもトップを争う人気雑誌の辣腕編集者であり、人気作家だった。読者という大衆に「恐怖という娯楽」を与えるための道具として「誰も見たことがない凶暴なオランウータン」という犯人設定、「これはいけるぞ!」という計算でつくった小説だったのかもしれない。こうして世界初の推理小説は誕生したのかもしれない。
【 完 】

