【 長 良 文 芸 社 】
まず最初に思ったのは、(あの声が聞ける!)ということだった。
我ながら奇妙なことだと思う。「声に恋する」などということがあるだろうか。しかもその声が誘発するのは本人ではなく、はるか昔、高校生時代に(ひそかに)好きだった女子の声なのだ。自分にとってはせつなくむなしい気分になるだけであり、相手にとってはじつに失礼な話だというほかない。いいことなんかひとつもない。にもかかわらずこの心の高揚感はいったいどういうことなのだろう。
そんなことどもをあれこれ考えている最中に、彼女は目の前に来た。あわてて立ち上がり、(いや立ち上がる必要などないだろ?)といった自嘲を感じ、「……あ、どうぞ」と目の前の席を示した。彼女が座るとしたら目の前の席しかないに決まってる。我ながら無様で狼狽丸出しの所作となった。改めて見ると生地がやや厚い作務衣とでも言おうか、じつに美しいムラサキ色で、袖のところに蝶の刺繍があった。活動的でお洒落な和服ファッションだ。
身長170cmは優に越えている長身の(店長の)奥さんがサッと来た。奥さんは彼女が窓ガラスをコツコツとたたくところから私の席に来るまでの一部始終をじっと見ていたのかもしれない。私の狼狽ぶりも見ていたのかもしれない。オーダーを受けながら「あんたも色んなことがあるみたいね」みたいな感じの、うっすらとした含み笑いを見せながら私をチラッと見た。
彼女がコーヒーをオーダーしている間に、私は机上のA4出力紙を手早く片づけた。ルポ課題の提出は「A4サイズで出力/文字は縦組/天地30文字・左右30行」と文書で指定していたにもかかわらず、何人かの生徒はその条件を全く無視していた。ある男子生徒に至っては、あろうことか横組文字で提出していた。「こんな雑な感覚でプロを目指していると言えるのか」と記入したいほどの提出作品が数点あった。
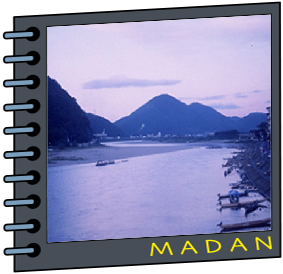
「ご無沙汰しておりました」と私はまず謝った。時計草庭園に入ったのは8月の盛夏で、その日は11月の初旬だった。
「いいえ、こちらこそ」と彼女は笑い、机上の出力紙に視線を走らせて「お仕事の邪魔だったのでは」と言った。私は笑った。「ルポライター養成講座」講師を引き受けた経緯を手短に話し、「……今頃になってかなり後悔してます」と言った。「こんな仕事は……」と言いかけてふと思い出した。
「そうそう。あの時は名刺を渡すこともせずさっさと退散してしまい、失礼しました」
私はカバンから名刺入れを出して1枚を抜き、彼女に渡そうとした。
「いいえ、私こそ」と彼女は笑い、着物の内ポケットから(ちょっと驚いたことに彼女の着物には内ポケットがあった)名刺入れを出した。
我々は名刺を交換した。彼女の名刺を机上に置き、改めて見た。角が丸い上品な和紙に黒文字だけの印刷。名前はたった2文字だ。孤蝶。筆名なのだろう。その上に小さな文字で「長良文芸社」。
「長良文芸社……地元の出版社ですか?」
「はい。ひとりでコツコツと本を出してます」
「なるほど。……どんな本です?」
「俳人さんたちの句集とか、詩人さんたちの詩集とか、小説サークルの同人誌とか……」
「ああなるほど。地域貢献の出版ですね」
岐阜市にはそうした文芸サークルや絵画サークルが多いという話を聞いたことがある。なにしろ50年ほど昔、あの「柳ヶ瀬ブルース」が生まれた頃には「名古屋で飲むより岐阜で飲んだ方がよほど面白い」と言われた繁華街全盛期時代を謳歌した街だ。「……その名残り」などというと怒られそうだが、その時代からの、庶民的な文化芸術を愛好する気風がまだ残っているのかもしれない。「デザイナーの会」などというものまであり、誘われて一度だけ集会に参加したことがある。しかし年配デザイナーたちの「往年の仕事自慢」を拝聴するだけの会だと知り、あきれて二度と参加しなかった。
【 孤 蝶 】
「サルタヒコさんはお元気ですか?」
「まあ、どうにか」と言った孤蝶さんの表情は微妙に曇っているように感じた。
「相変わらず、ひきこもりですか?」
こんな話題は嫌かもしれないと知りつつ、重ねて聞きたい気分の方が優先してしまった。私としては「サルタヒコ作のシーラ・ナ・ギグは、じつは(サルタヒコの妻である)アメノウズメ」説を持ち出して彼女の反応を見たかった。また「サルタヒコが何体もシーラ・ナ・ギグを制作する意図はなにか」という率直な疑問もぶつけてみたかった。
ところが……
「家出しました」
言葉を失った。
* つづく *
