【 絞首台の形 】
今回は語り手を震え上がらせた「黒猫の胸の白い毛」から話を始めたい。
それが、とうとう、まったくきっぱりした輪郭となった。それはいまや私が名を言うも身ぶるいするような物の格好になった。(原作)
黒猫の胸の白い毛。それが徐々に「きっぱりした輪郭」に変化していく。そしてついに絞首台の形となって、語り手を震え上がらせる。
この「絞首台の輪郭」は現代の日本人読者にとっては、いまひとつピンと来ない人の方が多いに違いない。私もそうだ。あなたはどうですか?
もちろんポーを読もうというほどの人だから、絞首台というもののおぞましい存在は知っているだろうし、それが具体的にはどんな形状のものなのか、「きっぱりした輪郭」までは連想できないまでも、この言葉のみで語り手の戦慄は十分に伝わるだろう。
とはいえ「黒猫」はリトールドされて、小学校の図書室にもあるほどの小説だ。古今東西の様々な本で挿絵があるに違いない。そこに描かれた黒猫の胸の白い毛を見て(語り手が一見して戦慄したように)「うわっ、これぞ絞首台!」というあっぱれな挿絵があるかもしれん。
そうした期待であれこれ調べてみたのだが……結果、そのような挿絵はなかった。
「おいっ、「黒猫」の挿絵を依頼された画家たち! そんなことでどないすんねん!」と叫びたいところだが、ここにひとり、じつに奇怪な「黒猫」挿絵を描いた画家がいる。
オーブリー・ビアズリー(1872〜1898)。御存知だろうか。
1872年、ポーが客死した1849年から23年後にイングランドで生まれている。イラストや挿絵に興味のある人であれば、知らない人はいないほどの有名な挿絵画家である。白黒のみのペン画でじつに精緻な挿絵を描き「耽美主義の鬼才」と評されたが、25歳で死んでしまった。そういう画家である。
そのビアズリーが「黒猫」の挿絵を描いている。挿絵には「黒猫の胸の白い毛」も描かれている。ところがこれがまたじつに奇妙なことに「複雑な模様がからみあった円形の模様」としか説明できないような形状なのだ。どう眺めても、その模様から絞首台は見えてこない。
ビアズリーはどのような意図でこんな模様を描いたのだろう。あれこれ調べてみたのだが、ビアズリーの評論は山ほどあるものの、この疑問に対する明瞭な解釈なり説なりはついに出てこなかった。
「おいっ、ビアズリーの評論家たち! そんなことでどないすんねん!」と叫びたいところだが、さすがの評論家たちもお手上げだったのだろうか。ビアズリーは屈折した引きこもり画家だったので、評論家たちをケムに巻こうとしてこんな模様をでっち上げたのかもしれない。
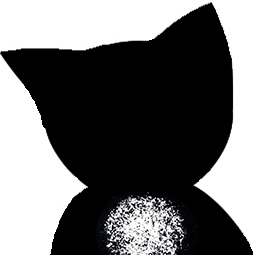
話を戻そう。「ビアズリー黒猫」の謎は解けなかったものの、ポーが生きていた時代のアメリカ人にとっては「絞首台」というおぞましい言葉の暗黒イメージは、かなり強烈なものだったのだろう。「黒猫」をあれこれと調べているうちに、そうした「当時のアメリカ社会のダークサイド」とでも言おうか、かすかに匂ってくるものがある。
私なりの結論を先に言ってしまうと、どうやら「絞首台」のイメージは「魔女狩り」の暗黒歴史と繋がっているように思われる。これについては、もう少し後で詳しく述べていきたい。
【 黒猫という魔女 】
さて語り手は地下室に降りる階段で黒猫に足をとられ、転げ落ちそうになり(いっそ転げ落ちてしまえばよかったのだ)、逆上した。
彼は(地下室に降りるという用事で)なんでオノなんぞを持っていたのだろう。よくわからないが、逆上したあげく、オノで黒猫を打ち殺そうとした。止めに入った奥さんにさらに逆上し、あろうことかオノは奥さんに向かって振り下ろされた。
この顛末を全く知らずここまで読んできた読者なら、まさにここで「ああーっ」と悲鳴をあげてしまうような最悪シーンだ。
✻ ✻ ✻
それにしてもこの小説の奥様にはもう本当に「お気の毒」というよりほかない。詳しい描写はないのでルックスなどよくわからない点が多く影の薄い女性だが、「お互いに動物好き」ということで、この最悪の男と結ばれたのだろう。
そうそう、唯一、彼女の言動で印象に残っている一点があった。最初の黒猫、プルートーという名前でしたな、(そういえば2番目の黒猫には、名前さえついていない)、彼女はこの利口な黒猫にすっかり心を奪われ、「黒猫は魔女が姿を変えたもの」という昔からの言い伝えを何度も口にしたのだ。
このように考えてみると「黒猫に姿を変えている魔女」が、ついに彼女の仇を打った……この話の結末はそのようにも受け取れる。
次回は戦慄の結末を語りたい。
【 つづく 】

