キネマ旬報の昨年度のベストテンで、予想に反して「国宝」は2位だった(1位は「旅と日々」)。妥当かも知れない。私も昨年絶賛したが、年末に2回目を見たら、脚本のアラが気になってしょうがなかった。それで、原作の小説を買って読んでみた。主人公喜久雄(吉沢亮)の長崎時代からの恋人春江(高畑充希)や、芸妓との間に生まれた綾乃(瀧内公美)との関係が原作ではどう描かれているのか?
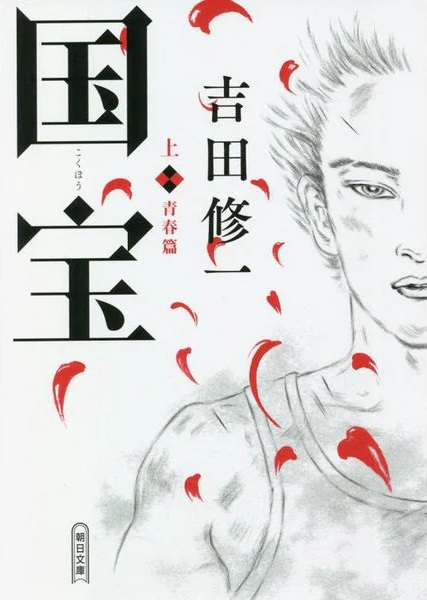
『国宝』吉田修一作 朝日新聞出版
前後編の2部作だが、後編が映画と相当に違うことにビックリしてしまった。映画は端折ってしまっているというか、バッサリ切っているところが多い。
一番驚いたのは、映画でラストにカメラマンとして登場する綾乃が、それまで全く交流が無く突然現れたように描かれたが、原作では、親子で仲の悪い時期もあるものの、ちゃんと親子としての交流があるのである。おまけに、この綾乃、出版社に就職した後、相撲取りと結婚しその相手が横綱になる!
喜久雄と妾となった彰子(見上愛)との関係も何十年もわたって描かれている。
また、俊介(横浜流星)の足の切断の原因は、原作では地方公演で舞台から落ちて怪我をしたからだが、映画では父親と同じ糖尿病だった。安直ではないかなあ。遺伝があるなら、息子はきちんと節制しなかったのか、と皮肉を言いたくなる。
また、映画では、喜久雄は彰子とドサ周りをするが、それはない。スキャンダルの後、いい役に就けなくなるが、歌舞伎界に依然残っているのである。などなど、随分改変されている。
残念なのは、徳次という、冒頭のシーン、長崎で一緒に喜久雄が歌舞伎を演じた年上の男の存在。原作では、ずっと、喜久雄と関りを持ち随所で彼を助けるが、途中、中国大陸に渡る。彼がラストに鮮やかに登場するシーンも見事にカットされている(このラストシーンは、真に映像的でこの小説の白眉の1つ)。
勿論、映画と原作は別物だから云々する気はない。原作はよく考え抜かれていると思うが、映画の脚本は不満の残るものである。
さて、原作者の吉田修一が「100年に一度の芸道物」というコメントをしているが、これはきっと「残菊物語」を意識しての発言だろう。この作品は1939年(昭和14年)、溝口健二監督の見事な傑作である。

「残菊物語」監督:溝口健二 出演:花柳章太郎 森赫子ほか
歌舞伎の2代目尾上菊之助(花柳章太郎)は、身分が下のお徳と共に東京を離れ大阪に行き、田舎廻りをするなど辛酸をなめつつ芸を磨こうとする。苦節4年、代役で「積恋雪関扉」(つもるこいゆきのせきのと)で女形を演じて芸を認められる。しかし、糟糠の内縁の妻として苦楽を共にしたお徳は消えてしまう。
好きな人の成功を喜ぶ気持ちと、自分が身を引かざるを得ないことを知るお徳の心中を思い、もう、涙するしかない。ラスト近く、二人暮らしたおんぼろ下宿で、菊之助に言う「晴れて、あなたと呼んでいいんですね」は名文句。正に、情緒纏綿(てんめん)、子守唄を聞くようなゆったりした映像リズムが心地よい。
美術も見事。ラスト、大阪の堀を、歌舞伎ファンの歓呼の中、提灯を掲げて、菊之助が乗った船が進んでいく映像など素晴らしいの一語。
ほとんど音楽が無く、虫の声、太鼓の音、物売りの声などの現実音が効果的。お徳を演じた森赫子の、少し甲高い声も演技もいい。この映画は、溝口お得意のワンシーン・ワンカットの技法が成立した作品としても知られる。
好きな映画をもう一本!「国宝」では、「曽根崎心中」の舞台が描かれた。お茶屋の遊女お初が、茶屋で床下に隠れた油屋の手代徳兵衛に、一緒に死ぬ覚悟があるかどうか聞く場面だ。花井半二郎は、喜久雄に対して「死ぬる恐さ」と好きな人と一緒に「死ぬる喜び」がない交ぜになった感じを出さにゃあかんのや、と言っていた。

「曽根崎心中」監督:増村保造 出演:梶芽衣子 宇崎竜童ほか
1978年(昭和53年)の映画「曽根崎心中」も中々の力作。増村保造監督作。黒メガネを外した歌手の宇崎竜童と梶芽衣子が主演。宇崎は台詞回しが固いものの一途な徳兵衛を体当たりで熱演。梶芽衣子も、狂気スレスレのギラギラ光る眼をして恋の意地を通そうとする役を好演した。
お寺で徳兵衛が信頼して金を貸した友人たちに殴られ蹴られ、池に投げ込まれるシーンは迫力ある。彼が、せつなさそうな顔をして床下でお初の足をさすったり頬ずりしたりするシーンがまたいい。ラストの心中は血が噴き出し凄絶。増村のリアルかつ容赦ない演出に引き込まれる。
(by 新村豊三)