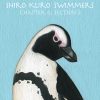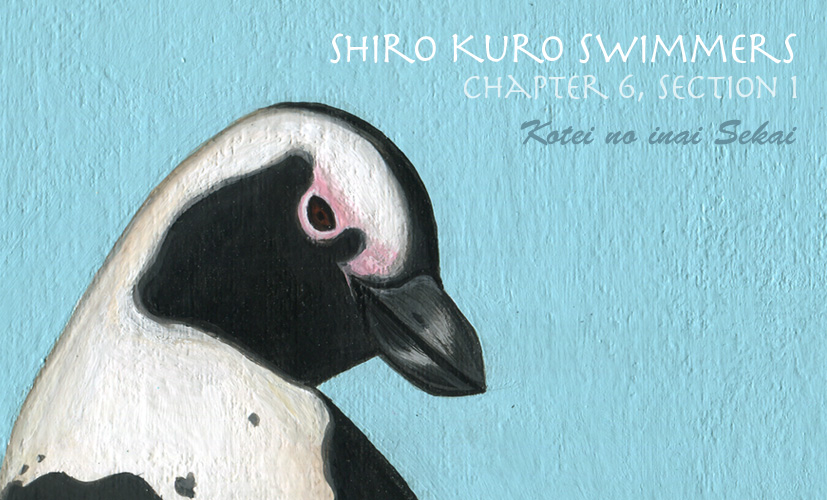
皇帝は焦っていた。遅れてしまう……急がなければ……。すっかり重たくなった大きな体を大儀そうに動かし、暗闇の中で店のドアの鍵を閉めた。そして、店から離れ歩き出した。歩きながら、無意識にカバンの中から魚を取り出しクチバシに放り込む。魚を飲み込もうとした瞬間、大切なことを思い出し、思わず魚を噛んでしまった。
「肝心の張り紙を忘れていた」
皇帝は、方向転換し店に戻った。焦燥と興奮で汗はだくだくと流れ続ける。クチバシにも生暖かいものが伝う。フリッパーで額とクチバシを拭った後、暗闇の中、一枚の紙をドアに貼り付けた。そして、店に背を向けた。皇帝の目の前には人気のない深夜のおさかな商店街の暗闇だけが広がっていた。
* * *
「ルトトちゃん、太った!?」
「そうなの!房子ちゃん、分かってくれて嬉しい!ダイエットして太ったの!」
ロイヤルペンギンの貴族貴子(きぞく・たかこ)の店、ロイヤル紅茶館に仲良しのメスペンギン、フンボルトペンギンの分堀戸ルトト(ふんぼると・るとと)とヒゲペンギンの比毛房子(ひげ・ふさこ)の二人がお茶をしている。
「そういう、房子ちゃんも太ったよね!」
房子は、嬉しそうに自慢のヒゲを軽く揺らして「うふふ」と笑った。
ペンギンの「ダイエット」とは、人間のそれとは異なる。人間の場合は、「痩せる」ことがダイエットであるが、ペンギンの場合は、「太る」ことがダイエットなのだ。太っている方が美しい、ペンギン特有の美的感覚である。
「あらあら、二人とも素敵なレディですわ。基本マナーがしっかり身についたからこそ、美しく太ったのですよ」
貴族が豊満な体をしなやかに動かしながら、二人のそばに近付いた。
「確かにそうですね。貴族さんには感謝しています」
「本当に嬉しいです!……あ・貴族さん、私、この新メニューのロイヤルおさかなアイスティーを追加でお願いします」
「私も!」
貴族は、若いペンギンの二人に優しく微笑むと、カウンターに戻り、ロイヤルおさかなアイスティーを作るため、冷凍庫を開けた。
「あら……!」
氷がほとんどない。かろうじて注文のアイスティーを作り終えて出した後、貴族は、
「氷を早めに注文しなきゃならないわ」
と、皇帝の店、氷屋に電話をかけた。
「ペペペペン……ペペペペン……」
受話器からは、呼び出し音が鳴り響くが、一向に電話に出る気配がない。何度もかけてみた。しかし、結果は同じだ。
「皇帝さま……」
受話器を握ったまま、貴族は不安になった。皇帝は、いつもすぐに電話に出るし、いない時は必ず留守番電話の応答になる。
「皇帝さまがいない……」
貴族にとって、皇帝は特別な存在なだけあって不安は募る。貴族は、「皇帝」に尊敬の念を抱いているのだ。そして、次に尊敬しているのは「王」だ。その理由は、ただ単に名前が「皇帝」と「王」だからである。しかし、名前が「貴族」の貴族にとって、理由はそれだけで十分であった。貴族は自分より位が高いペンギンとして皇帝と王を盲信していたからである。
そこに店のドアを開けて、「清酒魚盛」の前掛けを掛け、異様に長い例のカチューシャをつけた王が入ってきた。
「こんちにはー!酒屋の配達でーす」
「あっ!いいところにいらしたわ!王さま!」
配達の荷物を抱えてカウンターに来た王に、貴族は腰をかがめて貴族的な挨拶をした。
「貴族さん、やめてって言ってるじゃない。その『王さま』っていうの……」
王は困ったように特製シュレーターズカチューシャを揺らした。
「それより、王さま、皇帝さまの店に氷の注文で電話したのですが、出ないんです。どうしたのかしら、皇帝さま……」
貴族のワインレッドの瞳が潤んでいる。
「え!そうなの!?数日前に会ったんだけどな」
「皇帝さま、どこかに行かれたのかしら。もしや、『歩きおさかな』をして、大穴にハマってしまったとか……。それとも、平民の中で生活するのが嫌になってしまったのかも……」
「平民って!貴族さん、皇帝さんも我々も平民だよ。でも、皇帝さんが店にいないのは確かに心配だね」
「王さま、配達の途中で皇帝さまのお店の様子を見てきてくれないかしら?」
貴族は、肉感的な体をしならせ、上目遣いに王に懇願した。
王は、貴族のそんな媚態に反応している風でもなく即答した。
「うん、いいよ。私も心配だし。配達途中に寄ってみるよ」
「王さま、さすが王さまだわ。感謝致します」
貴族は、深々とお辞儀をした。
約束通り、王は、配達途中に皇帝の店に寄ってみることにした。皇帝の氷屋は、おさかな商店街では海に近い場所にある。氷屋の青い屋根が見えてきた。その屋根の下、皇帝の氷屋の入口前に、一人のペンギンが佇んでいるのが分かった。それは、ボストンバックをフリッパーに持った中型の見知らぬペンギンだ。
「誰だろう?」
氷屋の前には営業中の看板が出ていない。店内には光がなく、中からカーテンが下されているようだ。店が閉まっていることは一目瞭然だ。そして、見知らぬペンギンは、店のドアに貼られた一枚の紙をじっと見ている。
氷屋に近づいた王は戦慄した。皇帝の店のドアの張り紙がハッキリと見えてきたからだ。その張り紙は、赤いシミで汚れていた。それは明らかに血痕であった。
(つづく)

浅羽容子作「白黒スイマーズ」第6章 皇帝のいない世界(1)、いかがでしたでしょうか?
ルトトと房子、まるまるぽてぽて幸せなティータイムのおすそ分けで和んでいたら、なんということ!ペペペペン……の電話の音に誰も応えず、あの皇帝ペン一郎さんが、血染めのメッセージを残し謎の失踪。そしてタイトル絵になっている、目の周りのピンク色が愛らしいペンギンは一体誰でしょう?幾多の謎を残して、次回へ!
ご感想・作者への激励のメッセージをこちらからお待ちしております。次回もどうぞお楽しみに。
※ホテル暴風雨にはたくさんの連載があります。小説・エッセイ・詩・映画評など。ぜひ一度ご覧ください。<連載のご案内>