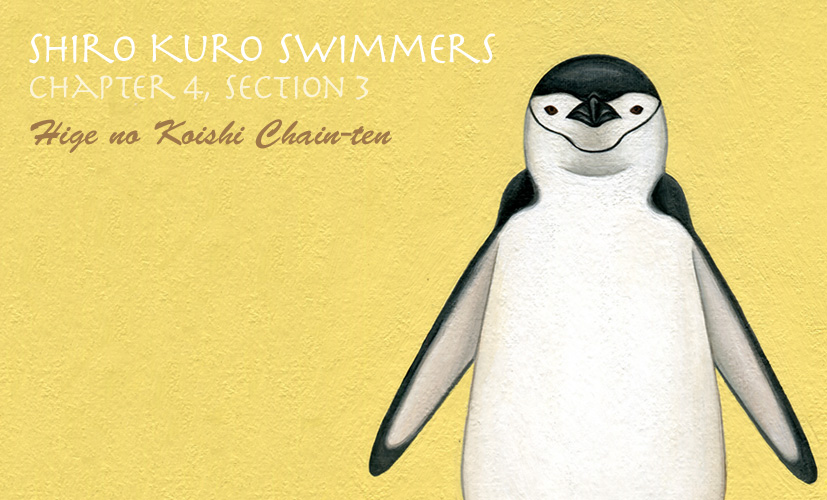
「それで、昨日は、阿照(あでり)さん、比毛(ひげ)さんの店で小石は買わなかったの?」
阿照のプロマイド店に来ている慈円津(じぇんつ)が阿照に尋ねた。
「うん……。あんなところ見ちゃったし。持ち合わせがないから、また来るって言って帰ってきちゃった。それに、なにより、あの店の小石って……あれでしょ?」
阿照は、自分の胸の巾着を触った。慈円津は、その巾着をチラリと見ると、首を縦に振った。
「そう……YESよ。比毛さんの店の小石って大量生産よね。阿照さんのその小石と順子にあげたネックレスに混ざっていた小石、全く同じだったみたいよ。よく見ないと気がつかないけど」
「そうそう、店にも僕のと同じ小石があったんだよね。まぁ、どれも素敵な小石ではあるけど。でも、同じ小石があるとなると魅力は一気に半減だな」
阿照は豆絞りの手ぬぐいの下のクチバシから魚臭いため息をついた。
「やっぱり小石は天然がいいわよね」
慈円津も同意し、ねじりハチマキを締めた顔を可愛らしく傾げた。
「うん……そうだね……手作りでもいいけどね……」
阿照は、自分の巾着から小石を取り出しフリッパーの上に乗せた。
「あら?じゃあ、阿照さん、その小石いらないのね!いらないのなら、ちょーだい!」
「ダメだよ!慈円津さん!」
阿照は、急いで小石を巾着に戻すと、慈円津は「冗談よ」と言い可愛く笑った。
そう、比毛の小石チェーン店の小石は、工場で大量生産しているのである。
工場で働いているのは全てフンボルトペンギンの一族だ。彼らは、大人しい性格で手先が器用な専業漁師であった。そんな彼らを言葉巧みに工場勤務に斡旋したのはヒゲペンギンの比毛ボーボである。
「君達、これからの時代はね、労働の時代なのだよ。働くことは素晴らしい。専業漁師もいいが、もっと別の職業こそ生きている価値があるというものだ。私の小石工場で勤務することこそ、新しい時代を生きるペンギン達の真の姿なのだよ!」
確かに、比毛の言う通り、最初の頃の工場は働きがいもあり良かった。フンボルト一族が作った手作り小石は評判で、待遇もいいし、労働は確かに楽しかったのだ。しかし、小石が売れ出して大量生産されると、チェーン店化が進んだ。それに連れ、徐々に労働時間は増え、ノルマもできた。ノベルティグッズの付けヒゲの生産も始まり、作業は増える一方だ。それと反比例して、「機械購入や開店費用がかさむ」という理由で給料は毎月下がっていく。フンボルト一族にとって、ペンペンとした毎日が始まったのだ。こうして、いつしか、ノルマに追われるフンボルト一族は漁に出る暇さえもなくなってしまった。そう、あんなに楽しかった小石作りが、いつしか辛いだけの作業に……。
そんな一族の若い兄妹、分堀戸(ふんぼると)ボルルとルトトが、直訴に敗れて工場に戻った後、比毛の指示通り、1日20時間勤務となってしまっていた。1日たった4時間の自由時間である。今日も20時間働いた兄妹は、ヌルイ区の自宅に向かいやつれきった様子でトボトボペンペンと歩いていた。
「ボルルお兄ちゃん……比毛社長怒らせちゃったのがいけなかったのかな……」
「……うん……」
ペンペンと歩く分堀戸兄妹の正面から歩いてくるのは、同じヌルイ区の住人、黄頭ボブ尾(きがしら・ぼぶお)だ。頭に新種のクラゲをふんわりと乗せている。兄妹に近づいた黄頭は、二人に声をかけた。
「分堀戸さんちのボルル君とルトトちゃんじゃないか。久しぶり。元気……そうでもないね……」
ボルルとルトトは寝不足で充血した瞳で黄頭を見た。
「あ、黄頭さんか……。知っての通り、僕たち小石工場に勤めているんですけど……」
「すごく困っているの……」
黄頭は、じっと兄妹をレモン色の鋭い瞳で見た。兄妹のフリッパーは荒れ、痩せて腹は凹み、羽毛はガサガサ、極度の疲労のため朦朧としている。黄頭は鋭い視線のまま言った。
「君達、困った時はどうするか、覚えていないのかい?」
「……!?」
兄妹の前で、黄頭はクラゲを頭に乗せたまま、自分の腹を撫で出した。色素の薄い瞳をまばたきもせずに、じっと兄妹を見つめながら。
兄ボルルは、息を飲んだ。そう、黄頭を見て、忘れていたことをペンとして思い出したのだ。
「ルトト、腹を撫でるんだよ!僕らペンギンが困った時は、腹を、撫でるんだよ……!」
「そうね、ボルルお兄ちゃん!」
すぐに兄妹は、その場で目をつむり、無心に腹撫でをし出した。すでに見えないペンギンオーラが二人を取り巻いている。
黄頭は、やせ細った兄妹を見て、つい「君達、海に行けば……」と言いかけたが、言葉を飲み込んだ。そして、クラゲを乗せたまま、そっとその場から立ち去ったのである。
クラゲは、フワフワと黄頭の上で一回転をしている。
「きかしらさん、僕のお腹はどこだろう?僕もお腹撫でたいなぁ」
「クラゲくん、君は……クラゲ……だろ?クラゲは腹を撫でなくていいんだよ」クラゲは、寂しそうに口をへの字に曲げた。
「クラゲくんがクラゲなんてつまんない。僕もペンギンになりたいな……」
「ふふ、クラゲくんは、そのままでいい」
クラゲは、また元のように黄頭の頭にふんわりと乗ると、不思議そうに星型の目をパチパチさせた。
「でも、さっきのお兄さん達、なんでペンギンなのに海に行かないのかな?きかしらさん、教えてあげないの?」
「クラゲくん、君は賢いな」
黄頭はククッとニヒルに笑った。
「そうだな。……でも、ペンギンには、自ら道を切り開かなくてはならないこともあるんだ」
黄頭達から別れた後も、分堀戸兄妹は、そのまま腹撫でを続けている。自由時間は、あと残りわずかだ。あと10分……その時、二人の頭にペンペンとした素敵なアイディアがひらめいた。
「……!」
「……!」
兄妹は、顔を見合わせると力を振り絞り、工場へとペンペンと足音高く引き返した。そして、工場のドアを開くと、兄妹は、働いているフンボルト一族に力強く告げた。
「みんな、フンボルト一揆をしよう!」
(つづく)

浅羽容子作「白黒スイマーズ」第4章 ヒゲの小石チェーン店(3)、いかがでしたでしょうか?
困った時にはどうすればいいのでしょう……そうか、腹を撫でればいいんだ!
今回も名言を吐く黄頭ボブ尾さん、かっこいいですね〜。そして分堀戸兄妹が腹を撫でてペンペン思いついたナイスアイディア「フンボルト一揆」の行方やいかに!?
ご感想・作者への激励のメッセージをこちらからお待ちしております。次回もどうぞお楽しみに。
※ホテル暴風雨にはたくさんの連載があります。小説・エッセイ・詩・映画評など。ぜひ一度ご覧ください。<連載のご案内>

