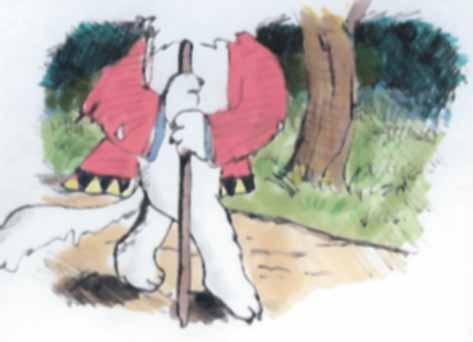
革命軍のリーダー、ニャ・ケバラは独房に入れられている王を見て、その変わり果てた姿を見て驚いた。
ニャ・ケバラは、食べ物の腐敗臭が漂う王の独房に足を踏み入れた。
王はほとんど視力をなくした白く濁った目で、ケバラを睨みつけて言った。
「・・・・この裏切り者め!!」
「王よ、いや元王だった猫よ。裏切り者はあなたです。
あなたは全ての猫の平等と幸せを約束したのに、我々混血種の猫はけっきょくの所、差別され、社会の底辺へと押しやられた。
あなたの臣下達は我々を迫害し、時によっては殺した。
それを、あなたは知っていながら、放置していました。違いますか?」
「・・・・・・・・・・・・」
「しかし、実はというと私はあなたを尊敬していたのです。あなたは猫の尊厳と自由のために戦っていたのでは?
あの頃のあなたは、私の何よりの憧れだったのです。
・・・・・そう、あなたが処刑を免れているのは、私の慈悲によるものです。
ここにいると、あなたはいずれは私の部下に殺されるでしょう。
なので、あなたをここから遠く離れた安全な場所へと移送します。
そこで、余生を静かに過ごしてもらいましょう。それでは、さようなら王よ・・・」
ニャ・ケバラはそう言い残し、王の独房を出た。
翌日の明朝、ニャ・ケバラの命をうけた猫達が王を独房から出し、革命軍の猫達に気付かれぬよう、
王を馬車に乗せた。
馬車は朝日が差し始めた道を、西に向かい走り始めた。
しばらくすると、馬車に乗っていた一匹の猫が言った。
「ここで馬車を止めよ。王には、ここから歩いて移送先へと向かってもらおう」
その猫は独房の看守だった。
三毛猫の看守は、特に王を憎んでいたので、生きて王を町から出す気は、毛頭なかった。
他の猫達は不審そうに顔を見合わせたが、その看守の言う通りにする事にした。
王は馬車から出され、縄に繋がれ、馬車の後ろから歩かされた。
何マイルも歩かされただろうか、王は力尽きバタリと倒れ、そして動かなくなった。
馬車の猫達は倒れた王を見て言った。
「どうする?死んでしまったようだぞ・・・・」
「ふん。本部には途中で王は死んでしまった、と報告しておけ。さあ、帰るぞ」
「遺体はほうっておくのか?」
「ほっておけ。そのうちカラスにでも食われるだろう・・・」
そして馬車は踵を返し、猫の町へと帰っていった。
夜になり、動かなくなった王の顔に夜露があたった。
王は息を吹き返し、あたりを見渡した。
「・・・・あいつらめ、ワシが死んだと思い込んだのだな」
王は痛む身体をいたわりながら、ゆっくりと立ち上がった。
「ケバラめ、見ておれよ。町に戻り、残った仲間を探し出し、必ずやおまえを倒す!」
王は杖になるような棒を見つけ、それで身体を支えながら町へと向かった。
王はすっかりと弱っていたので、町にたどり着くには3日もかかってしまった。
町の入り口に立ち、町を見ると革命軍の旗が至る所になびいていた。
町はもう完全に革命軍の支配下に置かれていたが、王は勇気を振り絞り、町に入っていった。
しかし町に入った王を見ても、猫達は誰も彼の事を王だとは気がつかなかった。
あんなに立派だった白い毛並みは、すっかりとボロボロになり、目は白く濁り、自慢だった牙も抜けていた。
杖をついて歩く彼の姿は、誰の目にも年老いた物乞いの猫としか映らなかった。
王はもう何日も何も口にしていなかった。
王はわずかに残った力を振り絞りながら歩いたが、町の猫達は、誰も彼の事を気にも止めなかった。
仲間も見つからないし、哀れな猫に施しなんかしようとする者もいなかった。
王はフラフラと町を彷徨い、町行く猫を見た。
ある猫は、威勢よく未来を夢みながら歩き、そして、年老いた王の事なんか目に入らないかのように闊歩する猫のカップル達。
今まで気にも止めていなかったのだ、町には哀れな猫達も多くいた。
「なんたる事だ!これがワシが築いてきた王国なのか?」
王は町が見渡せる丘に登り、そこで再び倒れこんだ。
「ワシももはやこれまでか・・・・」
王は覚悟を決めた。
王は死が訪れるのを待ったが、何か気配がするのに気がつき、そちらを見ると人間がいた。
それは年をとった人間だった。
猫の王と人間の目が合い、王は人間に殺される事を覚悟した。
人間は倒れこんだ王の側まで近づくと、魚の生肉を差し出し言った。
「猫の王よ、さっきこれを市場で手に入れた。食べなさるがよい」
「・・・・!人間よ、なぜワシの事を王だと分かったのか?」
「分かるとも。われら人間の文明はおまえに滅ぼされたのだからな。忘れようもない」
「だとすれば、ワシが憎いだろう!」
「確かに恨んでいる者もいる。しかし恨んでどうなる?とにかく食べなされ」
王は人間から魚の生肉を受け取り、それを一口で平らげた。
もう生肉なんか食べなくなって何年も経っていたが、王が食べたその生肉は何よりも美味だった。
王は舌なめずりをしながら言った。
「もうないのかね?」
「それしかないのだよ。それは私の孫に持ってかえるはずだったのだ」
「人間よ、礼を言おう、しかしどうやらワシはもうダメのようだ・・・。町に戻ってもいずれワシは殺されるだけじゃろう。・・・・それに、ワシはもう疲れた」
王は、横になり目をつぶった。
やがて、王は寒さで身体を震わせはじめた。
「寒いのかね?」
人間は王に聞いた。
「ああ」
「猫の王よ、ワシの膝の上で眠りなされ」
それを聞いた王は驚き、人間に言った。
「ワシが?人間の膝の上で?なぜじゃね?」
「覚えておらんのかね?元々あなたがた猫は人間の膝の上で眠っていたのだよ。いいから、私の膝に乗りなさい」
王は恐る恐ると人間の膝に乗り、身体を丸めた。
そこは、とても暖かくて、何か懐かしい感じがした。
少し寒さが和らいだ王は人間に聞いた。
「ひとつ聞いていいかね?あなたがた人間は100年も生きるという。
・・・・しかしワシら猫はどんなに長く生きても20年だ。
・・・・短い!あまりにも短い・・・・。
本当に生きる意味を見出すには、短かすぎるのじゃよ。
どうじゃね?人間は100年も生きれば、少しは生きてる事に満足できるかね?」
人間は星空を見上げ、しばらく考え込み、そして王をやさしく撫ではじめた。
そして言った。
「もう、そんな事を考えるのはよしなさい。あなたは精一杯、生きた」
気分も落ち着き、人間に撫でられ気持ちがよくなった王は、やがてゴロゴロと音をたてはじめた。
王はもう猫の王である事を止め、人間の膝の上でゴロゴロと音をたてる、ただの猫になっていた。
猫は人間に言った。
「人間よ、ワシを許してくれ。ワシは間違っておった・・・・」
「許すとも。私の膝の上では、おまえは王ではなく、ただの愛おしい猫にすぎんのだから」
猫は、もう何も考えなかった。
暖かい人間の膝の上で、ただ人間に撫でられるままでいた。
猫の喉から聞こえるゴロゴロとした音は、少しづつゆっくりになり、やがて音がしなくなった。
猫の王は安らかな気持ちで、その生涯を終えたのだった。
人間は、息を引き取った猫を町が見渡せる丘の上に埋葬した。
木で墓標を作り、墓標にはこのように刻んだ。
「猫の王さま ここに眠る 17年AC」
人間は、ゆっくりと立ち上がり、丘の下に見える、猫の町の喧騒を見渡し、そして家族が待つ森の中へと帰っていった。
――――完
☆ ☆ ☆ ☆
※ホテル暴風雨の記事へのご意見ご感想をお待ちしております。こちらから。