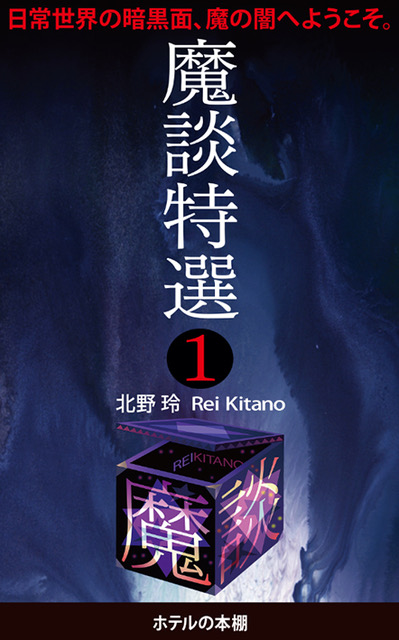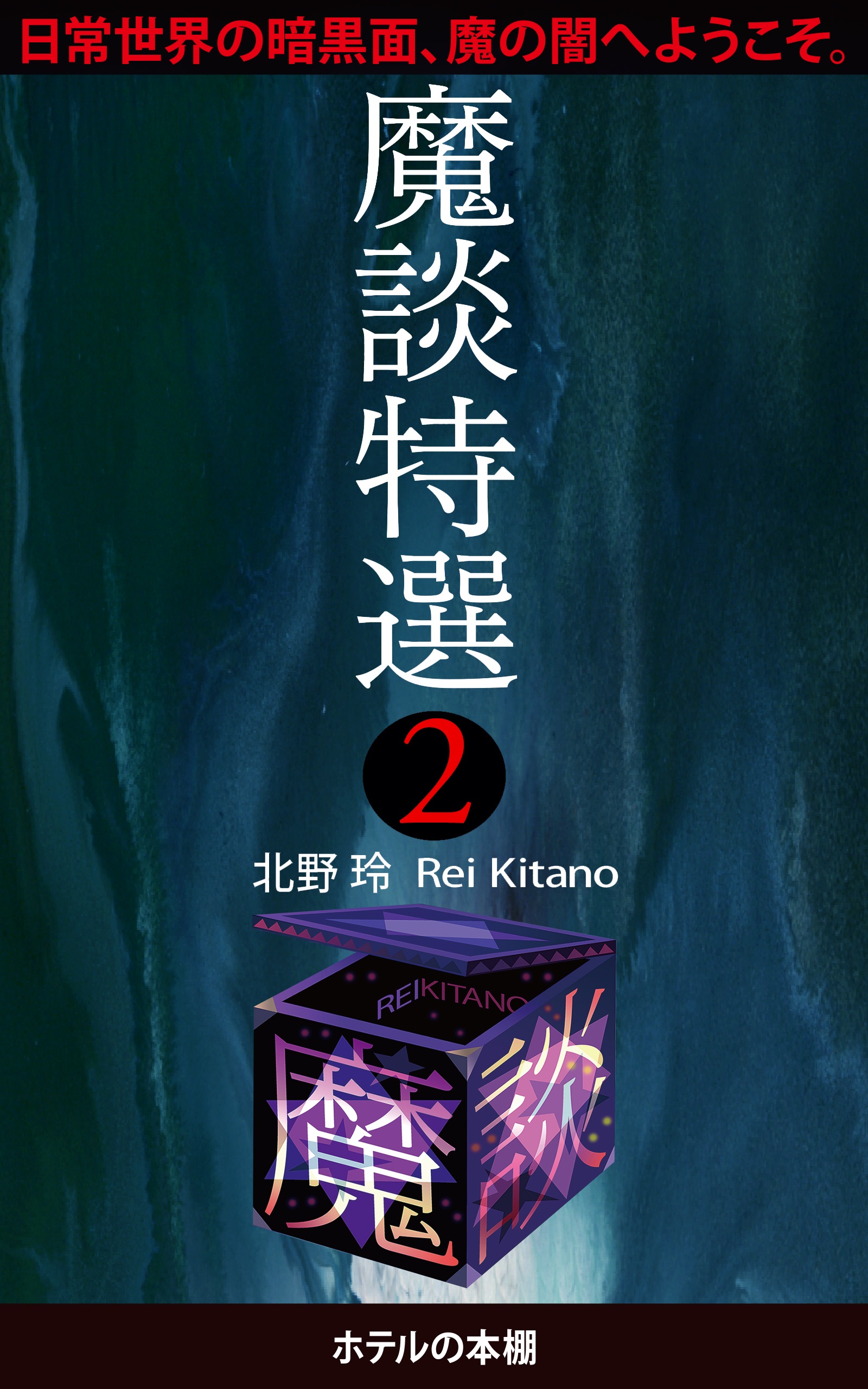【 叉手/しゃしゅ 】
ふとタイトルを見て気がついたのだが(今ごろかよ)、このところの魔談は「延暦寺魔談」あるいは「坐禅魔談」と化しており、映画「魔界転生」とは遠く遠く離れてしまっている。そもそもなんでこんな話をしているのか。冒頭で少々の言い訳(笑)をしたい。
「魔界転生」で伊賀者が登場した。「伊賀を壊滅させたのは甲賀ではなく信長」という話から「四面楚歌の信長は、忍者とも戦った。宗教者とも戦った」という話となり、「比叡山焼き討ち」の話となった。そこから延暦寺の話となり、「延暦寺と言えば、私は8歳の時に10日間、そこにぶちこまれた」という話になった。
最終的には(強制ではなく)私は自分の意思で行ったのだから、「ぶちこまれた」という表現は不適切かもしれない。しかし当時の私は延暦寺がいかなるお寺なのか全然知らず、また興味もなかった。京都には神社仏閣など山ほどある。そうした環境で延暦寺が特別のお寺であるという認識は全くなく、「叡山にある大きなお寺」「山のお寺なのでお坊さんたちが修行している」程度の認識で10日間も滞在することになったのだ。年齢といい、動機といい、延暦寺で修行中の若き僧侶たちにとっては誠に目障りな存在だったかもしれない。
そうした立場をかずくんはちゃんと理解し、受け入れていた。彼はおそらくその時点で「延暦寺10日間」は2回目とか3回目だったのだろう。すでに経験済みであり、ある程度の「正しい過ごし方」みたいなものを体得していたのだろう。しかし私は違った。オブザーバーとしか言いようがないような立場だったが、そもそもオブザーブする対象の知識も興味もなかった。延暦寺はじまって以来の「最年少無知門外漢」だったに違いない。山門で尻を蹴飛ばされて外に放り出されても仕方がないような少年だったのだ。

さて座禅談のつづき。
かずくんは「結跏趺坐/けっかふざ」の次に、手の組みかたを教えようとした。
「……これは叉手(しゃしゅ)いうてな」
私は驚いた。座布団の敷きかた、足の組みかた、背筋の伸ばしかた、これでなんとか座禅に入ることができるのかと思いきや、手の組みかたまで決まっているというのだ。
「なにからなにまで、そういうのがいちいち決まってるんかいな」と思った。8歳の少年にその理解はむずかしかった。まだ到着したばかりだったが、早くも逃げ出したくなった。大広間は誠に気持ちの良い広々とした空間だったが、走り回ることもできず、ゴロンと寝転ぶこともできず、石のようにじっと座っていろというのだ。全く理解できなかった。
しかしかずくんに文句を言うこともできない。彼はお坊さんの言いつけをきちんと守ろうとしているだけなのだ。学校の先生に対してさえ、これほどその言いつけを懸命に守ろうとしている少年を見たことがなかった。正直なところ「変なヤツ」と思う気持ちがあり、また一種の哀れみに近い気持ちを、私はかずくんに対して抱いていた。「そうまでしてお坊さんになりたいか」と思ったり「お坊さんになるためにはそこまでせんとあかんのか」と思ったり。
「左手の親指をな、右手で軽く握るんや」
私はそうした。
「左手の他の指でな、右手を包むようにするのや」
なんだそんなことか、と思いつつ私はそうした。
「お腹にくっつけるようにするのや」
この手の組み方を叉手(しゃしゅ)というらしい。
まあなんとか座禅らしい体制になった。このままじっと1時間も座ってろというのか。
心中は不満やらなんやらでザワザワと揺れた。途中でトイレに行きたくなったらどうするのか?
「目は半眼、いうてな」
もう本当に驚いた。まだあると言うのか。
「目は閉じるんやない。うっすらと開いてな、目の前の畳をじっと見るんや」
畳なんか見てどないすんねん。そう思ったが黙っていた。ここは(余計なことは言わず)黙って従った方がいいだろうという、半ば本能的な判断だった。
「目を閉じてしまうとな、かえってあかん」
なにがあかんのか。そう思ったが黙っていた。
「うっすらと目はあいてるんやけど、じつはなにも見てへん、そういうのがええのや」
いま目の前の畳をじっと見ろというたやんか。そう思ったが黙っていた。
【 つづく 】