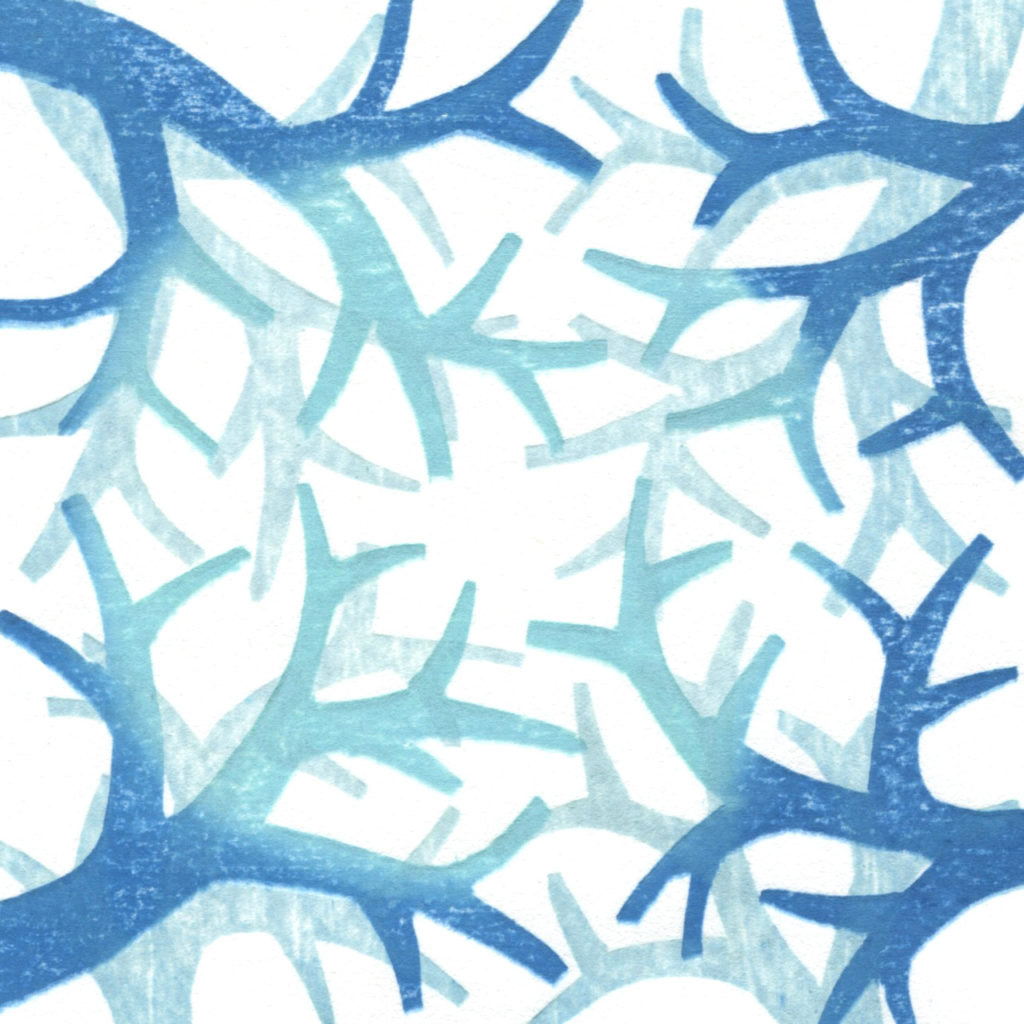
挿絵:服部奈々子
十六の季節の十五番目、「青い弦」が過ぎ去ろうとしていた。
重力の方向がゆらゆらと変化する日々は、もうすぐ終わる。
あたたかい朝、メメイはお気に入りの枝につかまって、甘いペウをしゃぶっていた。
オトナたちは重力酔いをきらって、次の季節「とがりつむじ」まではコブの中で溶けている。おかげでコドモは、オトナの面倒をみなくてすむ。
「おーい!」
声のするほうを見ると、ニニエがひらひらと枝を伝ってやって来るところだった。
うっすらと青い空間に、いくつもの軸索から広がった半透明の枝が重なり合っている。コドモは体が軽いから、重力が揺れ動いてもそんなに気にならない。
ニニエはメメイのそばまで来ると、息を弾ませて手を差し出した。
小さな手のひらに、灰色の粉っぽいかたまりが乗っていた。
「なあにこれ?」
メメイはペウの甘い匂いが漏れないように、あまり口を開けないで喋った。だってこれ、最後の一個なんだもん。
でも、ニニエはそんなことは気にならないようだ。すごく興奮して、灰色のかたまりを乗せた手を、もっとメメイに近づけた。
「枝の先に引っかかってたの。イキモノじゃないかな? 動くし、あったかいし!」
「へーえ?」
メメイはおそるおそる、そのハイイロを見つめた。
粉がついているように見えた表面はザラザラした皮のようで、ニニエの手に接している部分が、ゆっくりと伸びたり縮んだりしている。
上の方の表面を、指先でちょん、とつつくと、その部分がキュッと凹んだ。
メメイはひゃっと叫んで、枝から離れそうになった。とっさに触角の先を枝に巻きつけたので、平気だったけれど。
「でも、あったかくて動くだけじゃ、イキモノとは言えないって聞いたことあるよ」メメイは、いつかオトナに聞いた知識を披露した。「ココロを持ってなきゃ」
「ココロってなあに?」ニニエは聞き返した。
「うーんとね、例えばこの枝からあの枝に移る前に、まず『移ろう』って思うでしょ。そういうふうに思うのがココロだよ」
「うん? わたしがそう思ったとしたら、思うのはわたしでしょ? ココロが思うんじゃないよ」
「だから、それがニニエがココロを持っている証拠なんだよ。ココロがなかったら、思うこともできないんだよ」
メメイは自分でもよくわからなくなって、だけどなんとか説明したくて、ゆらゆら動く枝につかまりながら、ニニエの目を見て熱心に話した。
それが起こったのは、一瞬のできごとだった。
ハイイロが、ニニエの手のひらで平たくなったと思うと、体膜の上を網のように伸びて、腕から顔の片側までぺったりと貼りついた。
ニニエの体から力が抜け、揺れ動く重力につられて、メメイにしなだれかかった。
「どうしたの!」
メメイは驚いて、ニニエの体をゆすぶった。
がくん! と、ニニエの顔が上向いた。
うつろな目。
口が動いて
「ソラ」
と言った。
ニニエのココロから出た言葉じゃない。
網目のようにニニエの体膜を侵蝕したハイイロが、ニニエの口で言ったのだ。
ソラ。
メメイが、あまりにも広すぎるようなその音の響きに不安になっていると、
ばしゃっ!
ニニエの背中から、ハイイロが噴き出した。
それは広がってオトナの翅のような形になったが、大きさははるかに大きかった。
ぶわっと羽ばたいて、ニニエが枝から離れる。
メメイはとっさにニニエにしがみついた。脚と触覚で、枝をつかむ。
翅のないコドモが枝を離してしまったら、重力の方へ行ってしまう。重力は軸索の森の外にある。そこは何もつかまるもののない、恐ろしい世界だ。
――――つづく
(by 芳納珪)
☆ ☆ ☆ ☆
※ホテル暴風雨にはたくさんの連載があります。小説・エッセイ・漫画・映画評など。ぜひ一度ご覧ください。<連載のご案内> <公式 Twitter>