
優れた日韓合作「アジアの天使」「ノーボーイズ、ノークライ」
今年劇場で見た邦画の中で一番好きという作品が現れた。以前紹介した「茜色に焼かれる」の石井裕也脚本・監督の日韓合作「アジアの天使」だ。普通の日...
ご縁で出会った素敵な映画たち

今年劇場で見た邦画の中で一番好きという作品が現れた。以前紹介した「茜色に焼かれる」の石井裕也脚本・監督の日韓合作「アジアの天使」だ。普通の日...

それ程話題にならなくても、このコロナ禍でも様々な国から優れた映画が着実にやって来る。スポーツにも敬意を表するが(現在のオリンピックは別だ)、...

この稿がアップされる3日後、東京オリンピックが開催だ。57年前の昭和39年、小4の時、田舎で五輪の興奮を経験した自分は、以来、ずっと五輪大好...
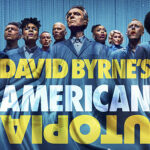
まず最初の20分ほどが中々面白い。ロマンスグレーのバーンは、人間の脳みその模型を手にもって、脳が一番いろいろなことを純粋に吸収するのは幼い時で、段々に、汚されていく、といったことを、真面目な顔をして、科学者のように哲学者のように歌っていく。

一部の映画ファンの間で賛否分かれて話題になっているのが日本映画の「茜色に焼かれる」だ。 主演の尾野真千子が熱演しているという情報だけで見た...
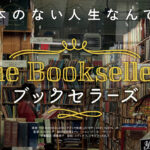
まだ、「断捨離」を実行する年齢ではないが、60代後半、年々増える本には困っている。先日、「一生残すか残さないか」の基準で選んで、かなりの本を...

傑作「チルソクの夏」を撮った故佐々部清監督の遺作が公開されている。亡くなったのは昨年の秋頃かと思っていたが、調べると、昨年の3月末であった。...

1977年の作品「竹山ひとり旅」だ。脚本・監督の新藤兼人は100歳まで生き、生涯にわたって映画を撮り続けた映画人で、「愛妻物語」「裸の島」など秀作が多い、尊敬する映画人である。初めて見たのだが、この映画は誠に素晴らしかった。

初めてブータン映画を観た。「ブータン 山の学校」は僻地の小学校で教える若い先生と村人の交流を描く映画だが、とても面白いし表現は映画的に豊かで...
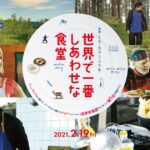
コロナ下では旅行に行けず、映画で異国の風景が見たくなる。そんな単純な理由で、あまり期待しないで見に行ったフィンランド映画「世界で一番しあわせ...