翌朝——といっても下層世界に朝日は射さないので、暗闇の中を——我々は出発した。
地図と高度計と方位磁石で現在位置を推定し、構造躯体の鉄骨がむき出しになっている中を、なんとか階段までたどり着いた。途中、巨大ミミズと羽アリの群れに襲われたが、どちらも私が万能銃で駆除した。
先頭を行くマスチフのサムは、安定したペースでそのがっしりした体を運び、次に続く鯖猫のジョーは、長い尻尾を左右に振りながらはずむような足取りで歩いている。しんがりをつとめるのは私だ。
音楽アカデミーを追放された銀猫人の作曲家にして音楽史研究者、アレキセイ・トトノフスキイ(父)は、古代の記録媒体「四角石」の再生装置がある場所の候補を、三箇所あげていた。その候補地を、上の方から順に確かめるということで、我々の方針は一致した。
現在、考古省が発掘調査を進めているのは70階付近までで、それより下になると地図の記述が極端に曖昧になる。ここから先はトトノフスキイ氏の研究ノートの記述が頼りだ。
トトノフスキイ氏は銀猫人の言い伝えを丹念に収集し、銀猫人の集会堂があった場所を推定していた。そこに四角石の再生装置があるはずだというのだ。その候補地は、上から50階、25階、そして、1階(?)——と、ノートにはあった。
50階は空振りだった。候補地の手前に大規模な崩落箇所があり、近づくことができなくなっていたのだ。サムが匂いを嗅いで調べたが、アレキセイ(息子)が来た形跡はないとのことだった。
我々はまた階段に戻った。
下るにつれ、だんだん空気が湿り気を帯びてきた。そして、埃っぽさと甘さの混じったような匂いがかすかに漂ってきた。
「マスクが必要かな」
私は先頭のサムにたずねた。
立体都市の下層がなぜ打ち捨てられたのか、はっきりとはわかっていないが、戦争で汚染されたためという説が今のところ有力である。
そのため、装備の中に防毒マスクも入れてあった。
サムが振り向いて答えた。
「たしかに妙な匂いはするが、危険はなさそうだ」
そのまま下って行くと、なんとなくあたりがぼんやりと光っていることに気づいた。
目をこらすと、階段のステップの奥や壁の下にキノコのようなものが生えている。それらが、青っぽく発光しているのだ。どうやら匂いの元は、このキノコらしい。
進むにつれてキノコは増え続け、25階に着く頃には、ヘッドランプが必要ないほどの明るさになっていた。
フロアに出ると、これまで見てきたガレキだらけの世界からは想像もつかない光景が広がっていた。
床といわず天井といわず、大小さまざまのいろんな形をしたキノコがびっしりと生えていて、全体がぼうっと発光し、そのおかげであたりは昼間のような明るさになっているのだ。
私はその場に立ち尽くし、しばらく幻想的な風景を眺めた。
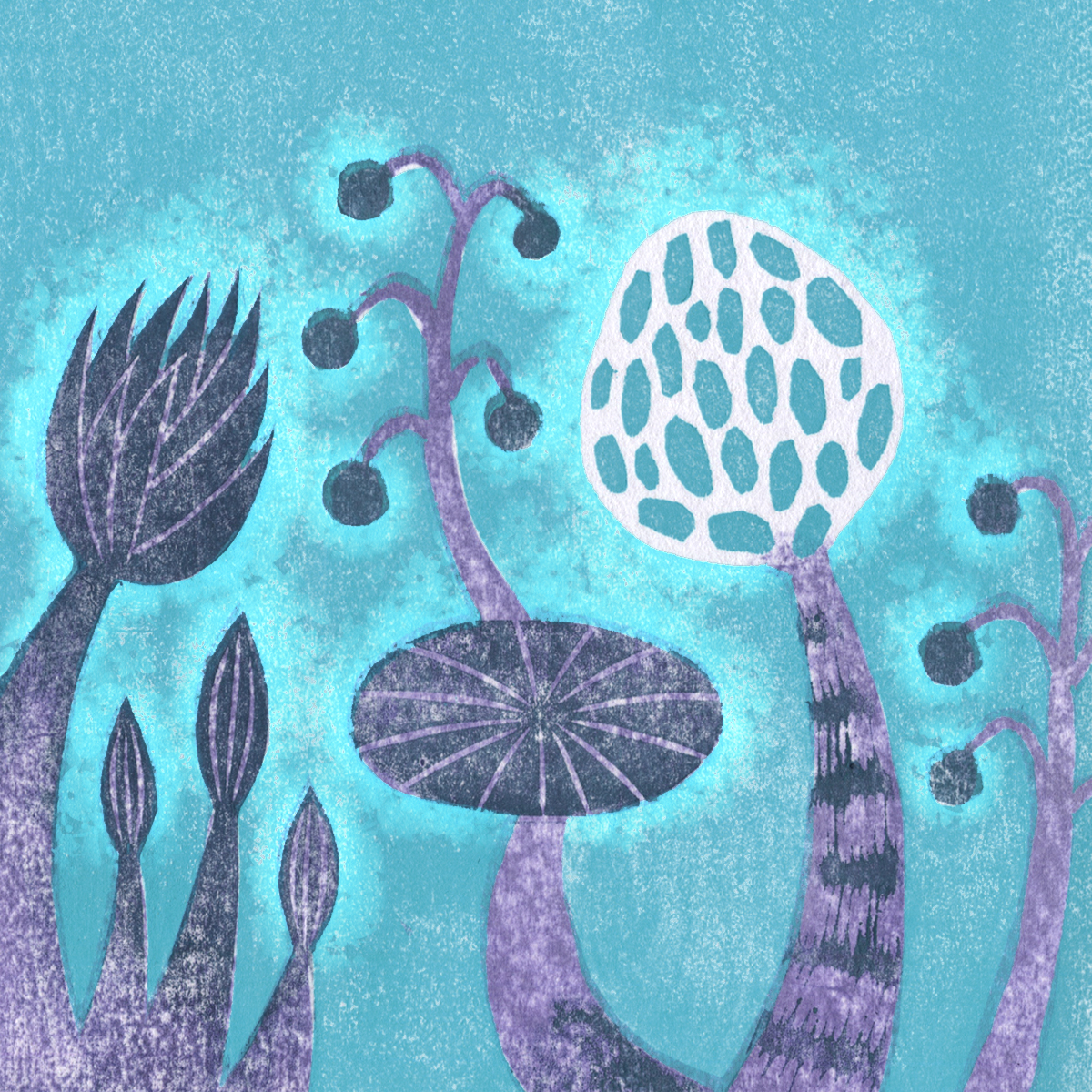
挿絵:服部奈々子
正面に目を戻すと、キノコの群落の向こうに見慣れたものが見えた。
あれは、事務所に残してきたサボテンだ。
私の胸を郷愁がしめつけた。レッドイーグル探偵社に所狭しと並べてあるサボテンたちは、家族同様の存在である。
いない間の世話は向かいのおかみさんに頼んであるし、これまでも仕事で何日か彼らの元を離れることは幾度もあったのだから、心配はないはずだ。
それなのに、いま実際に姿を見て、胸がざわめいてどうしようもなくなった。
私はふらふらと歩み出た。
キノコをかき分けて行くと、たしかにそれは、一番初めに事務所にやってきた「金鯱(きんしゃち)」だった。
「ああ、こんなに立派になって」
一日会っていないだけなのに、彼女は一回りも大きくなって肌のつやが増し、幸せそうにふくふくとしていた。隣には、古株二番手の「弁慶(べんけい)」がいる。こちらも、いつのまにか私の背を追い越し、誇らしげにすっくと立っている。
気がつくと、そこらじゅうサボテンだらけになっていた。
ほとんどは見知らぬサボテンだが、ところどころに、私の家族のサボテンが混ざっている。そして彼らはみな、前に見たときよりも立派に成長しているのだった。
私の心は歓喜に満たされ、夢中でみんなの姿を探し回った。
いきなり、パシッ! と背中に衝撃があった。攻撃というほど強くはない。こちらを正気づかせるような叩き方だ。
「マスクを持ってますか? 持っていたらつけてください!」
マスク……? そうだ、さっきマスクをつけなきゃと思ったんだっけ……。
自分でももどかしいくらいにのろのろとマスクを出して、なんとか装着した。
頭が少しはっきりする。
私は後ろを向いて、声の主を見た。
(第十九話へ続く)
☆ ☆ ☆ ☆