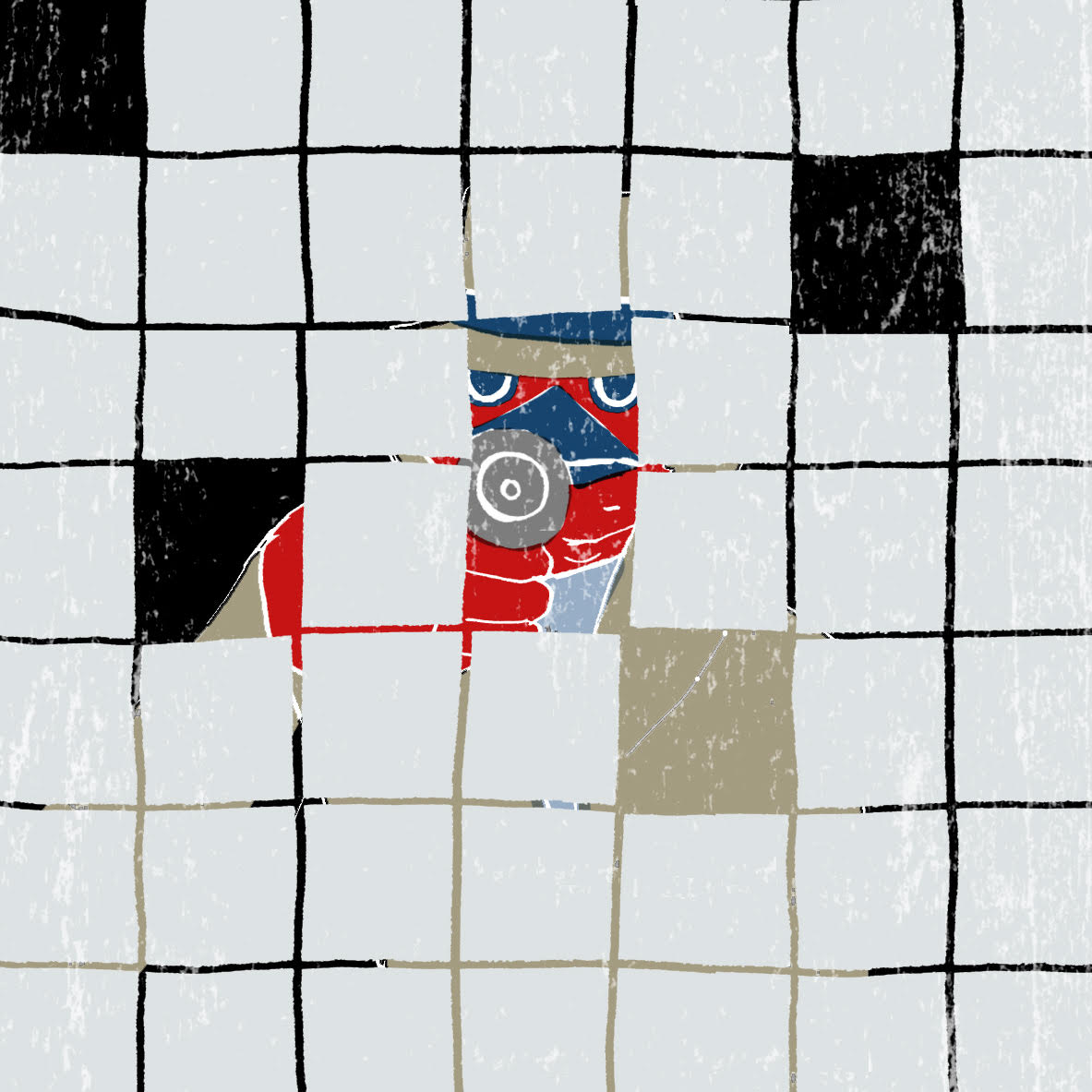
挿絵:服部奈々子
立体都市最古の家系のひとつ、フェアードマン家の現在の当主と200年前の当主が、対峙している。
町並みを形成する構造ユニットの屋上に立ったレディMは、背中に背負った筒状の装置を前に回すと、それを両手で抱えて、ユニットの下にいるフェアードマン卿に向けた。
どうやら一種の飛び道具らしいが、一人で持つには大きすぎるようだ。
私は万能銃〈ムラマサ〉を構えているので、真横にいるレディMをちゃんと見ることができない。撃ってもフェアードマン卿はやすやすと避けてしまうとわかっていても、本能的に銃を下ろすことができなかった。
ノルアモイにどっしりとまたがったフェアードマン卿が口を開いた。
「我が一族の裔(すえ)に会えたことは望外の喜びである。挨拶のかわりに武器を向けられるとは思わなかったが」
「祖先に対しては敬意を払いますが、過去から来た亡霊を敬うつもりはありません」
レディMの声は苦しそうだ。装置が重いのだろう。
「たとえ亡霊であっても、生体を破壊することは犯罪になる。余が生物学的クローンか、それともヒューマノイドであるかをどうやって見分けるのだ」
「私のメイドのヒューマノイドには、あなたと同じ素子が使われています。彼が衛星を通じて、あなたが海底で起動するのを確認しました。あなたは生体ではありません。チタンとシリコンで作られた人造体です」
レディMが言った「彼」とは、エムニのことだろう。
フェアードマン卿は笑ったようだった。
「さすがである。その上、時間展開立体に入り込むことができたとは」
それは私も疑問に思っていたことだった。レディMはこの終わりのない世界の外から来たのだ。一体どうやって?
そのとき、装置を構えたレディMの体が、がくんと沈んだ。
私は反射的に、万能銃を片手に持ち替え、空いた手で彼女を支えた。横目で見ると、レディMの顔色は真っ青で、冷や汗が流れている。
「具合が悪いのですか?」
「私のことはご心配なさらないで。それよりも、あのヒューマノイド・Fを倒すのに、どうかお力をお貸しください。一度しか撃てませんから、しっかり支えていてください」
レディMは、苦しい息の下から訴えた。その体から、並々ならぬ緊張と覚悟が伝わって来る。
私は万能銃をホルスターに収め、両手で彼女を支えた。
「膝をついた方が安定します。装置は肩の上に乗せて。そうです……」
ノルアモイ軍団がざわりと動いた。と思うと、我々がいるユニットの壁を垂直に駆け上がって来た。フェアードマン卿は下に残っている。
迫り来るノルアモイの群れに、恐怖で気が遠くなりそうだった。そちらを見ないように、ただ一点、フェアードマン卿の顔をまっすぐに見た。
レディMの装置が低い唸りをあげ、オレンジ色の光線が発射された。光線はノルアモイの群れを包み込むように拡散し、青い炎と混ざり合って強烈な白い光になった。
目が眩んで何も見えなくなる。
パタパタパタパタ……
遠くから、何かを叩くような連続した音が聞こえた。その音はたちまち近づいて来た。
私は何も見えないまま、レディMの体を庇った。
パタパタパタパタ……
音は四方八方から、雨のように押し寄せる。
これは、空間が折りたたまれる音ではないか?
パタパタパタパタ……
奥行きもわからない白い空間の中、音は今や雷雨のように轟いている。
レディMの体から伝わる体温だけが、音以外に感じられる世界の実感だった。
ずいぶん長いことその状態が続いたように思うが、やがて音は少しずつまばらになり、まさに雨が止むように止んだ。
目の前の白い空間に、小さな正方形の穴があいた。少したって、離れた位置に同じように穴が空いた。さらに離れた位置にもう一つ。
四角い穴はあちこちにあき、白い壁は見る間に虫食いだらけになった。
現れた景色は、夜のロ号歩廊だった。
レディMを見ると、ぐったりと横たわっている。
彼女の具合を確かめようとした時、また、あの心臓を鷲掴みにされるような恐怖が襲ってきた。
白い壁がすっかり消え去った静かな夜空を背景に、燃え盛る巨大な馬が立っているのが見えたのだ。
そのノルアモイは後ろ足で立ち、頭をのけ反らせ、声のない勝鬨を上げた。
見よ、ノルアモイが駆け下りてくる。
私は動けなくなった。
群れでいた時よりも一頭だけの方が、かえって姿が強調され、目に焼き付く。
〈ムラマサ〉はどこだ?
冷たくなった頭の裏側で、ぼんやりと思考する。
青い炎が迫ってくる。
私は目を閉じた。
たちまち思考がはっきりする。
ホルスターから〈ムラマサ〉を抜き取りざま、見えないノルアモイに向けて発射ボタンを押した。
複雑なメカニックの中枢が破壊される手応え。続いて、硬い重量物が配管にぶつかりながら落ちていく音。
その音がはるか下へ遠ざかり、完全に聞こえなくなったとき、私は目を開けた。
ヒューマノイド・エムニが、目の前に立っていた。メイド服の裾が、ふわりと風に揺れる。彼/彼女は、自分よりも背の高いレディMを両腕にしっかりと抱えていた。
エムニはにっこりと微笑んだ。
「ありがとう。レディMを守ってくれて」
「彼女は、大丈夫なのか」
横抱きにされたレディMは、髪こそ乱れているものの、目立った異常はなさそうに見える。
エムニは大きく頷いた。
「単なる過労だよ。寝ないで『対ヒューマノイド・F砲』を作っていたからね」
その体が、スッと空中に浮き上がった。
エムニの頭上で、二台のドローンが静かにホバリングしていた。レディMを抱えたエムニは、そこから吊り下がっているのだった。
「大変申し訳ありませんが、お先に失礼いたします。後日あらためてご連絡いたします」
エムニはそう言って目礼すると、レディMとともにスーッと上昇し、夜空に吸い込まれていった。
最後の言葉はレディMの口調だったと気がついたのは、彼らの姿が完全に見えなくなってからだった。
私は、その場にぼう然と立ちすくんだ。
まるで、夢を見ていたような気分だった。
(第二十三話へ続く)
(by 芳納珪)