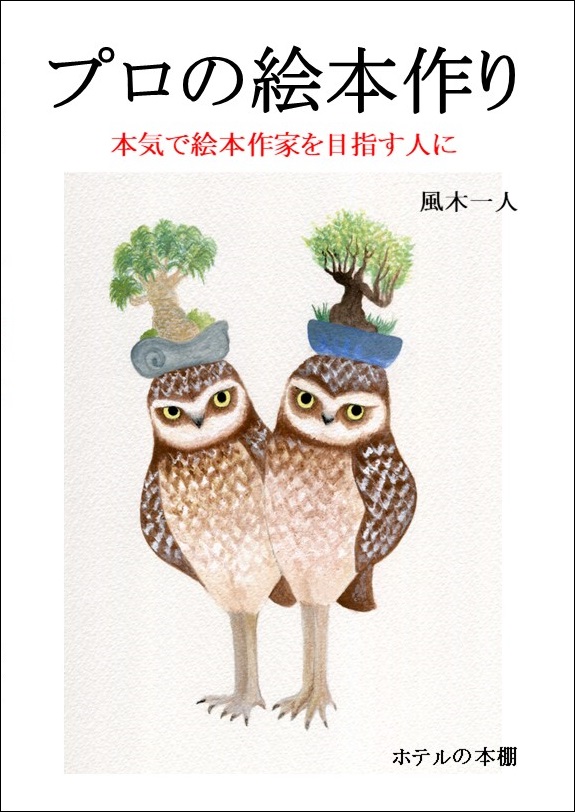奇跡のラブストーリー
『ぼくの鳥あげる』はラブストーリーである。しかしとても珍しいラブストーリーだ。
半分まで読んでもまだまったくラブストーリーらしくない。後半に入ってようやく運命のふたりの物語になってくる。
こんな話はめったにない。しかし佐野洋子ファンなら誰でも似た話を知っているだろう。
『100万回生きたねこ』だ。
2つの作品はともに前半と後半に分かれる構造を持っている。
『100万回生きたねこ』の前半は「ねこがいろんな飼い主のあいだを渡っていく」、『ぼくの鳥あげる』の前半は、「1枚の切手がいろんな人の手を渡っていく」だ。
そして後半はどちらも奇跡のような純愛を描きだす。
『100万回生きたねこ』は1977年に、『ぼくの鳥あげる』は1984年に発表された。この2作は変奏曲といっていいだろう。佐野洋子さんは7年たってもう一度同じテーマに挑んだのだ。
『ぼくの鳥あげる』の1年前、1983年刊行のエッセイ『アカシア・からたち・麦畑』で佐野洋子さんは画学生時代のことを書いている。
18歳で実家のある清水をはなれた佐野洋子さんは東京で暮らし始める。はじめ御茶ノ水の美術予備校に、それから当時吉祥寺にあった武蔵野美術大学に通う。
そこにはのちの佐野さんの自信に満ちた姿はない。
初めて入った教室では誰もが自分より上手いように思えて落ち込む。都会になじめず、垢抜けたクラスメートたちに劣等感を覚える。終戦から十数年という時代で、貧しさと、豊かさへの憧れも語られる。
何者にもなれないのではないかという不安、自分だけ場違いであるような疎外感、このようなものはいつの時代も変わらぬ青春の痛みということもできる。
それでもあの佐野洋子さんにこんな初々しい時代があったのかと思うと、やはり一通りでない感慨がある。
『ぼくの鳥あげる』の主人公ふたりは、若き日の佐野さんの分身だろう。
女の子は小さな町を出てひとり都会で暮らし始める。そこに豊かさと幸せがあると信じて。
絵描きの若者はずっと描きためてきた作品で個展をするがまったく売れず「どうせぼくの絵を好きな人なんて誰もいないんだ」と言う。
ふたりとも貧しい。
「すべての偶然がひとつの運命となり」女の子と若者はめぐりあう。
ふたりの幸せを願わずにはいられない。
全国の書店・ネット書店で好評発売中です。ぜひお読みになってください!
(by 風木一人)
※『プロの絵本作り~本気で絵本作家を目指す人に~』が紙書籍になりました。連載に加筆修正の上、印税、原稿料、著作権、出版契約に関する章を追加。amazonで独占販売中です。