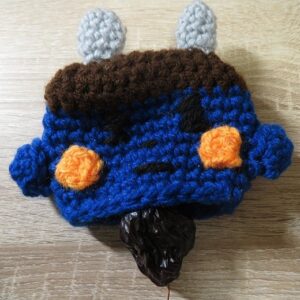
【第十四話】
小田原泉は、あまりに荒唐無稽のようで、どこか合理的なようにも感じるこの推理に、何と返答すればよいか考えあぐねていた。
「うーん……。じゃあ、もしそうだとして、梅木さんは、私に何を相談したいんですか?」
「……実は、さっき、先生に会う前、業者と一緒にその林檎畑のある山林を見に行ってきたんです。ご夫婦にもお会いしました」
「ああ、そうなんですね。ご夫婦は、その廃棄物処理場のこと、ご存知なんですか?」
「初めてお伝えしました」
「何と仰ってました?」
「大変ショックをお受けになっておられました」
「そうでしょうねえ……」
「そうなったら、もうここでは林檎は育てられないね、と」
「困るじゃないですか」
「そうなんです。涙ぐんでおられて……」
「ちょっとそれは、辛いですね。ちなみになんですが、竹林町長は、もちろんこのことをご存知なんですよね?」
「知ってます。ご夫婦にお伝えしたことはまだお話ししてませんが」
「なるほど。竹林さんのご意見は?」
「あの人は、〝林檎畑はそのままにしよう。あのご夫婦が亡くなるまで作ってもらおう〟と言ってます」
「道の駅の予算のことは?」
「そこは考えてないんじゃないかなあ。どうにかなると思ってるんですよ。道の駅って国から補助金も出たりするし、公共の施設なんだから最終的には業者もまけてくれると」
「甘いですね」
「そうなんです」
「なるほどねえ。確かにこれは、メールでは書きづらい内容ですね」
「そうなんです。私もいろいろ想定外過ぎて、どうしたらいいのか困ってしまって……。あの……、もし、先生だったらどうされます? って、訊かれても困りますよね」
「はは。そうですね。うーん。……でも、そうですねえ、私が梅木さんの立場なら、まず、建築費用の見直しをするかなあ? そして、身の丈に合った、予算に収まる範囲でのリノベーションを検討します。今あるのが老朽化してて、建て替えた方が安く済むならそうしますけど、建てて十年以内ならリノベーションで十分だと思います。この際、〝樹の魔術師〟は、きっぱり諦めます。そして、林檎畑のほうはそのままで、業者に委託も譲渡もしません。そもそも彼らの申し出は寄付ではありませんから。受け取りませんね、そんなお金。お金が足りないのなら、その林檎の持つ物語を大いに活用して〝幻の林檎を売る場所を新たに作るため〟とか何とかいって、クラウドファンディングなどを検討します。ふるさと納税の返礼品にするのもいいかもしれません。その林檎が収穫されたら送ると言えば、割と簡単に集められるような気がします。私も、竹林さんに劣らず甘いかもしれませんが……」
「そんな……。でも、クラウドファンディングか……。確かに、その手もありましたね」
「ちなみに、その林檎栽培の後継者はいるんですか?」
「いないと思います」
「だったら、それも含めて土地のことを考えた方がいいんじゃないですか。そんなに貴重で価値のある品種なのなら、ご夫婦がお亡くなりになったら終わり、というわけにはいきませんよね? ご夫婦が動ける間に、町で後継者を育てるんです。ご夫婦には管理人のように、引き続きその土地に住んでいただいて、林檎を作ってもらう。その代わりに、若い人にそのノウハウを伝えてもらう、というのはどうでしょう? それだと問題ありませんよね?」
「ああ、確かに。でも、引き受けてくれるでしょうか? かなりお年ですし……」
「ご夫婦にも生活があるでしょうし、引き受けざるを得ないですよね。既に、法律上、もはや自分の土地ではないのだし……。それに、却って励みになるかもしれませんよ。人は、役割を与えられたほうが生き生きするから。下を育てるって確かに大変だけど、これ以上ないやりがいだと思うんです。生きる希望というか。ご夫婦にとってもいいことなのかもしれません」
「確かに」
「それから……。個人的には、これが一番大事だと思うんですけど、何故、業者がこの話を知っていたかについて、危機管理の面からも、もっと徹底的に検証した方がいいと思います。もしも対立している町があるのなら、なおさらです。まあ、私だって外部の人間ですし、私が聞いたように、他の人も聞けた可能性はありますよね。っていうか、これ、私が聞いて、よかった内容なんですか?」
「先生はいいんです。私のブレーンですから。でも、確かにそうですね。コンプラ意識は低めですからね、この町の人。私も気にはなっていたんですが、どうせ町議の誰かが漏らしたのだろうと思って……。でもそうですね。この件についても、きちんと検討します。いつもすみません。先生とお話してると、頭の中が整理されていく感じがします」
「そんな……。梅木さんの会社には、梅木さんの右腕となるような人はたくさんいるんじゃないですか? 公共政策のコンサル会社でしたよね?」
「おかげさまで、いろいろやらせてもらっているのですが、いかんせん、人出が足りなくて。手が回らないんです。だから、このお話も、本当はお断りしたかったのだけど、旧友からの依頼でそうもいかなくて……。まあ、こんな小さな町の政策支援なんて、私一人でやればいいや、と思っていたんですが、意外にもあまり経験したことがないような問題が山積してまして。先生に頼ってしまって、本当に申し訳ないです。今度、きちんと謝礼をお支払いさせて頂きます。今日のところは、こちらで……」
そう言って、梅木は鞄から白い封筒を取り出し、机上にそっと置いた。封筒の表には綺麗な字で〝お車代〟と記されていた。
「えっ……。こんなの頂けません。私は、ただ勝手なことを話してるだけですから」
「いいえ。受け取ってください。少なくて申し訳ないのですが。次回からは、きちんと謝礼をお支払いさせて頂きます」
「いや、そういうのは、ホントに受け取れないです。最初にもお伝えした通り、仕事として関わってるわけではないのです。本当に、ただの個人的な関心で……。好奇心のようなものなんです。だから、本当に、これは……」
そう言って、小田原泉は、テーブルの上の封筒をぐっと梅木のほうに押し戻した。
梅木は、「いやいや、それでは……」と言って一瞬首を横に振りかけたが、小田原の瞳の中に、強い意志を感じ取り、「わかりました……」と言い、封筒を鞄に戻した。
その姿を見て、小田原泉は、ほっとした表情を浮かべ、続けた。
「あと……、確かにメールでは書きづらい内容だったかもしれませんが、今後、アポイントはメールでお願いできると助かります。詳しい内容を書く必要はありませんので、ご相談があるという旨を送って頂ければ。マンションの他の住人の方に待ち伏せされたりするのも、ちょっとドキドキするので」
「あ、そんなことが。……すみません。これからはそうします」
「今日は、最初に思ったよりも怖い話じゃなくてホッとしました」
「ははは。脅かしすぎましたね。失礼しました。またお願いするかもしれません。その際はどうぞよろしくお願いします」
「その日が来ないことを祈っています」
そんな会話を交わしたたった一週間後に、まさか本当にメールが届くとは思っていなかった。
【第十五話へ続く】
(作:大日向峰歩)
*編集後記* by ホテル暴風雨オーナー雨こと 斎藤雨梟
ごく当たり前のアドバイスをし、謝礼を断固断って、「逃げ帰って」きた小田原泉。しかしやはりそう簡単には逃げられないのか……さて次はどんな相談事が舞い込むやら、まさか梅木浩子の「産廃業者が隣町からの刺客」という邪推が当たっていたとか? 次回をどうぞ、お楽しみに!
作者へのメッセージ、「ホテル暴風雨」へのご意見、ご感想などはこちらのメールフォームにてお待ちしております。