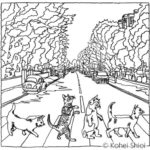
お風呂と塩昆布
あまり広くはないバスルームにはおもちゃの類は出来るだけ持ち込まないようにしているが、胴体が4つに分かれるペンギンのおもちゃと、塩昆布の入っていた容器が息子の今のお気に入りである。お風呂でどうして塩昆布なのかというと、
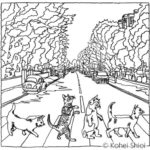
あまり広くはないバスルームにはおもちゃの類は出来るだけ持ち込まないようにしているが、胴体が4つに分かれるペンギンのおもちゃと、塩昆布の入っていた容器が息子の今のお気に入りである。お風呂でどうして塩昆布なのかというと、
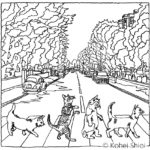
世の中には手づくりのクッキーとそうではないクッキーがあることを知ってしまったのだ。それ以降「手づくりのクッキー食べたい」とよく言っているが、手作りの方がおいしいとは限らないという現実があることも、いつか知ることになるのだろう。
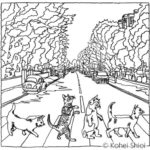
本当は逆なんじゃないか、と思うようにもなってきた。仕事というのは自分の時間や労力を誰かのために費やすことである。その誰かがまずは子どもであることは間違いではないだろう。そんなふうに考えられるようになったのは、つい最近のことである。
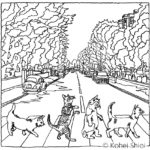
なんでも自分ですると言ってチャレンジし、挫折するとすぐに「父さんがやって」ということになるわけだが、自分が何かしてあげたいという気持ちと、自分にはできないことがまだたくさんあるという現実の中で揺れ動いているようだ。
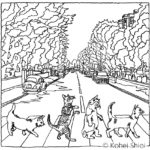
「イヤイヤ期」というのは育児ワードの中では有名だが、息子はイヤイヤと同時になんでも「したい、する!」と言う「するする期」に突入し、さらに自分以外の誰か(たまに人じゃなかったりもする)に「してあげる」といいはじめる「してあげる期」の中にいる。
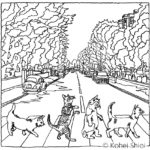
子どもはどうしてか「今かよっ!」というタイミングでおしっこやうんちをするので、どうしてもあたふたしたりイライラしたりしてしまうことも多いが、そこでの養育者の振る舞いが子どものトイレに対するイメージに大きく影響を与えることは間違いないだろう。
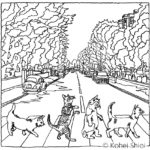
自分がはじめて映画館で映画を見たのは「宇宙戦艦ヤマト」の劇場版だったと思うが、今ひとつ記憶が定かではない。近所にあった映画館に、たしか祖父が連れて行ってくれたような気がする。昔の映画館は今よりももっと非日常感にあふれていた気がするけれど、
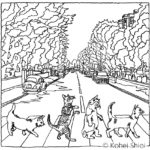
「父さん、大きい声出さないで、アリさんだよ」と子どもに言われた。自分は大きい声など出していないし、直前まで大騒ぎしていたのは子どもの方である。これは大人の言ったことをそのまま模倣する「モデリング」というものであり、この少し前に大声で叫んでいた子どもに
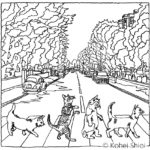
子どもには怒ることもあるけれど、それがどうしていけないことなのか、なるべくきちんと説明をしようと心がけている。息子はまだ3歳で大人の話がきちんと理解できるとは思わないけれど、とにかく自分の言葉でどうしてそれがいけないことなのかをはっきり説明
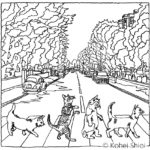
3歳になった息子は、このところ言葉での表現が一気に広がってきた。言葉が増えるということは、様々な意思の疎通がより細かく出来るようになってきたということでもある。「イヤ」と「したい」がかなり具体的なものに変化してきているのだ。