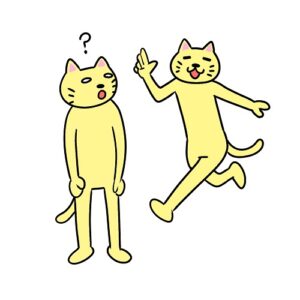
8080号室で綴られているもう一つの文章『誰かのために』では、見知らぬ暗殺者の〝人違い〟によって、憎き相手を抹殺しようと、主人公たちが企んでいる真っ只中。
個人的には、暗殺となどという大それた企てを、完全に他力本願で押し進めようとする主人公たちのことを「なんじゃそれ」と呆れる気持ちを抱えつつ、実際、世の中には、意外と〝人違い〟が溢れているとも思うのです。
私は目が悪く、最近では、加齢による視力の低下、つまり老眼も始まってしまったので、持っている眼鏡やコンタクトがどれもあまり目に合っていないという有様で、付けたり外したり細めたり広げたりするのにほとほと疲れ、車の運転と料理と機織り以外は、極力眼鏡の類を外して〝ぼんやり〟させながら日常を過ごしているのですが、そういう時に決まって、通りの向こうから歩いてくる〝知り合いのような人〟に遭遇するのです。
よく見えなくて相手が誰かわからなくても、それがすごく親しい人ならば、それこそ他力本願的に相手にその判断の全てを委ね、「あ、ぶぶちゃん!」と私に気づいて声をかけてもらうことを待つか、「あー、ぶぶちゃん……」と気づいてはいるけど面倒だとか急いでいるとかで、スルーしてもらうことを待ちます。
どっちに転んだとしても、それはそのとき相手がそうしたいのだし、それによって今後の関係にヒビが入るとかもないので、相手の採択を受け入れて受け流します。
問題は、あまり親しくないけど恩義や好意や義理を感じている人の場合で、この人たちには、他力本願は通用しません。
立場上、自分のほうが下だったり、新人だったりすると、ここでの「(見えてるくせに)気づかなかった」は、今後の人間関係における縺れの結び目になり得るので、できれば回避したい。縺れを解くのって、めっちゃ面倒だし、苦手なのです。
だから「気づかなかった」は避けたい。でも見えない。
というジレンマが生じるのです。
素直に「目が悪くて見えなかったもんで……」と言って逃げる、という方法もあるけれど、厄介なことに、〝ぼんやり〟にも関わらず、好きなものや人は、なぜかよーく見えたりするんですよね。だから「私のことは見えなかったのに、あそこでパンが30%オフだったのは知ってるんだ、へえ」とか言われたりするんです。なんで? なんで?
そんなわけで、このジレンマを解消するために編み出した私の作戦は、とりあえずフレンドリーな笑顔を作って軽く右手を上げておく、というものです。
相手が果たして本当に知り合いであった場合も、これで概ね乗り切ることができます。
大抵の場合、別にお互いに立ち止まって話したいというわけではないので(稀に話しかけてくる人もいますが、その場合は今の季節なら「暑いですね~」でOK。その点では猛暑も役に立ちます)、相手をきちんと認識できなくても大丈夫です。重要なのは、「あなたのこと、ちゃんと見つけましたよ」というメッセージの発信と、親しみやすさのアピールなのですから。
(相手が「ここは見逃してくれよ」の場合は、さにあらず)
相手が全くの人違いで、全然知らない人であった場合も、この方法は有用です。
人がたくさんいるところでは、あたかもその人の後方に目当ての〝知り合い〟がいるような素振りをして、その人の脇を通り抜けます。
あまり人がいないところでは、怪訝な顔をするその人とのすれ違いざまに、少しはにかんで、緩く上げたその手をゆっくり下げればいいだけです。
それだけで「ああ、人違いだったのね」と相手は思ってくれるでしょう。
この方法をやりだしてからというもの、私は〝人違い〟を全く恐れることがなくなりました。
眼鏡等を着けている時に冒してしまった人違いの際の気まずさも、このやり方で回避することができました。
ところが、こうして過ごしていると、いつしか〝人違いされる〟ことも増えてきました。
知らない人に「〇〇だよね!」と腕を掴んで声をかけられたり、人違いだと否定しても「いやいや。〇〇さんでしょ?」と横車を押し続けられたり。あまりに自信満々に人違いされるので、自分の記憶を疑うほどにまでなりました。
そして、ふと思ったのです。
これって、願望なのかな?って。
誰かが私を誰かと間違う時、私が知らない人を知り合いと間違う時、誰かや私の心には確かにその人がいて、その人に会いたいと思っていたのではないか。
1940年代後半の心理学において、知覚における、ある一連の研究が盛んになりました。
ものを見たり聞いたりして認識するという人間の知覚において、私たちは、それぞれの感覚器官に到達した音や光や温度のような刺激をありのまま受け止め知覚しているわけではなく、その時々で、こうしたいと願ったり、こうだろうなと期待したり、こういうものだと決めつけたりする、その人ならではの要因が、その知覚に大いに影響を与えています。つまり、知覚の過程には、知覚者の欲求や期待、判断が反映されるのです。
このような考え方に基づく一連の研究群のことを、『ニュールック心理学』と言います。
有名なものでは、金額の高い硬貨ほど大きく見え、その傾向は経済的に余裕のない社会階級の人ほど強くなる、という研究や、口にするのも憚られるようなタブー語は、タブーではない語に比べて長い時間見せないとなかなか認識できない、という研究です。
実際に、私も大学の授業で学生たちに、日本の紙幣の千円と一万円札の大きさを現物を見ずに推測して描いてもらうと、概ね3割程度の学生は、一万円札を横のみならず縦も少し大きく描きます(実際は、横は一万円札が1センチ長いが、縦は千円も一万円も同じ大きさです)。
「幽霊の正体見たり枯れ尾花」という句がありますが、あれも、「そこに幽霊がいるはず。怖い怖い」と思っている気持ちが、ただの薄を幽霊に見せてしまうことを表しています。
他にも、喉の渇きを抱えながら砂漠を彷徨う旅人が、ありもしないオアシスの幻影を見つけて駆け寄り、救い上げると砂だった、なんてものも、この『ニュールック心理学』の考え方を表しています。
「ある」「あってほしい」と思っているとそれが見えてしまう、あるいは、「ない」「あってほしくない」と思っているとそれが消えてしまうということばかりでなく、心から欲しているのに手に入らないものに直面した時も、人はそれを〝なかったこと〟にしてしまったりする。
私が大好きな高野文子さんの『るきさん』という名作漫画において、こんなシーンが描かれていました。
主人公るきさんが、暑い中、道を歩いています。前方から子どもが美味しそうなアイスを舐めながら歩いてきます。るきさんは、アイスが食べたいと思います。ところが、そのあたりにはアイスを売っている店がないのです。
るきさんは、そのアイスを見つめます。すると、子どもが手にするアイスのあたりがかすんでくる。というものです。
その話を、るきさんは友人のえっちゃんに話します。えっちゃんは言います。
「かなわないときなのよ。脳がアイスを抹殺しちゃうの。るきを不憫がって」
このような心理には、不都合な出来事から心を無意識的に守ろうとする『防衛機制』と呼ばれるメカニズムの『抑圧』や『否認』が作動していると考えられています。『抑圧』とは自分を脅かすようなものを認識できない心の奥深くへ押し込めてしまうことで、『否認』とは実際に起こっていることを認めないようにしてしまうことです。
「とても暑くてアイスを食べたい」のに手に入らないるきさんは、自分の心を悶えさせるアイスを知覚の世界から追いやることで、心の安寧を保とうとしたのかもしれませんし、子どもが手にするアイスを消しゴムで消すように見なかったことにすることで、食べられない自分を癒そうとしたのかもしれません。
もし『ニュールック心理学』の考え方が反映されるなら、私が誰かを人違いする時、あるいは、誰かが私を人違いする時、きっとその心には、「あの人に会いたいなあ」という願望や「あの人がいるに違いない」という期待があるのかもしれない。
そう思ってみたら、誰の人違いも「その人に会いたい」という心の表れで、その人の目にはそう見えたんだなあと思うのです。
他のものは〝ぼんやり〟なのに、好きなものや人のことはよーく見えるのも、きっとニュールックのせい(これは実際に『知覚的促進』と呼ばれる現象です)。
だから、人違いは、違っているけど、違ってないんです。いや、違うんだけどね、実際。
(by 大日向峰歩)
*編集後記* by ホテル暴風雨オーナー雨こと 斎藤雨梟
今見ている世界が自分にとって理想的な世界である可能性があるのですね。それならそれでもっと都合良くならないもんかと思っちゃいますが、想像力のリミッターというやつでしょうか? それはそうと、人違い「される」側に何か原因となる要素ってあるんでしょうか。人の願望の依代となりやすい、シャーマン体質とでもいうのか。それってどんな人も演じられる俳優の才能と同じ? じゃあ、間違われやすい人は名優の素質あり!?……脱線しすぎました、来週は『誰かのために』暗殺(遅刻させ)計画が本格化します。どうぞお楽しみに!
作者へのメッセージ、「ホテル暴風雨」へのご意見、ご感想などはこちらのメールフォームにてお待ちしております。