このお話は斎藤雨梟作・SF小説『N生児の星』の第2話です。第1話はこちら、全10話で完結予定です。

N生児の星©︎SAITO Ukyo 斎藤雨梟
「昔は姿かたちが似るのは不思議な、時にそれを通り越して、禍々しいことでした。私たちのような双子も、もっと古い時代には不吉とされ、片方は棄てる習わしだったというから恐ろしい。でも、私たち姉妹も生後間もなく揃って棄てられていた子です。親が古い俗信で双子を嫌ったとすれば、これでもまだ、早く生まれ過ぎたのでしょうか」
客は聞き手に回るなり押し黙り、わずかに首をかしげたまま微動だにしないのは、人工体のひとつかと思わせるほどだった。剣崎は腕組みをして下目遣いに相手を伺うと、そのまま遠くへ目を移し、言葉を継いだ。
「宮ヶ瀬球との出会いは忘れられません、あの時、狭い部屋にそっくりな人間が四人、いたのですよ――今ならば珍しくもないことですから、古い物言いを引きましたが――世の中にいるという同じ顔の五人の人間のうち、四人までが揃うとは当時にしてみれば驚くばかりで。もっとも、うち一人は実は人間ではなかったのですが」
ちらりと見やった若い来客の顔には依然、まるで表情の変化がない。剣崎の瞳には、不審げな、逆に得心したとも取れる、複雑な色差しがあらわれた。だがそれも、小さな果実がソーダ水に沈み、すぐに気泡をまとって浮かび上がるほどの、ほんのひとときの移ろいだった。
「まだ世界が国に分かれていた最後の頃です。『国』が今の『地区』とは似て非なるもの、主に地理的に濃縮された遺伝子を共有する、原始的な集団だったのはご存じでしょう。私の育ったジャパンは黒髪に黒い瞳の人ばかりが住み、私の――あなたも同じですね――灰がかった緑色の瞳などは、誰もが外国の血と疑わず、珍しがるような国でした。ええ、おっしゃる通り、生きていた言葉も、公用語でもあった古いものがひとつきり。その後共通話を覚えたおかげで、こうして神経同期に頼らず話せますが……何ですって、ジャパニーズをお話しになる? ええ、私はその方が不自由がないくらいですが」
客の突然の提案がよほど思いがけなかったか、蝋のように白かった剣崎の頬にかすかに赤みが差した。持ってまわった口調の「連邦共通話」をやめ、くだけたジャパニーズを口に乗せると、自然と剣崎の舌はなめらかに、表情も多少の起伏と変化を得てゆくようだった。
*
ああ、驚いた、日本語ができるなんて。へえ、親が日本の出と聞いて習ったの。決まった親がいるのも珍しい、今は遺伝上の親が誰とも言えず大勢いる人が多いのに。それがセントラルで習うジャパニーズね、癖がなくて水みたいだ。私は東京で育ったんです、遷都前の。そのへんの方言が一応、日本標準語だった頃で、まだ海に沈む兆候もなかった。後の混乱と遷都とですっかり変わって、私たちも養い親と家をなくしましたが。あの頃の東京は、J地区の長老どもに言わせれば随分壊れて汚れて、もう古い良いものなんぞないから捨てた方が良かったそうで。なるほどごもっともだが、壊れて汚れた言葉で育った後、これからは共通話だ、すぐに次は言葉なんか要らない世の中だ、なんてことになって捨て置かれたら、いつまでもその汚れた刻印が消えずに残る。私の言葉はそういうもんです。
望が造形作家になったのは遷都の後。もう珍しかった猫や犬、栗鼠や鹿や鳥なんかを本物そっくりに作った。動物が減ってきた頃は、その説そのものの妥当性を含めて、どうするべきか、せざるべきかと論争の種だったと聞きますね。でも、明らかに取り返しがつかないほど減ってしまえば、誰もが安心して滅びゆく生き物を懐かしむ。そんな段階に入った時代でした。今から思えば、まだ余裕があったんでしょう。ともかく、望はたちまち、注文者が列をなす売れっ子になって、二人分の生活を支えてくれてた。残念ながら、望の了解が取れたとしても、当時の作はもう大して手元には……おや、違う? では見たいものというのは……?
そうですか。私の話を先に聞きたいならば続けましょう。
(次回につづく)
斎藤雨梟作・『N生児の星』2 いかがでしたでしょうか。次回をどうぞお楽しみに!
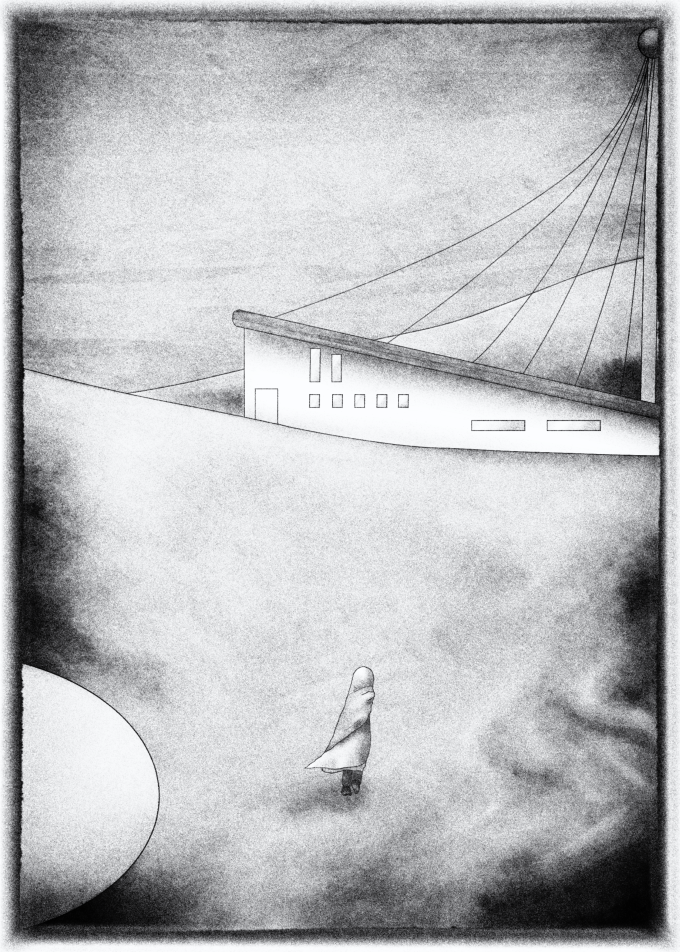
※ホテル暴風雨は世界初のホテル型ウェブマガジンです。小説・エッセイ・漫画・映画評などたくさんの連載があります。ぜひ一度ご覧ください。<連載のご案内> <公式 Twitter>